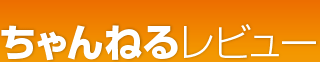3.91
3.91
| 5 | 356件 | ||
| 4 | 188件 | ||
| 3 | 24件 | ||
| 2 | 23件 | ||
| 1 | 116件 | ||
| 合計 | 707件 |
ある公卿が雑記のようなものに「源倫子は背が低く太っている」と、書き残しています。
源倫子が身目麗しいと書いている文献は見当たりません。倫子が人並みの容姿ならば冷泉天皇、円融天皇、花山天皇のいずれかに入内していたとしても不思議ではありません。しかし、そのような縁組の話があったという文献も見当たりません。倫子には年齢が近い同母・兄と弟がいますが、彼らは自ら仏門に入っています。よって源雅信の正妻の長女・倫子が、土御門邸や源雅信とその正妻の所有する荘園を相続します。道長は倫子の経済力に魅かれ、倫子を正妻にしたのだと思います。財力と権力の権化のような倫子と道長が、真綿で絞殺すように一条天皇をじんわりと追い詰めていく姿が鬼畜のようにみえます。
どなたか歴史に詳しい方、倫子の兄と弟が仏門に入った理由を教えていただければ幸いです。
このドラマは、当時の上級貴族のお家事情、経済、外交、軍事(武士の起こり)、民衆の苦労など、ほとんど描かれておらず、まひろとミチナガの頓珍漢なラブストーリーばかりで全く面白くないです。
道長が己の欲のためではなく、民草のためぞという大義名分で、自分の中に芽生えつつある醜い欲をひた隠しにしようとする姿がなんともいえない。
聖人君子よろしく、自分の欲は一切ございません、なんて人はいないって。まひろの前だけでは手に入れられなかった女を囲いたい欲も権力に対する欲もポロポロと隠せずこぼすけど、そういうところが憎めないだよな。
実資さんが周囲の顔色を気にせず、自分が是とすることだけを貫く態度や、行成があれだけ帝に尽くしながらやはり一番は道長であるところとか、脇を固める役者さんたちが実に素敵です。
さてさて、東宮が立ったところで、三条天皇様はどうなりあそばすのか。ちょっと恐ろしいが、恐ろしいもの見たさが勝る次回です。
病で一条天皇が譲位して、次の東宮が敦成親王に決まったが、それにより陰でそれぞれの思惑が錯綜して面白かった。次の天皇の三条天皇はいづれ自分が落とされる予感がしたのか道長に対抗意識を燃やす。東宮にならなかった敦康親王側の清少納言はまだ諦めないと気丈に反発した。彰子は母のように可愛がっていた敦康親王を差しおき黙って敦成親王を東宮にした道長への怒りで初めて逆らった。成長著しい彰子は将来国母になる片輪を見せて頼もしくなって来た。そして逆らう彰子に政(まつりごと)を行うのは中宮様ではなく私であると厳しく引き離す道長の気迫の瞳に引き込まれた。これから道長は闇落ちして悪の権力者になって行くのか、それとも世のため、民のためにあえて悪を装うのかこれからの道長に目が離せない。
道長もっと野心家でもいいのにね。
実際はハラスメントレベルの圧を一条にしてたろうに。
道康親王はどうすんだろ。鎌倉殿だったらまず消されるでしょうねえ。
いやいや野心を隠さなくなってきてるでしょ道長。
どうなっていくんでしょうね、楽しみ。
すっかりまひろは傍観者になっていた。
道長が主役で紫式部が脇役でもいいのかと思いました。
主役である道長をサポートする役目にすればよかった。
ついに一条までお隠れになってしまったか。
今までお疲れ様でした。
塩野さんを代表する役になっただろう。
次回は選挙で放送時間変わるので注意です。
↑の方、ありがとうございます。
そうか!選挙で時間、変わるのか。
ネットニュースでクランクアップの記事があり、道長が出家した姿を見たら、あとはラストまでカウントダウンなんだと思えてきて、心の底から悲しい。
こんなに大河を毎週楽しみにしていたのは初めてだった。
闇落ちしているのは、藤原道長ではなくて、間違いなく清少納言ですよね。あそこまでネチネチと道長と彰子を恨むとは、ちょっと病的過ぎます。もっとも、それはそれでお話としては、それなりに面白いと思うのですが・・・。とにかく、この大河ドラマは、終盤に差し掛かってからも、その勢いが、まったく落ちないんですね!!
※史実として、藤原道長の長男・頼通と退けられた敦康親王は、非常に仲が良く、それほど道長が、その敦康親王を嫌っていた訳では無いと思うんですけど・・・!!
※藤式部( 紫式部 )は、敦成親王が帝になるまで中宮・彰子を支えて行くことになるのですが、これからのお話にも、凄く期待が持てるんですね!!
「八重の桜」の実質的な主役が山本覚馬だったように、今作の実質的な主役は間違いなく「藤原道長」。源氏物語と紫式部という知名度は道長よりはるかに高いから視聴者を誘導するために利用したにすぎず、劇中においても大したことをしていない。
道長の野心もありながら、心労すごいね。自分の理想を実現するために、非情にならざるを得ないときもあり、自分に都合のいい人間で回りを固める必要もある。今も昔も政治ってそういうものだよなあと思う。
まひろの娘に近づく武士の従者はオリキャラなんだよね?下賤な者として、いとに邪険にされてるのがちょっと笑える。惟規亡き後、政情が緊張を高めていくなかで、ホッと息をつける存在なのかな。
清少納言は陰険に描かれてるね。紫式部が主役だから、仕方ないのかもしれないけど。逆恨みされる彰子中宮がかわいそうだ。仲良く過ごしてきた敦康親王とも遠ざけられて。今後、聡明な中宮がさらにどう変わってゆくのか楽しみだ。
クランクアップに感慨に耽ってたらなんと柄本佑くんは伸ばした地毛を剃られたようでビックリ!お忙しいだろうに今後の仕事は大丈夫なのかな?坂の上の再放送もやってますがお嫁さん家族含め柄本ファミリーはなんか凄いなぁ
平安高官貴族も大変だ。
偉くなればなるほど、子ども達の事を思えば思うほど、家族親族には疎まれ、今度の三条天皇は一筋縄では行かなそうで、道長もストレス満杯!
妻明子の子どもは望む官職を道長に拒まれ、延暦寺に出家(これまた、激しい性格だこと)!予告?では、その明子からピンタはられて、道長、敵は外にも内にも。
どうする道長!偉くなった道長はどうするの連続!
これでまひろと道長の決定的瞬間を倫子様に見られたら、最悪。
そんな道長のオアシスは、まひろ。中高年のソウルメイト、これは若い時以上に忘れられない存在。いいね。この流れ!
紀行ガイドでは公任を紹介。父親藤原頼忠を早くに亡くしていたからかはわからないが、彼は直に出家して和歌を詠んだりしたり歌会を催したりして、穏やかに暮らしたと紹介されていた。四人の若手イケメン貴族の中高年の生き方、いろいろだろうが、こんな生き方もいい。
三条天皇と道長の権力争いが始まり、まひろが書く源氏物語も終盤を迎え、まひろと道長の運命も佳境を迎え盛り上がって来た。亡き伊周に代わって道長派に逆らう清少納言の厳しい表情が怖くなった。彰子はまひろの助言で彰子の弟たちと仲間を作り道長に抗う。後に彰子が立派な国母になる布石か、まひろの娘賢子と双寿丸の仲はどうなるのか、まひろはじめそれぞれの人物たちの運命の終着を見守りたい。
誰が何をしました的な教科書的年表を追う史実中心重厚大河など知ったこっちゃないお得意の作風男と女を中心に貴賤関係なくいつの世も変わらない普遍「人間のおかしみ」を核に置く大石脚本が面白い。時代の枠組みの中で、はみ出たり出なかったり利害損得結局好きや嫌いで色をつけ己でも解らぬうちに時を経て俯瞰で見られる人間の生き様がデザインとして後々残る。リアルと空想に思いを馳せどんな時代も人間とは面白く愛しい生き物だと感じる創作力に感嘆です。
賢子役の南沙良さん良いですねえ。なんかホマキを思いださせます。
敦康の気持ちわかるわ。見えそうで見えないのは見たくなってしまう。
あれ?道長ひょっとして孤立しちゃった?今後どうなることやら。
俺より先に死んではならんて関白にはなってはいないが
関白宣言じゃん(笑)
今回のお話は、あの「 源氏物語 」の光源氏が亡くなって、これから新たに始まる『 宇治十帖 』の物語に掛けていたんですよね。余りにも大石静さんの脚本が上手過ぎて、いつも惹き込まれてしまいます。そして、藤原道長がまひろ( 紫式部 )と二人で一緒にいる時だけ素の自分をさらけ出す描き方は、凄く良い感じに見えるんですね!!
※史実として、紫式部と藤原道長は、身分を越えた冗談を言い合ったり、道長が彼の長男・頼通の結婚相手を紫式部に相談したりしていたことが「 紫式部日記 」の中に書き残されていますので、お互いに男と女の関係が無かったとしても、かなり親しい関係にあったのではないでしょうか!?
※「 源氏物語 」の『 宇治十帖 』は、その書き方の文体が、それ以前と少し違うこともあり、作者が紫式部では無くて、彼女の娘の藤原賢子( 大弐三位 )だと言われているんですね!!
道長とまひろが川縁のお散歩…って、無理がない!?
道長邸には、百舌彦しかいないわけでもあるまいし、口さがない女房達も大勢いるだろうし、何よりも倫子と鉢合わせしたら、どうするの!?
それとも、別邸? 広い邸宅の端?
道長、杖をつきながらでも、歩けたんだ…。
二人で川を流れよう…だっけ!?のるか反るか…運命の分かれ道だったのかな!?来週の予告に復活して出てなかった!?
道長がまひろに
俺より先に死んではいけない。
関白でない道長の関白宣言が面白かった。
道長だいぶ三条天皇にやられてますなあ!
儚げな一条天皇も美しくて毎回楽しみでしたが三条天皇も力強い美しさで良い良い!!
今までの大河での天皇って威厳の有る方・品の有る方が多かった気がするが今回の一条天皇と三条天皇はそれプラス美しい。
平安の雅な世界観に良く合っています。
現代劇と違い古典的な世界には『雅』『儚さ』『美しさ』はスパイスになって良い効果をもたらすのかもしれませんね!
まひろ(紫式部)が書く源氏物語を現実に進行する本編と巧みに絡ませて面白い。源氏物語は主人公光源氏が亡くなり一旦休止して、その後執筆を再開して光源氏の子孫の時代を描いて締めくくった。ドラマはまひろと道長は子供の頃出会った同じ川辺で語り合う。病で弱気を見せた道長はまひろに俺より先に死んではならぬ、お前は死ぬなとまひろを気遣い、まひろも道長様が生きれば私も生きられると励ました。道長はまひろの優しさに権力者としての孤独と病で疲れた心が癒されて感情が込み上げて号泣した。感情を曝け出す道長に新たな一面を見たまひろは影響されて新たな気持ちで休止した源氏物語の執筆を再開した。源氏物語を巧みに本編に絡ませた脚本が秀逸でした。
道長は糖尿病で目が見えなくなったんだっけ。
先日あさイチに出てたけど綺麗な光る頭になってたね。
怪文書は誰が書いたんだろうね。
時々こういうことが起きるが誰がやったか謎のままが多いね。
キヨコはなんか最初からあんま聡明そうに見えなかったが、
ついにアル中になっちゃったのか🍶
源氏物語の幻の巻きで光源氏が弱って亡くなることをほのめかしていたが具体的には光源氏の死を書いていない。ドラマで描かれたように雲隠れの題名だけ書いて白紙のまま源氏物語は終わっていた。そして源氏物語が再開したときには子孫の代の物語だった。何故源氏物語の終了の雲隠れの巻きは白紙だったのか、なぜ源氏物語の執筆を再開したのか、それらの謎をドラマでどう描かれて行くのか楽しみです。
今回のお話は、ある意味、ロバート秋山さんが演じる藤原実資の独り舞台になっていましたよね。もっとも、実資は、筋を通せば通すほど、ちょっとズレて来ていたように思うんですが・・・。そこが、凄く面白かったです。そして、双寿丸の賢子に対しての男らしさには、なかなか爽快なモノを感じましたね。やはり、このドラマの脚本は、それだけ秀逸なのだと思います。ですから、後数回で終わってしまうのが、とても惜しいような気持ちになるんですけど・・・!!
※藤原隆家が大宰府に赴くお話の展開になって、いよいよ “ 刀伊の入寇 ” のエピソードが出て来そうですね。果たして、この大河ドラマでは、それをどこまで描いていくのでしょうか!?
※史実によりますと、藤原道長の長男の頼通が具平親王の娘である隆姫女王と結婚したのは、「 紫式部日記 」の中で、その具平親王と姻戚関係にあった紫式部に道長が相談したからだと書いてあったんですね!!
私の中の光る君と齟齬を感じてきた道長と距離を取りたい行成しかしタイミング悪く太宰府行きは隆家に…「お前はわたしのそばにいろ」没年月日まで同じの2人その死の際さえ道長ばかりがクローズアップ最期まで光と影として連れ添うこの2人にも運命を感じます。そして次回は望月の歌ですか巧い運びですね。
そろそろ、終盤、回収へと!説明的大河ドラマも必要だ。
行成、清少納言、道綱はこれでこの先決定かな。公任は紀行ガイドでやったから、ナレ終わりかな。一年間慣れ親しんできたドラマの終わりは寂しい限りだが、来週はいよいよ、この世をば〜を道長吟ずるか⁈山場中の山場!
三条天皇は即位が遅かったのか、目も耳も見えない、聞こえない病とは?
あとは彰子と東宮?の源氏物語を期待するが、時間的に無理があるね。それと、そろりと出てきた双樹丸、伊藤健太郎の存在は普通の若者だよね。
奇しくも、道長、まひろは62才で亡くなっている。年代は違うが!今、あの世で道長は自分の人生をどう振り返りながら永眠しているのか。
賢子の初恋。おそらく双寿丸は架空の人だよね。
ついていくのは、ムリムリ無理!
料理ひとつ作れるわけでなし、荒くれ武者の足手まといになるばかり。
賢子って、この後、どーゆー人生を歩むんだろう。
もうすぐ終わりかと思うと寂し過ぎる。
道長の人となりの役作りがとっても微妙でよく分からない私
全般的には自らの権力と栄華を欲して居るようには見えない
御上の退位を勧めるのも目や耳が聞こえないという状況ではおかしくはないし
御上が推薦する人物も「御上自身のため」が目的と見極めた場合は諫めるのもおかしいとは思えない
でも自らの血筋の子を至尊の地位につけようとするのは自己の権力基盤を盤石とするためですよね
うーん
どういう人なのだろう
「人民の暮らしを上向かせたいという気持ちが根底にあり、そのためにはまだまだ自分が高い位にいて政治を執らなければならないと考えている」
「自分が高い位で長く政権を握るためには血筋の者を至尊の地位につけ、(本人の意思に関わらず)手足になってくれる部下を傍に置き続ける」
という感じでしょうか
完全な無私・誠実でもないが決して悪ではない、くらいな。
歴史教科書で習った、道長の増長・傲慢を体現したとされる句
「この世をば、我が世とぞ思う、望月の欠けたることなしと思えば」
この句がこのドラマではどういう気持ちで詠まれたものになるのか
上記の通り道長の人となりをまだ見極めることができない私にはリトマス試験紙のようなシーンとなりそうです
次週が気になります
三条天皇と道長との覇権争いが激しくなって来た。
目も耳も悪くなりそれでも譲位を頑なに拒否した三条天皇
の強情さに圧倒されました。まひろの娘賢子と恋仲になった
若武者双寿丸は主君に従い大宰府へ、敦康親王についていた
隆家も大宰府へ行くことになった。大宰府といえば刀伊の入寇が
あり史実通り隆家の活躍が楽しみです。
まひろは源氏物語の終盤の浮舟の下りを書いているらしい。
次回の予告では道長が権力を我が物にしたときのあの有名な望月の歌を
披露していた。いよいよ終盤に差し掛かり盛り上がり面白くなって来た。
天皇なんて形だけで実際には何の権力も持っていなかったからこそ長続きしたのだと改めて確認させられる。日本国内でも政権を握っていた一族は時代とともに変化したが、天皇家が滅ぼされることは無かった。傀儡天皇だったからこそで、中国のように王朝が変わったら一族もろとも滅ぼされていたのとは大きく違う。
前に知恵泉で隆家やってたけど実資との話出てきたねえ。
刀伊の入寇はやるのかな。
双寿丸はもう帰ってこないフラグビンビンだな^^;
なんか最近出てくる姫達の名前が難読になってきたような(笑)
振り仮名ないと読めないよ。
いよいよ望月の歌を詠むのか。楽しみだこれは。
最後の演出で、てっきり、道長はこれで逝くのかと思いました。
でも、予告に出ていた。
あ…違ったのね。
うわー
望月の歌、学校で習った道長の増長・傲岸不遜を体現したものと習いましたが
このドラマでどう解釈するのだろう、と思って楽しみにしていました
でも
この演出では私ごときでは全く分からなかった(;'∀')
藤式部は道長が歌を詠んだ後にちょっと驚いた表情をした後に薄く微笑んでいましたよね
「自分の思いのままにできる世の中」という解釈をしたのか、そうではないまた別の意味を感じ取ったのか
分からなーい
どなたかご自身の解釈をぜひ書いて頂きたいです
他の人がどう看たのか、気になります。
あの藤原道長の心情を詠んだ「 この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも なしと思へば 」という歌は、「 この世で自分の思うようにならないものはない。満月に欠けるもののないように、すべてが満足に揃っている 」という傲り高ぶった意味の歌ではなくて、「 今夜は心ゆくまで楽しいと思う。空の月は欠けているが、私の月 后となった娘たちと宴席の皆と交わした盃は欠けていないのだから 」という意味の歌だと言われているんですよね。そうでなければ、うるさ方の藤原実資が「 そのような優美なお歌に返す歌など御座いませぬ。今宵も皆で唱和致しましょう 」と出席者全員に呼び掛けて、一同がこの歌を数回吟詠することがなかったと思うんですけど・・・。いずれにしても、このドラマは、最終回が近づけば近づくに連れて、その内容が、かなり濃くなって来ましたね。ですから、いつも、非常に見応えがあります。やはり、これこそが、本当の意味での大河ドラマだと感じるんですね!!
※もしまひろ( 藤式部 )が藤原道長の人生を書くことになれば、彼が三郎と呼ばれていた時代のことから書かなければならないので、間違いなく二人の仲が源倫子にバレるのが目に見えて、それは、ちょっと書けないのではないかと・・・!!
道長の人生
右大臣兼家や道長三兄弟のこと
百舌彦を連れて都の街中によく出歩いたこと
政には大して興味が無かったが、盗賊を無下に殺した検非違使への怒りから、今のままではいけないと決意したこと
ま、呪詛や疫病にも負けなかったからね
大鏡の雲林院での語りに任せておけばいい部分もありますね
思慮深さと観察眼の倫子さんは、すべてのピースを埋めているはずですが、紫式部を責めることはないでしょう
源氏物語に表れる彼女の生き方や人目を忍ぶ恋心を理解しているはず
貴族女性は、生贄、道具、我慢、等々、辛いですね
予告で、猫さんを愛でる倫子さん、年齢を感じさせる赤染衛門…それぞれ落ち着くべきところに落ち着いていくようですね
2024-11-17 20:51:02さん
2024-11-17 20:49:25のものです
ありがとうございます!
そういう説もあるのですか~
でもそうなのですよね
学校で習った通りの解釈があのドラマのシーンだったら、実資があの場で
穏やかで居るはずがありませんよね
なるほど、勉強になります!
そういう目でもう一回、見返してみようと思います(●´ω`●)
※藤式部への道長の記録の件
わたしも同感です
まひろの性格からして、道長との関係に一切触れずに書くということもできないと思いますし。
まひろから更に頼まれて他の人に書いてもらうとかあるのかなー
道長、兄二人が早逝した為、宮中の官職に。そこから始まる高みへの人生。
道長はかなりの策士、やり手だと思う。幼い時から。一方、去る者は追わず的な面もあり、今でも充分モテたと思う。
平安時代中期というと、寝殿造り、官位束帯、綺麗な姫達など、衣食住と美術品をサラッと学び、道長、頼道を知り、直ぐに武士の起こりから源平合戦へと。のっぺりした時代との印象。それが兼家から始まる藤原氏を、関わる人達を詳しく描いていて良かった。
道長の望月の歌は残念!皇居歌回始めでは、当時の慣習を踏襲して、皇室の方々の短歌を読む人が一句3分はかけて読み上げる。昨夜のは甲高い佑の詠み、それに続いて、廊下に座る貴族たちのリピート唱和!あのような句を詠んだ歴史上の人物は私の知る限りいない。もう少し盛り上げて欲しかった、せめて2回詠む、普通そうなんでは?
道長の歌の通り、もはや道長に違を唱える者はいないだろう。仲良し貴族四人とは差をあけ、本音を言える貴族はいるだろうか。
必ず欠ける満月。来週も楽しみです。回収回収の嵐でしたね。
「英雄たちの選択 刀伊の入寇」観てたら、関白道長は極悪人。民の幸せなんて嘘をついて望月の歌を詠む。道長を大河の主人公にすらるにはかなり無理がある。
おととい16日の土曜日18:45からのNHK関東地方ニュースで平塚市博物館のプラネタリウムが平安時代の夜空を再現しているというニュースが取り上げられていました。プラネタリウムではもちろん今回の望月の歌も紹介しているのですが、公式SNSで「#道長と同じ月を見上げよう」という企画を立ち上げて16日の土曜日の夜空の月を写真に撮って投稿するように呼びかけたそうです。
その理由が、道長が望月の歌を詠んだ旧暦の10月16日とは現在の11月16日に当たるそうで、その日と同じおととい土曜日の夜の月の写真をアップさせるという洒落た企画だったのです。
つまりなんと今回の「望月の夜」は道長が歌を詠んだ翌日を狙って放送したのだという驚愕の事実! いやーまさか放送回を史実通りに合わせる凝った設定だったとは。脚本というより制作スタッフが企画段階の最初から長きにわたって準備してきたのでしょう。
ちなみに博物館によると道長が歌を詠んだ時間帯は満月から半日ほど経過した「わずかに欠けた月」だったそうです。
百舌彦の粋な計らいで、道長のいる宇治に駆けつけたまひろ。憔悴した道長の姿を見て涙するまひろ。この辺りからドキドキしてきました。久々に二人きりでゆっくりと会える二人。どんな会話をするのか想像するだけでときめきました。そして、二人とも「もう終わってもよい」と思っていた。まひろは一緒に死んでもよいようなことを言い、道長は生きていてほしい、と言う。まひろは一緒に生きるならばと言う。年齢を重ねた二人の会話。抱き合うことも触れることもなく、距離を置いて静かに話す二人。だからこそ、二人の老いとこれまでの深い絆を感じた素敵なシーンでした。
いよいよ残り数話クライマックスに向けて盛り上がって来た。道長は三条天皇を譲位させ、孫の後一条天皇を即位させ、息子頼道を摂政にして、一家三后を成し遂げ、道長の政権を盤石にした道長は、娘威子の中宮を祝う宴で詠んだ、【この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも 無しと思へば】は後世の人々や歴史の専門家たちから様々な解釈で語られて来た。栄華を誇った道長の増上慢を表したものや、「この世」は「この夜」を掛けたもので、「望月」は同僚たちと酌み交わした丸い盃と三后の独占の二つだとされた。
または後一条天皇が生まれた5日目の儀式で紫式部が詠んだ、【めずらしき光さしふ盃はもちながらこそ千夜も巡らせ】を道長がモチーフにして望月の歌に変えて詠んだとされた。それを思うと、かつて満月夜、まひろに道長が約束した民の為の政を叶えた想いを望月の歌に託してまひろに伝えたのだと思うと感慨深かった。
ここでいう道長のことを書いた書物というのは、「大鏡」のことてすよね?
かなり道長に近しい人が書いたと言われていますが、作者は不詳なので、それがまひろであっても赤染衛門であっても不自然ではないか。
ほんとに上手に史実をとりこみながらストーリーを作り、各登場人物をこのドラマのキャラとして(実際の姿はどうあれ、分からないことだし)たてるなぁと感服。
栄花物語のことじゃないんか?
長女が一条帝へ、次女が三条帝へ、三女が後一条帝へ入内した。そして道長は四女へも「役割がある」みたいなニュアンスのことを言っていた。後にやはり入内する。四姉妹(一人異母)が天皇妃となる栄誉を喜ばない人はいない。我が世の春と奢り高ぶり「望月の唄」を詠んでもおかしくない。いやむしろその方が人間らしい。その唄に応じなかった実資も立場をわきまえている。下手に応じて道長の機嫌を損ねないようにとの自衛本能であったのだろう。さらに皆で唱和するというのも機転が利いていた。道長はその方がより気分がよかったと思われる。
なかなか興味深い内容だった。ただ紫式部が脇役になってしまっていることが気になっている。また個人的には一条帝の華やかな時代における彰子との愛の語らいをもう少し長く見たかったというのが本音である。
望月回面白かった。
まあ歌の連呼はいらんかったかも。
摂政はあんな感じで仕事してたのかな。
ささやき女将みたいでしたね(笑)
三条天皇とは何だったのか。
ヒゲ姿カッコよかったのに活躍はちょっとだけだったね。
天皇だけ目や耳の病気になるとはおかしなことだ。
実際はやはり毒をちょっとずつ盛られてた☠?
スポンサーリンク