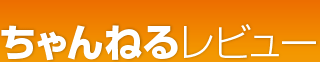3.01
3.01
| 5 | 1873件 | ||
| 4 | 341件 | ||
| 3 | 218件 | ||
| 2 | 260件 | ||
| 1 | 1884件 | ||
| 合計 | 4576件 |
私もせっかく好きになった沢村一樹さんを失踪させないで欲しいと思っている。出稼ぎで家族が離れて暮らしてるところに失踪させたら、奥さん子どもが悲し過ぎる。そこで常子がんばるみたいな、みね子のがんばりが始まるのだろうが、みね子がもっと自然な形で生きて欲しいと思ったりする。
まずは一週間。定番の朝ドラで目新しさは何もないけど
そこが良いのよ。ほっこりします。
ドラマの中の何気ない日常がきちんと描かれている。
そこだけで充分に合格点。
登場人物それぞれの心情がきちんと伝わるセリフの数々。
ここ最近の朝ドラにはイライラさせられっぱなしだったので
落ち着いてみれてたいへんよろしい。
目先の視聴率に左右されず、しっかり良いものを作ってくれたら
視聴習慣やめた人たちも戻ってくるかも。
失踪か。つばさと同じじゃん。
まれとも同じ。定番なんだね。
まぁ駄作ばっかり朝ドラって。
今回は好きだわ~。最高です。わりと明日ないのが数年ぶりに寂しいです(笑)
ドラマの舞台と同じくらい田舎で生まれ育ちました。
1964年、私の実家も貧しい農家でしたが、叔父は高校に進学しました。
その下に叔母が、さらに私達姉妹もいたけれど高校に通っていたのですから、土地によって事情は異なるでしょうが、もう高校進学はかなり普通になっていたと思います。
田舎では大学進学が珍しい時代でした。叔父も大学進学をあきらめて東京のけっこう大きな企業に就職しましたが、大卒の人ばかりの研究室に配属され、学歴の差が辛かったと話していましたから、大卒もそれなりにいた時代だったのでしょう。
普通高校が一般的になってきた時代で、農業高校はもう少なくなっていたように記憶しています。
あの頃叔父も楽しそうに高校に通い、部活もしていました。友人達もよく遊びに来ていました。もちろん、叔父も叔母も、私達姉妹も、日々の家事や、農繁期の農作業は手伝っていました。
水道がまだなくて、毎日井戸から水を汲んでお風呂まで運ぶのが私達姉妹の仕事でした。炊事用の水も汲んで水瓶に入れてたこと、懐かしいです。戻りたくはないですけど(笑)。
ガスもまだでしたから、ホントに今考えると不便な生活でしたが、当時はそんなものだと思ってそれが苦痛だったことはなかったですね。
うちも借金はありましたよ。毎年お米がとれたらその借金を返し、半年もすればまた借金みたいな生活だったと、大人になって両親から聞きました。そんな自転車操業でしたから、不作の年があったら父も出稼ぎにいき、叔父も高校進学はできなかったかもしれません。
そんなことを思い出しつつ、毎日楽しく見ています。
べっぴんさんでオリンピックの映像をいっぱい流されたためか、申し訳ないんだけど、オリンピックはもうお腹いっぱいって感じです。
前作とは違う背景でドラマが進んで欲しいなと思います。
べっぴんさんはオリンピックを飛ばして万博映像を流しました。
登場人物の性格と境遇を丁寧にエピソード積み重ねて紹介した1週目だった。
今週出てきた誰がどんな奴か、今場面とともにパッと思い出せる。
そして一人一人を好きだと思えている。
まあテレビドラマだったら当たり前のことだが、37時間の尺を使いきってついにこれができなかった例を最近見たので、その当たり前をすごくありがたいことだと思う。
人物紹介に徹するあまり事件はまだ何も起きていない。
でも主人公一家の貧しくも幸福そうな描写を見ていたらこのまま何も起きないでくれと祈ってしまう。
俺はとりあえず主人公たちにどっぷり感情移入できているぞと脚本家に伝えてやりたい。祝儀の五星球。
これから登場するであろう朝ドラ恒例の
イケメン枠の若手俳優さんが
霞んでしまいそうな程
お父ちゃんの沢村一樹さんがカッコ良すぎです!
私の出身地も半田舎でしたけど、昭和30年代の時点では、すでに高校は全日制普通科・定時制はもちろん、農業高校、工業高校、商業高校も存在していて、それぞれが、現在に至るまで、しっかりと地域に根付いております。もっとも、今は少子化の影響で、どこも全体的に生徒数が減少しているという事実は否めませんが。
昭和39年という年は、まさに高度成長期の真っ只中で、最初の東京オリンピックをはじめ、東海道新幹線開業、首都高速道路開通、高層ビル建設、マイカー、テレビの普及など、様々な話題を振りまき、すでに完成していた東京タワーと合わせて、戦後からわずか20年足らずで、所謂「焼け野原」を、ここまで復興させたんだという日本人の技術力と自信に満ちた姿が、大いにクローズアップされた年でしたね。
また、この頃は、中卒で都会に「集団就職」する人々の事は「金の卵」(歌手の森進一さんもそうだったらしいです。)と呼ばれ、家族からの期待(仕送り等)を一身に背負っていました。故・井沢八郎さんの大ヒット曲「あゝ上野駅」も、その人々の応援ソングとして、多くの人々を勇気づけ、心の支えとなった事でありましょう。私も大好きです。
そんな訳で、脚本家の岡田さんの中では、時代が時代なだけに、その「金の卵」をクローズアップさせたいという気持ちはよくわかるのですが、もしかしたら、あの当時でも、中卒も高卒も同じだと考えていたのかもしれませんね。猫も杓子も高校や大学に行ってしまう現代ならまだわかるのですが。
この1週間でみね子とその家族が大好きになりました。
なのでこの先何が起こっても、この家族を応援出来そうです。
皆で協力しながらの稲刈り、とても良かったです。
毎日3回は必ず見ています。見ないと淋しくてたまりません。
何だかこの朝ドラが一番好きになってしまいそうです。
私が今まで一番お気に入りだった朝ドラさん、ごめんなさい!
始まって一週間 時代考証的な感想を目にしました。
私の主人は昭和43年生まれの専業農家の家庭の長男です。小学生時代でも、五右衛門風呂、井戸水、かまどでご飯炊く、納豆は手作り、家畜は牛と鶏だったそうです。
主人の叔父叔母は、みね子世代で、「ひよっこ」のようなことが現実にあったこと…懐かしく微笑ましく、何度も聞かされました。貧乏だったけど、親が高校に行かせてくれたんだ。と…感謝して、でも、その後は親のいいなりにお見合いで結婚して、でもずっと親に感謝してる。そんな「みね子世代」のリアルを知っています。
だからこそ…この一週間は平凡でいいと思うし、きっとこの後、何かあるのでしょう。…が…この時代、この地域の普通のことが なんとなくよかったなぁって感じられただけでも良くないでしょうか。
父親の失踪の理由は、実入りの良い仕事を紹介されて漁船に乗って拿捕された的なものなら良いが、女絡みだと唐突感。
父親の失踪は朝ドラ定番みたいなもので、おしんの夫も失踪、ふたりっ子の父親も駆け落ち、花子とアンでも行方不明になっていた。
思えば、昔の朝ドラは、妾の子とか、父親の不倫騒動とか、親の離婚とかかなり寛大に自由奔放にやっていて面白かった。
この時代の高卒が、金の卵として劣悪なブラック企業で働くのは時代考証がおかしいが、「波乱万丈」と公式に書いてあったので、これからブラック企業に行きドラマは展開していくのだろう。
いまは良くも悪くもなく普通だが、これからの展開を見守る。
オリンピックの頃の時代がわかるのはこれからでしょう。今日のひよっこの番宣には、当時の上野駅の再現や撮影風景が紹介されていました。スタッフ総出の稲刈りで1日で撮影を終えた裏話などもありました。
いつも思うのですが、中卒者がなぜ金の卵なのでしょう?経済成長期で人手不足の時に安く使われただけではないのかと思うのです。出稼ぎ労働者だって日雇いのようなものだったのかもしれません。あの時代を陰で支えたというのは聞こえがよいですが、地方では農業の衰退と貧困があり、都会への人口流出が止まらなかったと思います。
ドラマのこれからは、どんな流れで何を描くのか楽しみです。
第1週、面白かったー
こういう見てて照れるぐらいの優しいドラマっていいなぁ
あと、感想でもなんでもないんだけど…テレビから“みね子”って聞こえると、まずは能町みね子が浮かんでちょっと笑ってしまう…(^^;)
今週はまだ何も起きていない。
だけど薄いとか間延びしてるとかでなく1個1個の事象はテンポよく描写され説明されてた。
脚本家がちゃんとセリフで尺を埋めてるんだな。
(台詞の密度が高ければ良いというものでもない。『シン・ゴジラ』をホームドラマでやられたらドン引きすると思う)
金の卵の意味は、企業側から見て、です。
世間知らずなので、低賃金で雇いやすく使いやすく仕込みやすいからです。
職場も見ずに、学校と職場で勝手に決まっていたそうで、いまの外国人労働者と似た雇われ方だと思います。
当時、市内に金の卵を雇っていた工場は二社ありましたが、ああ野麦峠の製紙工場がマシになった程度です。
いまなら完全に労働法に触れますし、世間知らずの女工を引っかけて遊ぶ男の人の車が工場の周りによく停まっていました。
>中卒者がなぜ金の卵なのでしょう?経済成長期で人手不足の時に安く使われただけではないのかと思うのです。出稼ぎ労働者だって日雇いのようなものだったのかもしれません。
その通りですよ。多くのマスコミは金の卵について、なぜか「美談扱い」にしかしませんし、亡くなった私の父も、当時、オリンピックだなんだと騒がれていたけど、実際のところ、盛り上がっていたのは中央(東京)だけで、こちら(地方)には何の影響・恩恵もなく、日々の生活に追われ、働く事で精一杯で、それどころではなかったと、よく語っていたのを覚えています。
まぁ、そんなものですけど「ひよっこ」はあくまでもドラマなので、その辺は割り切って考えてもいいのではないでしょうかね。
ひよっこと昭和を語ろうになってしまいましたね。
やっぱ持ってるヒロインは違うな。前回は悲壮感漂ってたけど、久々に安心して見れる内容ってかスタンダード。最高
まだ一週間だけど、谷田部家とその周りを取り巻く人々との何気ない日常のやりとりが観ていてとても心温まる。ほっこりする。前作では一度も感じられなかった感覚。ん?と思えるようなところも多分無かった。もしあったとしても、それが気にならないくらい素直に楽しめてるんだと思う。しょっぱなからのオープニング曲&映像にはやられた(わたし的にどツボ)。昭和30年代日常使われてた生活道具で当時の街並みを表現している世界観がとっても可愛くて素敵過ぎ。特に、そろばんの団地がお気に入り。来週も楽しみ!
出稼ぎのお父さんが帰省して家族総出、ご近所さんまで集まっての稲刈り。事件もなく平凡な農家の一年の集大成のイベントが実際の季節にリアルに再現されて惹き込まれました。
機械もなくすべて手作業の重労働だけど、みんなの農業への愛情があふれとても生き生きしている。現実はもっと過酷なんだろうけれど、このドラマの伝えんとすることは十分伝わるからいいんじゃないのかな。岡田さんはもともとちょっとファンタジックなドラマも多いから、あり得ないような描写はないドラマとして最低限のリアリティを保ちつつ、心温まる描写で私は好きでした。
そしてそんな家族幸せいっぱい充実の笑顔の中で、ヒロインのみね子は寂しさも感じてる。
これが終われば明日にもお父さんは東京に戻ってしまう。友人の時子や三男も卒業後は東京に行ってしまう。
今後の展開を暗示するようなヒロインの心の光と影が巧く演出されていたと思います。
この一週間は、貧しい農村の平凡な日常が丁寧に描かれ、そこで暮らす家族や友人たちの心温まる絆が素直に伝わるほっこりした内容でした。私の求める朝ドラ像とはぴったり一致して満足のゆくものでした。やはり朝から心がざわつくような不快な話はあまり見たくない。
でも来週からはお父さんの失踪?で、物語が大きく動きそうですね。
のんびり平穏な人生が一変するだろうみね子の頑張る姿を応援していきたいです。
1週間見ました。
沢村一樹さん演じるお父さんがとても良い雰囲気ですね。
何よりも見ている自分が自然と笑顔になっているのが分かるので、これは期待できる朝ドラです。
とりあえず1週目はね
前作の反動があるかもしれないけど
当時の出稼ぎ事情だったり、電話のつなぎ方だったり、ただの日常の中になるほどなって思うとこもあって面白い
土曜日の放送回(第7回)は稲刈りオンリーだった。
なのにとても引き込まれた。
日本の原風景の美しさと、家族や地域の人々との触れ合いがとても暖かかった。マッシュルームカットの叔父さんだけはウザいけど(笑)
いや〜「べっぴんさん」の、あの拙くも酷いエビやシーンの数々は一体なんだったの?半年間の悪夢だったのか?
外から見ると美しい原風景だよね。
でも毎年稲刈りしている農家は、その風景が当たり前過ぎて、まして奥茨城以外を知らないのに「日本の原風景だな」なんて絶対言わない。
こんなセリフを言うマッシュルームの叔父さん、なんか違和感ある。この叔父さんだけが目障りで残念。
古谷一行を父に、沢村一輝を兄に持つのに、なぜあのムッシュかまやつ風の弟なんでしょうか。
金の卵と銘打っただけなのでしょうね。聞こえだけはいいですから。安い賃金と日雇い同だとしても、地方の小作農では家族を養えない。日本が高度成長期などといっても、離農して都会に出るしかない、そんな家庭もたくさんあったはずです。押せ押せムードの時は陰の歴史の部分は見せないもの。表に見えるいい面しか見せません。東京に家族全員で出てそこで生きるか、働き手として、まだ若く働ける者が出稼ぎに出るしかない。でも当時の労働者は、今の労働者より確実に頑張ったと思いますよ。ゴネて、ゴネ得みたいな、自分の子供を国で面倒みてほしいなどと、なんでもかんでも国や他人に頼ろうとする、甘えた人間は少なかったと思いますしね。
15分という限られた時間の中でどれだけ視聴者を惹きつけて ”明日も観たい” と思えるドラマにするのかが脚本家の腕の見せ所だと思うが、次の日を心待ちにすることはほとんど無かった。
無駄な時間の流れが毎日のようにあってイライラした。
ドラマチックやドロドロな展開を朝ドラには求めてない
ただただ明るく今日も1日が始まったー‼︎っと思えるひよっこは好きです
新日本紀行や小さな旅を観たようなドラマ。冨田勲や大野雄二の
音楽が聞こえそうだ。稲刈りのお昼休みの時間に畑の脇で腰を
下ろしておにぎりを食べているときにトランジスター携帯ラジオ
からお昼のNHKラジオ番組、昼の憩い、で、昭和歌謡が流れる
演出だったらもっと良かったのに。
周りの騒がしい意見は気にしないでそれなりにドラマを楽しんで観ています。
ここ一週間、お父さんの建築現場、すずふり亭、奥茨城の日常、人物描写を丁寧に描いてました。大きな動きは無かったけれど、助走としていいスタートを切ったと思います。月曜日からいろいろありそうですよね。楽しみです。
好きか嫌いかなら好きな方だけど
面白いいかと言われてもまだ評価のしようがない。
懐古主義者さんの感想は他のサイトでも読みました。ご本人ならいいのですが・・・
いいわぁ~
役者さんや脚本の素晴らしさが多少の粗を補って余りあるので
何もかもが心に響いてきます。
こんなドラマなかなか無いんじゃないでしょうか。
ドラマで感動し、多くの皆さんの感想に感激しています。
元気を貰い、明日が楽しみに思える朝ドラひよっこに感謝です。
ここのサイト盛り上がっていますね。
市川猿之助曰く、賛否両論こそ本物。
名作になりそうだ。
去年BSで再放送された、てるてる家族とほぼ同じ時代。
昭和39年は店にテレビを入れて客が増えたり
石原さとみが宝塚目指してレッスンに励んでいた頃ですね。
ひよっこは5年前の不作とテレビがちょっと釣り合わないんですよね。
不作は3年前ぐらいにしておけば良かったのに。
理想の家族&周囲の人たち。
おとぎ話のよう。
貧しくてもお互いを思いやる暖かい家族、いつでも助け合いの精神で協力しあう地域社会、おとぎばなしに出てくるような山里の農家、黄金色に輝く稲穂の波、親切で心のこもった洋食屋さん、あのころの日本は美しかった・・・ノスタルジーを感じるでしょう?と言われているみたいでちょっと気持ち悪いです。今後の展開にそなえていかに父親が家族にとって大切な存在なのかということをこれでもかというほど描いていた一週間でした。あの変わったおじさんをはじめ登場人物がいい人すぎてリアリティに欠けるしあんまりドラマという感じがしない。話の展開も遅すぎて早く次を見たいという気にもならない。こういう朝ドラがいいという人も多いと思うけれど私の見たい朝ドラはおしんやごちそうさんのように展開が早く次の日に何がおこるのかわくわくするような、そしてきれいごとでないこともきちんと書いてくれる朝ドラです。もうしばらく見てみますが、べっぴんさんとはまた違った意味で脱落しそうな気もします。
今期は、なかなか味わい深い朝ドラだと。
田舎という限られた人物模様とシンプルなストーリーでありながら、
今週はそれらによってあの時代の地方と都市との関係性、またこの家族の自然や農業への価値観などがしっかりと明示されました。
これはヒロインがこののちに都会に出て生きていくとなった時にどのように身を処していくのか?の土台となる部分なるのでしょう。
世俗からちょっとだけ距離があるといいたいのかな、、。
奥茨城の山の中に、その土地を愛し周囲と助け合いながら農業を営み生きるという人生が、同時にヒロインの成長の日々であり、家族との絆がやがてこのヒロインの未来へと結びついていく行くであろう予感をさせます。
決して山の中の寡黙な隠遁者のような物語ではなく、あくまでも生活があり未来を感じさせる明るさがあります。
他がダメというのではなく、今回はとてもみずみずしい透明さに溢れた作品だと思います。
経済、文化等何においても東京を中心とした「東京一極集中主義」で、地方を蔑ろにした考え方は、そもそも江戸時代に端を発していますからね。本当の中心部は、秀吉が興し「天下の台所」とも呼ばれた大阪なのに、実際には天皇家も江戸に住み、そして秀吉に取って変わって政権を獲得した徳川家も江戸に根を下ろして政(まつりごと)をして、もちろん、そこに多くの士族が集まってきたのは言うまでもありません。
こういった主義・思想は何百年経っても変わる事はなく、現在に至っています。
だからこそ東京に行けば稼げるという発想で、出稼ぎ=東京になってしまうのでしょう。
以上、地方人間のボヤキでした(笑)
まあ、1週目は無難にこんな平穏な農村ものかな。
東京でヒロインが働くようになってから、いろんなトラブルが起きてくるのだろう。
ちょっと昔の話だから、当時のことをしっかり覚えている人が多い、昭和30〜40年代のドラマ。ここでも当時のことを思い出して書き込みしている人、多いですよね。
そして覚えている人は多いのに当時の「物」が案外残っていない。だからドラマにするには難しい時代と聞いたことがあります。
資料館や田舎に行けばある程度残っているかもしれませんが、制作者は大変だろうなと思いながら見ています。
あの時代だったら、稲刈りの後、千歯扱きか足踏み式の脱穀機の登場ですが、出てくるのかなぁ? 出てこなくても構いませんけれど、そんなのまで出てきたら感心しちゃうかも。
地方には当時とあまり変わらない風景が残っている場所があります。でも、東京は「物」のみならず何もかもが激変していますから、セット主体になってしまうのでしょうね。
美しい田園風景はそれだけでもホッとできる映像になるでしょう。
ドラマの内容とともにそちらに期待している私です。
賛否両論ありますが、私は自然に丁寧に作り込まれた世界観にどっぷり浸かってしまいました。
癒されます!
出演者、スタッフの皆様、視聴率にめげずこれからも良質なモノを期待してます。
祖父役の古谷一行さん、いいですね。
無口だが、表情や佇まいで家族を思う心の中のセリフが聞こえます。
息子が帰って来た時も「おー帰ったか」と一言で、藁を編む作業を止めないが、
内心はホッと安心して喜んでいる感じが良く出ていました。
なんだか亡くなった父を懐かしく思い出しました。
まずは合格点というところですね。一週目のテンポとしてはちょうどよいと思います。
安心して見ていられるのは、変テコで寒いスベリギャグなどをほとんど入れていないところ。全般的に好感は持てるが、半年間、飽きず呆れさせずに続けて見ようというモチベーションが保てるかどうかは、まだ判断がつかない。もうしばらくは様子見。
それにしても最近の次週予告編は簡単にネタバレしちゃうんですね。番宣などほとんど見ていない人間もいるのに。(ここは読んでいますけどね 笑)部分的なシーンをチラ見させて、「え?お父さんいなくなっちゃうの?」と想像させるくらいなら良いと思うが、「失踪」などそのものズバリのキーワードは伏せておいてほしい。とと姉ちゃんでも次週予告とサブタイトルでのネタバレ感が甚だしかったので、あ、またか、と少し残念に思ってしまった。
他の方も仰っているようですが、沢村一樹さんのイメージが変わりました。
片田舎の働き者で家族思いの良いお父さん。しかもカッコいいのオマケつき。
このような役もできるのだなと目からウロコの1週間でした。
今週の内容自体は普通のホッコリする朝ドラが始まったなぁ、
以上でも以下でもなく普通に楽しめる程度なのですが、
なぜこのお父さんが失踪などするのか?まったく分からないところに惹かれます。
東京を嫌いにならないでね、と言っていた鈴子さん。
この当時の出稼ぎ労働は、傍から見ても大変だったのだろうと思わせる台詞でしたが、
増田明美さん曰く「変な叔父さん」は、兄さんは人から可哀相と思われるような人じゃない、そんな風に思うのは失礼だという様なことも言っていました。
まだ失踪まで話が進んでいないのに謎は深まるばかりです。笑。
まれで大泉洋さんのイメージは全く変わらなかったけど、ひよっこで沢村一樹さんのイメージは少し変わった。失踪の理由で後のイメージが更に変わるのかもしれない。
朝からイライラ&不快がないだけでも最高。
前作が想像の遥か斜め上の破綻ストーリーで朝から暗い気持ちになったり、不快指数MAX、イライラさせられたりして散々振り回されたせいか、ほのぼののほほーんとしたストーリーだと物足らなくなってしまってる
脚本が朝ドラ史上に燦然と輝く傑作「おひさま」
そして昨年は2016年を代表するドラマとなった「奇跡の人」の
岡田 惠和なので期待しまくったが大外れ。
一週間面白くないものが今後いきなり面白くなるなど有り得ない。
要因の一つが有村架純 の調子っぱずれの茨城弁。
何とかならないものか。
沢村一樹の名演で何とか観れるが
失踪したら終わりだろうこのドラマ。
スポンサーリンク