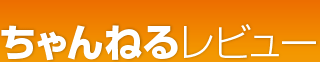井頭愛美さん、コメントありがとうございます。
おっしゃる通り源平交代説と言うのがあり、源氏と平家で交互に政権を担当すると言う考えです。でも戦国時代で見事に崩壊し、織田信長は平家を勝手に名乗るし徳川家康も源氏から系図を書き換えたと昭和の学者の本には書かれています。曲がりなりにもある程度の家柄だからごまかせたのです。
しかし、下層農民出身の豊臣秀吉はそうは行きません。そこで関白には藤原氏の他に豊臣氏もなれると言う規律を勝手に作りました。でも二代で潰れましたね(秀吉、秀次)。
徳川家康は、最初、関白になろうとしたんでしょうか?
『藤原』を名乗っていますね。
百田夏菜さん、コメントありがとうございます。
文献がないので全くの個人的意見になりますが、鎌倉幕府で源実朝暗殺後に九条頼経、頼嗣と摂関家から征夷大将軍が鎌倉幕府の名目上のトップにきているので、織田信長が平家を自称した以上、源平交代説から源氏を名乗ったのではないでしょうか。関白は京にいて天皇や公家に近侍し、室町幕府のような幕府の公家化脆弱化を嫌い、江戸城に拠点があっても差し支えない征夷大将軍は都合が良かったのではないでしょうか。
スレ主さんの方が正しかったです。
徳川家康が藤原を名乗ったのは、「三河守は源氏が拝命した前例がなく、藤原家康と一時的に名乗った」だけでした。
百田夏菜さん、コメントありがとうございます。
難しいですねえ、日本の歴史って。
これからも、いろいろ教えてやってください。よろしくお願いいたします。
明智光秀は源氏、織田信長は平氏、徳川家康は源氏を、それぞれ怪しくても、正式に名乗っているのに…
豊臣秀吉は、絶大な権力を持っても、源平のいずれも名乗れなかった…というのは…そこまで嘘はつけない…ということで、面白いですね😃
井頭愛美さん、おはようございます。コメントありがとうございます。
明智は土岐源氏ではある(光秀が濃姫と従兄かは不明)。織田は越前の神官と言う説が有力で尾張の守護代。徳川は室町幕府の政所執事・伊勢氏の被官とウィキにはある(徳川はそれ以前は下層とする学者もいる)。
一方、秀吉は下層農民で継父と険悪で家出。生まれながらの大名の信長、家康とは違う。これでは源氏だ平家だとは到底言えなかったでしょう(と学者の本にもある)。
足利義昭が将軍になる前に側近の前で「織田信長の力を借りようか?…と思う」と言った時に、明智光秀が「私は、織田信長殿の奥方の縁者です。私が話をつけてきます」との、話が残っているそうです。
なんの資料だかは覚えていません。
そこで、妹でないならば、従妹であろう?と推論したみたいですね。
芳根京子さん、おはようございます。コメントありがとうございます。
それは初耳です。通説になっていないのは決定的決め手が当該資料にないのでしょうね。司馬遼太郎の世界ではおっしゃる通りですけれど。でも、かなり有力な説ではあるんでしょうね。
貴重な情報ありがとうございました。
秀吉が御伽衆に書かせた中に
母親である大政所の父は「萩の中納言」であり、大政所が宮仕えをした後に生まれたと記述しており、天皇の落胤であることがほのめかされています。
もちろん、誰も信じていません。
百田夏菜さん、コメントありがとうございます。
似た話はありますね。
生命線が中指のてっぺんまで伸びている秀吉の手形、大政所が太陽に感応する夢を見て秀吉を生んだ、とか。
でも、秀吉は実際は小柄で大きく見せるため大きな衣服を着て、指も奇形であったとする学者もいますね。荒淫が過ぎて認知症に早くからなり亡くなったと言う指摘も司馬遼太郎は対談で触れています。一方、秀頼は体格がよく母方の祖父の浅井長政に似ていたそうですね。
スレ主さん、お返事ありがとうございます。
淀君は、今流行りの不倫していませんよね?
秀頼は、秀吉の子ですよね?
百田夏菜さん、コメントありがとうございます。
昭和の学者や司馬遼太郎は、あれだけの側室を持ちながら淀殿だけから男児が二人も出産はおかしいと指摘しています。
淀殿の乳母の大蔵卿の息子の大野治長の子ではないかとする史書もあるようですね。
スレ主さん、ありがとうございます。
大野治長にちょっとだけ味方するとすれば、容易ではなかったってことですよね。
もし、そのようなことを、誰かが告げ口したら、即打ち首です…もんね!
百田夏菜さん、コメントありがとうございます。
そうですね。当時の大阪城内には片桐且元らもいた訳ですし、いくら実力者の大蔵卿の息子でもね。こればかりは藪の中です。
目下、SNS人気1、2を争う反響の高さは…
吉田鋼太郎さんの松永久秀らしいですよ😊
出番の少なさのわりには、すごいですよね😉
家康も信長も秀吉も地位を得るために、家柄にこだわり、源氏や平氏、藤原氏につながろうとしたけど、三好、松永は地位が上がっても氏に拘らなかったようですね。
それも当時としては反感を持たれた要因なのかな。これもヒスとリアで言ってたことですけど。
現代の感覚だと、氏などは大きな問題ではないように思えます。
源氏などの名門は、秀吉も徳川も、特別な地位を与えてますよね。土岐や今川、吉良氏などもそうでした。
特に吉良氏は、徳川にとっては特別な存在だったようです。将軍職を手に入れるにあたって朝廷との交渉を吉良氏に頼らざるを得なかったとのこと。
三河で同郷であり、徳川にとってはずっと目上の存在。将軍が代替わりするごとに、吉良氏に頼まないといけないので高家筆頭の特別待遇を与えざるを得ず、徳川にとってはずっと特別な煩わしい存在だったのではないかとのことです。
浅野氏との事件で、赤穂浪士が仇討ちしやすいように、幕府が吉良氏に意地悪したのは、そういう徳川氏の吉良氏に対する感情があったからなのかも。
天下をとったからといっても、なんでも自分で自由にできる、というわけではないのですね。伝統を破ると上手くいかないということでしょうか。
べえべえさん、やはり氏は大切じゃないでしょうか?
豊臣秀吉でも征夷代将軍になれませんでした。
足利義昭が、毛利領内の鞆の浦で「われこそは将軍である」って頑張っていたからです。秀吉は、養子になるから義昭に位を譲るように交渉したけど断られました。こういうとき、朝廷というのは「義昭の位を剥奪する」みたいな乱暴なことは、やりたがらないものです。
秀吉も先祖が源平藤橘いずれにも繋がるように工作できなかったのが、最大の悩みだったような気がします。
芳根京子さん、べえべえさん、コメントありがとうございます。
「国盗り物語」ではエキストラ扱いだった松永弾正。本格的に描くのを見るのは私個人は初めてなので、吉田鋼太郎さんの渋い魅力に期待しています。シリアスからコメディまでこなし舞台劇で鍛え上げた声量の大きさ。楽しみです。
昭和46年に民放ながら大河並みのキャストと金で制作された三船敏郎主演「大忠臣蔵」。
この作品では幕府は当初、柳沢吉保(神山繁)は吉良家を守ろうとしますが途中から吉良と浅野を喧嘩両成敗にして吉良上野介の長男の上杉綱憲の米沢15万石を取り潰そうと作戦変更。吉良家家老の千坂兵部(丹波哲郎)が清水一学(天知茂)、堀部安兵衛(渡哲也)とやり口が汚いと憤る場面があります。創作かは知りませんが。ですから吉良家の武士も腕の良い人間は清水一学ら若干名にとどめ屋敷も警備の緩いさびれた場所に移す描写があり、屋敷の描写では「元禄繚乱」でも吉良上野介(石坂浩二)が心外だと抗議する場面があったような。ウィキで確認しましたが屋敷の移転は史実のようですね。理由は不明ですが。べえべえさんがおっしゃるように意地悪をしたのですね。
百田夏菜さん、コメントありがとうございます。
家柄ですね。現在でも皇室の婚姻関係の話になると出てきますね。氏より育ちだと思いますが、私が少年時代は民主主義の時代にまだ参議院議員に肥前藩主の鍋島家当主、彦根市長に彦根藩主の井伊家当主がいましたから昔は源平藤橘へのこだわりはあったでしょうね。落選しましたが沖縄県知事選の保守系統一候補も琉球国王の末裔の方でした。
芳根さん
松永久秀は、どこかで豹変しそうで怖いもの見たさですかね。今のところお茶目で人のいい、面白い人になってます。私も期待してます。
百田さん、スレ主さん
秀頼は、やっぱり秀吉の子ではないとする研究者の本、私も読みました。それによると、出産から逆算して、妊娠時期は、秀吉は朝鮮出兵のため九州にいて、淀殿は大阪だったのであり得ないと。
また、秀吉がねねからの手紙で妊娠を知ったのは、妊娠7か月になってから。返書でも茶々の子でよいとだけで、秀吉はあまり喜んでいる様子がなかったということらしいです。
結局、無理やり逆算した予定日から2カ月遅れで出産したらしいです。嫡子にしたので多くの豊臣大名が反感を持ち、滅亡の原因になったとしています。服部英雄氏によります。
それにしても、なんで自分の子ではないのに、跡継ぎにしたのでしょう。織田の血筋だから、というのもあるかもしれないけど、それがなぞです。一番聡明だと思った、ということが大きいのではないかと思います。いや、そういうことが判断できる年齢だったのかな?
べえべえさん、コメントありがとうございます。
いろいろ情報を提供下さり嬉しく思います。初めて知ることも多いです。
一点だけ言えば、豊臣系大名は秀頼に反感は持ってませんよ。加藤清正は家康の子供が秀頼の前で傘をさしたままなのを「無礼者」と怒鳴りつけ叱ってますし、福島正則も大阪の蔵屋敷の米を豊臣側が奪うのを黙認していました。
昭和の学者の本や司馬遼太郎によると秀吉は秀頼の機嫌を損じたとして逆上して侍女を処刑しようとしたり、秀次一族を男だけでなく妻妾や娘(幼女)に至るまで虐殺し認知症のような症状が出て、とにかく自分の跡取りだと盲信してたのではないでしょうか。「黄金の日々」は人格が一部崩壊したそういう描き方でした。「真田丸」が愛すべきボケたお爺ちゃんにしたのは今の時代なら認知症の人間への差別偏見を助長するものと糾弾されるのを恐れたのではないかと言う気もします。
日本の歴史って、天皇家と『源平藤橘』が、大化の改新~明治まで政権を担ってきたんですよね。
源平橘は元は天皇家だから、究極、天皇家と藤原家になりますよね。
唯一の例外が豊臣秀吉ですよね😃
さすが百🍑ちゃん
「足利義昭が、毛利領内の鞆の浦」出ましたね。秀吉に対して正統性主張して対抗してるのですね。
自分の仮説では、地理的にも、ここで水軍情報をもとに足利義昭が、織田信長の明征伐の野心を警戒し、光秀を反織田に祭り上げたのでは?と今のところ推測してます。義昭と光秀の関係については、まだ調べてもいませんが。
井頭愛美さん、おはようございます。コメントありがとうございます。
自称と言うことではそういうことですね。ざっと思い浮かべても、三日天下と言われた明智光秀や古いところでは木曽義仲も源氏ですからね。秀吉だけということになります。
43さん、戦国時代の火薬の入手経路これじゃダメなのかな?
日本の火薬は長らく黒色火薬のみでした。これは木炭と硫黄、硝酸カリウム(硝石)の混合物ですが、日本では硝酸カリウムが採れないのです。
ただし、大貿易港だった堺は硝石の輸入が可能でした。つまり、火薬は堺でしか作れず、これが戦国時代の堺の自治を支えました。
その後、硝石を「国産化」する技術が広がります。原料は意外なところにありました。トイレです。バクテリアがアンモニアを分解すると、硝酸ができることを利用するのです。
芳根京子さん、コメントありがとうございます。
43さんのご回答を楽しみにしてるところなんです。私は理系は不得手なので皆さんのやり取りで勉強させて頂きたいと思っています。
何のドラマだったか覚えていないのですが、時代劇で、家の床下に、古い土に草や蚕の糞などを混ぜて重ねた物に、時々人尿をかけ、鋤で混ぜ合わせると何年が経つと発酵して硝石が取れる、という説明がされていたのを見た事が有ります。それを藩が買い上げてくれるのだそうです。
それを見た時は「え〜汚ーい、ウソ〜」と思って嫌になりましたが、国産の火薬材料ってそんな風に作られてたって大真面目にホントだったんですね。
トクヨさん、コメントありがとうございます。
私も初めて知りました。ここの皆さんのコメントを聞きたいですね。私には全く分からない世界ですので。
百田さん
そう言われれば、足利義昭は豊臣政権時もまだ将軍のままでしたね。なるほど、秀吉は源平藤橘に繋がれなかったから、新たに豊臣という姓ををもらうしかなかったのでしょうね。
井頭さんが言われるようにように、結局、天皇家と藤原氏でやって来たということですね。
スレ主さん
私も元禄繚乱の石坂浩二さんの吉良上野介は覚えてます。屋敷の移転などの仕打ちに対して、「高家筆頭の当家にこのような扱いとは、理不尽な、、」 などと言ってたような。
前の投稿で、高家筆頭と書いたのですが、正式にそういう格式はなかったようですね。すみません。
私の情報、出所が怪しいのがあるかもしれません。ちなみに吉良氏と徳川氏の関係については、元建設省の河川事業などの専門の人が、地形から歴史を見た見解をのべたものからです。 吉良氏と徳川氏(松平氏)は、三河の矢作川流域でライバル関係にあったらしいです。
豊臣系大名が、秀頼に反感を持っていたというのは、服部英雄氏はそう書いているのですが、確かに今までそんな認識は私もありませんでした。秀頼への不満ではなく、朝鮮出兵の処理で、三成などへの不満が大きかったようなイメージがあります。秀吉は認知症で、秀頼を本当の息子だと茶々から思い込まされたのでしょうかね。
ありがとうございました。
トクヨさん、そうなんです。戦国時代末期、日本は世界№1の鉄砲保有国になります。そこで、大量の火薬が必要となりました。
トイレのバクテリアがアンモニアを分解する理論で…
古い家屋の床下にある土から硝酸カリウムを抽出する古土法が発見され、各地で行われました。 富山県五箇山では「培養法」という、サクと呼ばれる草や石灰屑、蚕の糞を床下の穴に埋め込んで、数年で硝石を得る技術が開発され、硝石を潤沢に生産するようになった。
と言われています。
私は理系ですが、化学は知識がないので火薬や硝石については全く知りませんでした。
芳根さんや、百田さんの作り方も、トクヨさんのドラマの内容も知りませんでした。
日本が鉄砲保有世界一ですか、短期間でものにするのは、この頃から得意だったのですね。
勉強になります。
京子さん
百🍑ちゃん
基本的にそれでいいけど、天下人(信長・光秀・秀吉・家康)や日本を統治してると考えてる朝廷や幕府にとってのそのことの意味(今後どうするか)が、信長・光秀の本能寺の変に繋がる時代の最重要事項でしょ、ということです。
鉄砲は国産化できるが、火薬は平和時の国内需要は賄う方法があるが、硝石の鉱山がない日本では対外進出するためには、継続的にポルトガルや英国等のヨーロッパ産の火薬を大量に輸入し続けることが必要で、一度そうなれは(明へ進出すれば)その状態は永続化して元に戻せない。石見銀山の銀をポルトガルが狙い、当初それを賄えたとしても埋蔵量は不明、いつまで銀の産出を続けられるかによっては、極めて高いリスクにさらされる。更にヨーロッパの鉄造船と火器(大砲)の技術には大きく溝を明けられてるから、対外拡張路線を取れば、鉄砲を国産化しても、火薬の調達費用が継続的に流出し、銀山の枯渇リスクとその後の、欧州の海軍に日本が制圧される(日本が征服される)リスクをどう評価するかで国内の意見はは、二分されるはず。
自分が天才だと思い、世界制覇できると思っている信長・秀吉の海外進出拡張路線とそれはリスクが大き過ぎて誇大妄想だと考える反拡張派(海外進出リスクは高すぎる)に分かれると理論的には考えられる。
その国内対立を背景に、本能寺の変・秀吉の巻き返し・朝鮮出兵・関ヶ原・鎖国政策等の流れがあるの🦆。
834 は 43さんですねよ。
深い、というか着眼点がすごい。そういう流れですか。
では、明治の拡大路線は、また、信長・秀吉への回帰ということになりますね?
秀吉も明治政府も、その路線は結局は破綻しました。
資源をどう確保するかは、日本の長年の苦悩ですね。
べえべえさん
フォローありがとうございます。名前入れるの忘れてました。
信長を、煽てて(駄洒落かな)、石見銀山を入手させ、対外進出させれば儲かる人達(他国の人)がいただろう。それを非常に危惧してる日本人もいただろう。背景はそうだった🦆ということです。
43さん
なるほど、それがポルトガルなどの植民政策の一環?
大量に硝石を購入させ、銀を流出させて手に入れ、いずれは、、
しかし、オダてられた信長も秀吉も、それは念頭になかったのですかね。それも認識の上で、大陸で資源を手に入れたらポルトガルなどにも対抗できるというもくろみですかね。
では、家康など、拡張路線の反対派はどうやって国を守ろうという考えだったのか、疑問が出て来ますね。
あ、徳川幕府が鎖国したのは、ポルトガルに対抗するオランダの戦略に乗ったのかもしれないですね。オランダと友好的な関係を保っていればなんとかなるという考えだったのでしょうか。
しかし、その後の幕府は、海外情勢を見極め、対応を変化させていくことができてませんね。
お得意の内ばかり見て変化を嫌う官僚化、硬直化が出て、その結果の明治維新ですね?
しかし今も日本は独自に石油とか、リチウムとか、死活問題の資源を解決できていません。それどころか防衛さえ他国頼み、完全な独立国とは言えないですね。
日露戦争以降の極端な拡大路線は、根本には当時の幅広い日本国民の意識として、大陸なしには日本は立ちいかない、という共通の認識があったからだ、と分析されているものがありましたが、今はそれも成り立たない。
物を仕入れて加工し、付加価値をつけて輸出するというのが得意だったのですが、もの作りも今は強みを失いつつあります。これから何を強みにすればいいのか、議論は色々ありますが。。。
話が飛びますが、一般的日本人の第二次大戦への思いは、被害者意識が強いような印象を受けます。戦争を主導した軍部や政府が海外にも我々日本人にも多大な被害を与えた。悪いのは軍部や政府の上層部だと。
しかし、そうではなく当時の日本国民全体の意識のなかで拡大路線が行われたのであり、日本人全体がアジアやその他の国々に対する加害者だという意識をまず持たないと、これからもそれらの国々との付き合いは上手く行かない気がします。
それはともかく、結果的に戦争に負けて、海外の全ての権益を失いましたが、それなしでも戦後復興を遂げ、経済的には一度は一流国となりました。
戦前の常識とされた大陸権益なしに日本は成り立たない、という認識は偏った考えだったことがわかりました。
今も同じことが起こり得ます。
政府は親アメリカの政策しか行いません。日米安保ありき、が戦後の常識。しかし、今後中国やアジアへのシフトが大きく進む中で対応に遅れ、20年後に、もっと早く親米路線を見直すべきだった、と後悔し、今の政権だけを責めるようなことがないことを祈ります。私も他人事ではないのですが。
書いているうちに話が飛び、まとまりなくなってしまいましたがこのまま投稿します。読みづらくてすみません。
べえべえさん
みなさん
当時の日本での海外情報・国際情勢情報は、
①足利将軍家の対明貿易ルート
②ローマ法王庁or/andイエズス会or/andポルトガル国家を背景にする宣教師
③ポルトガル商人
④水軍系にあるかもしれない東アジア海賊ネットワーク
他にあり得るでしょうか?朝廷ルート?真言宗ルート?その他?
信長・秀吉には、主に②③(煽て系)から情報が入る。堺商人ルートはある🦆お庭番ルートも
将軍家には織田等から②③の情報①からそれ以外のルートの情報が入り、毛利領内の鞆の浦に幕府が移りさらに④の情報も幕府に入っていたかもしれない。
そうすると、最も総合的な情報を持ってるのは、鞆の浦の足利義昭❔
光秀は、織田系の情報と義昭系の両方の情報に接してた🦆
海外進出後の見通しを判断できる立場にいたのは
①信長
②義昭
③光秀
④秀吉
⑤その他(毛利・大伴❔)
多分落ちが沢山あるだろうけど、本能寺の変前の日本の情報判断拠点は以上では❔
そうすると、信長・秀吉か煽て系情報に釣られるのを自分で抑えることも難しく、根拠を持って説得できる人間も義昭か光秀に限定されるのでは?
べえべえさん
欧州側から見れば、英国とオランダが信長や日本をどうとらえ、どう接触してたかしていなかったかというのは重要だと思います。
日本人の国際情勢やその歴史の見方が相当歪んでるのは、今までの歴史の教え方と、それを習って大河ドラマ視聴者になってる旧来の大河ファン・それをそのままにしてた大河ドラマ供給者(NHK)にも原因はあると思います。
その点でも、「いだてん」的な志は重要だと思った。
839さん、
そうすると、本能寺の変もそれ前後の動きも、ものすごくダイナミックですね。
大河でも、義昭や秀吉、毛利などと動きや海外勢力とのかかわりをできるだけ入れて欲しい気が強くなりました。
ありがとうございます。
43さん
なるほどです。
今までの歴史視点は見直さないといけないですね。
世界から見た当時の日本の視点を、ぜひ入れてもらいたいてす。 びっくりするような大河もいいですね。
839も43でした
べえべえさん
自分も
>大河でも、義昭や秀吉、毛利などと動きや海外勢力とのかかわりをできるだけ入れて欲しい気が強くなりました。
重要だと思います。そういう大河になって欲しい。
べえべえさん、百田夏菜さん、43さん、コメントありがとうございます。
高家筆頭と言う正式の役職はなかったのですか。昭和の学者の本でも当たり前のように筆頭老中とか言いますけれど。ウィキによると高家肝煎と言うのが正式のようですね。
「春の坂道」では明の遺臣の鄭成功の求めで明国支援に出兵し清朝に対抗しようと言う紀州藩の徳川頼宣か将軍の家光かに萬屋錦之助の柳生宗矩が喉元に刃を向け「明国出兵はお止めなされませ」と凄んで思いとどまらせる描写がありましたね。
化学の鉄砲・火薬の知識はお任せします。全然、分からないから。
米国との付き合いは各人ご意見があると思いますが、ベトナム戦争に30万人も陸軍部隊を派遣し(米軍は最大で50万人)、現地で略奪暴行行為があったとされる韓国軍のようなことがなかったのは幸いだったと思います。1968年大統領選挙では共和党ニクソン、民主党ハンフリーに対し、独立党の極右のジョージ・ウォーレスアラバマ州知事がベトナム戦争での原爆使用を主張し深南部の5つの州で選挙人を獲得し副大統領候補が日本大空襲指揮官のカーチス・ルメイだったこともアメリカに一つの側面です(反戦主張のロバート・ケネディは民主党予備選終盤6月にカリフォルニアで勝利直後に暗殺)。
あまりにもスケール大きな御二人の会話に驚きです。
後日、意見があったら、書かせてもらいます。何日か調べて、検証してみないと、滅多なことを書けない内容だと思います。
べえべえさん、戦国時代のトップの考えが昭和史まで繋がるとは…着目点が素晴らしいですね。
43さん、あまりにもスケールのデカい話なので、少し調べてみます。
ルート⑤の大伴は大友でしょうか?
あと…ルートとしては、独自に海外貿易していた琉球ルートがあるんですが、これは当時日本じゃないし、影響は少ないですかね?
832の百ちゃん
戦国時代、鉄砲保有数が世界最高となった日本はヨーロッパの国々を凌ぐ軍事大国だったらしいですね。
いち早く国産化を成し遂げた日本の鉄砲の保有数はヨーロッパの個々の国全部を合わせたが数より多く、その上、戦慣れした兵の数も豊富で、来日していたヨーロッパの宣教師たちも、日本が東南アジアなどに攻め込んだら、自分たちに勝ち目はないと恐れていた、という話も聞いた事があります。
トクヨさん、そうなんですよ。
だから、秀吉軍が朝鮮へ攻め込んだ時、最初勝つのは、当たり前なんですよね!
みなさん、ありがとうございます。
秀吉より少し後に、辺境の地の少数民族、女真人のヌルハチは、短期間で明を征服することに成功して、清を建てました。秀吉に似ています。
秀吉も配下の武将も、決して当時の軍事力や国力からみて、朝鮮と明の征服を絵空事と思ってやっていた訳ではない、十分実現性のあるものと思ったやっていたと思います。しかし秀吉も高齢で指揮できないし、後がない。朝鮮や明を知らないのがなんといっても失敗の原因だったのでは。
こちらでもこんにちは
遅ればせながら、新キャストの方を改めて拝見しました。
ユースケさんは写真から怪しさを醸し出していますが、怪しいユースケさんも好きなので楽しみです。
あと安藤忠信さんは、最初見た時に驚きました。
いつも長い髪が印象的でしたし、和装も初めて見た記憶なので。
でも和装も似合いますね、新鮮な感じがして気になっています。
間宮さん・本郷さんの活躍、まだビジュアルは公開されていない?真野響子さんやベンガルさんもどのように描かれるのか…越前編の衣装も好きだな。
今日の放送も含めて、今から楽しみです。
では、また皆さんお元気にお過ごし下さい。
43さん、べえべえさん、百田夏菜さん、846さん、コメントありがとうございます。
世界文化社「日本の歴史」シリーズだと文禄慶長の役の日本側の鉄砲の銃身は写真で見る限り長くて李朝や明朝の者より射程距離が長く優れていたようですね。
ただ、朝鮮民衆のゲリラ戦に後半は苦戦し李舜臣の水軍は撃破しても人足の逃亡等が続出し苦労したようです。
846さんの欧州の国々を凌ぐ軍事大国だったと言うのには兵力面では同意できますが、一点疑問があり大砲の技術はどうですか。既に東ローマ帝国のコンスタンチノープル要塞砲撃にオスマントルコ軍が大砲を使っていたのに対し、日本は江戸幕府が島原の乱の鎮圧にオランダ海軍に頼み大砲で砲撃してもらい大坂冬の陣の講和を迫る徳川方の大砲に豊臣方は恐慌をきたしたそうです。あまり普及していなかったのでは?
ただ、オランダ側も明朝の遺臣に台湾のゼーランディア城を奪われるし日本の末次平蔵には台湾事件で辛酸を舐めさせられるし盤石の強さではなかったのはその通りです。この後、英蘭戦争でオランダは英国の後塵を拝することになります。
スポンサーリンク