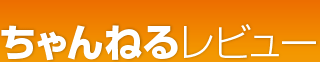『インビジブル』で高橋一生さん演じる志村が、車に乗っていたが渋滞にはまったので、降りて近くを走っていたバイクを止め警察のバッジを見せてバイクを借りるシーンがあった。
こういうシーンって久し振りに観た。
昔は主に舘ひろしさんが「借りるぜ」と言って強引に借りて走っていくシーンをよく観た気がするが。
昔のドラマは何かと説教臭い中高年男性キャラがドラマに付き一人か二人いたものだが最近のドラマは中高年も若者も一緒になって子供が口にすようなセリフを言うようになった。顔芸の激しいドラマなどはとくにそうだ。「叱る」というより「怒ってる」だけの大人の描写が増え、若者のほうが忍耐力ありそうな描写もあったりする。現実もそうなったのかもしれない。
BSで古いドラマ見ていると時代劇でも現代劇でも
よく出てくるチンピラ。
からかったり、難癖付けたり。
それを助ける人。
それがきっかけでヒロインは大事な人に出会う。
意外と大事だったチンピラ
なぜ今のドラマでは出てこないんだろう?
昔のドラマでは店の主人がそろばんを弾いてあの独特の弾く音が鳴っていたものだが、今のドラマでは見かけなくなったな。あたり前だが。
とにかく灰皿がない。あったとしても映さないし役目もない。
ドラマの最後に出てくる「つづく」
圧倒的に少なくなった。とても分かりやすい表示だったのに
(いや、表示のいう言い方もおかしいかも知れんが)
夏の炎天下、汗だくだくで見知らぬ町を歩いてぼろぼろになった紙切れのような地図を確認してはハンカチで顔を拭いている光景…スマホの存在ってやはり大きいね。
昔のアメドラにはシットコム形式のドラマがたくさんあったが、最近は少なくなった様子。この形式はアメリカにはよく馴染んだけど日本はいまいち合わない気がする。王様のレストランが最後の名作なのかもしれない。
1970年当時のドラマを観ていますが、出ている男性が、必ずタバコを吸っている。イスに座るとすぐタバコを取り出す。まるで男性とタバコがセットされてるかの如く。今のドラマで喫煙シーンは殆ど見なくなった。
昔のドラマでは「一軒家」というのがホームドラマ(家庭ドラマ)の舞台でマンションとかアパートとか、それは例えば殺人事件が起きた場所のような部分でしか舞台として描かれなかった。今では逆になっている。家庭の舞台はマンション、アパート。一方、一軒家はお尋ね場所か何らかのスポットとして登場するケースが多い。
昔のドラマは「釣堀」が撮影シーンに使われたりしたが最近はほとんど見かけない。釣堀自体は今も健在のようだ。
端的に言うと昔のドラマは画質があまり良くなかったしサイズも狭かったので料理とかスマホなどのアイテムをじっくり見せるという考え方はなかったのではないかと。その分、中身で勝負してたような気がする。
自分的にもっとも強く感じているのは教師の描写。生徒と1対1で面と向かうシーンはめっきり減り、変わって職員室で生徒不在で教師同士が揉めるようなシーンが増えた。生徒のことも教師同士が話し合う。時代を感じさせる。
自分が子供の頃に見たドラマは、大抵必ずといっていいほどヒッピー風の若い男が一人か二人、ヘラヘラ笑いながらいたものだ。時代もあるんだろうけど、そういう時代だったんだなと思う。今の若手俳優みたいにピシッとした服装してないし髪型もこじんまりとまとまってなかった。今のほうが断然カッコいいよ、でも昔は風流さがあったな。
昔のドラマにあったというか、今のドラマと比べて若い男の描写による受ける側の感じ方の認識がだいぶ変わったんだと思う。昔の男(とくにイケメンタイプ)は派手な服装、サングラス、タバコ、顔の表情、話し方など見た目でわかるくらい女性のいる前ではカッコつけていたものだ。しかし今のドラマではそれはダサさの象徴のような捉え方として表現される。シリアスなものにこうした見た目でわかるカッコつけによるビジュアルはもはや見られない。むしろコメディの分野で大活躍。今のイケメン俳優の演技は外側から内側へとカッコ良さをしまい込むところがある。この若い男優のカッコつけの描写は昔よりも今の方が良い。
レコード屋。これに尽きる。ドラマの中でタワーレコードだか店の中で今考えたらありえないくらい大きくて平たい30cm四角板を引っこ抜いてはしまったり…でも、あんな大きいのカバンには入らないから昔の役者、腕と横っ腹に挟んで持ち歩いてたな。今では考えられないアイテムだ。
道路で水をまく人。ドラマであまり見かけなくなった。
水をまくという行為はもちろん今でもやっているだろうが、
ドラマでそれを見せることに何の意味があるのかと
最近の演出家は考え始めたのだろうか・そうかもしれない。
本編の最後に青バックに白字で「このドラマはフィクションであり、人物・団体名は架空のものです」と出てくるテロップ。
昔はみな青バックに白字だったが、最近は白バックに黒字ばかりになった。新作はそれで良いが、違和感が有るのはTBSチャンネル等の有料CSの旧作の再放送の最後まで白バックに黒字のテロップに変えられてしまっている事。
恐らくオリジナル原盤にあのテロップは含まれておらず放送のたびに局側で用意していたからだろうが、あの青バックに白字のテロップも含め作品として記憶しているのであれはちょっと淋しい・・・。昔の日テレのドラマやTBSのドラマは青バックに白字のテロップでないと落ち着かないし、作品を観た気がしない。
放送禁止用語。
筒井康隆氏が「あれもこれも駄目だと言ったら書く物が無くなってしまうよ!」と言ったそうだが、
酋長、ブッシュマン、靴磨き、ルンペン、川向こう、お百姓さん、按摩、部落、乞食、アメ公、ナチス
といったものも今、番組によっては駄目なのだそうだ。
啞、盲、聾、かたわ、気狂い、チョンはさすがに駄目だと思うし、新作で使われないのは仕方ないが、せめて昔の作品の有料局での再放送やソフト発売では(「時代背景を考慮し〜」等のテロップを付けて)カットしないでもらえないだろうか。今の価値観だけで「昔そういう言葉の文化や習慣の時代が有った」事まで抹殺しないでもらえないだろうか。
今そういう言葉を無理に使えとは言わないが、昔の記憶や思い出を改ざんされるのは強い抵抗が有る。
このレビューもそのうち「不適切な言葉が有る」と削除されるのだろうか。
ベタですが、刑事ドラマで取り調べ室に差し入れされる「カツ丼」。
前のコメで最近のドラマはジャズ調の音楽が流れなくなったとの指摘があるけど、そのことにちなんだ話をしたい。「2001年宇宙の旅」という映画で監督のスタンリー・キューブリックが何故、当時としては最新の技術を駆使したこの映画のバックミュージックとしてクラシック音楽を取り入れたかって話…これについてはさまざまな憶測を飛び交っているけど、一番の理由は「少しでも映画の鮮度が落ちるのを防ぐため」というのがあったらしい。流行の音楽を鳴らすとその映画は時代の移り変わりとしてその当時に使われた音楽と共に古くなってしまう。そこで逆転の発想でクラシックというのが鮮度を保つもっとも保存機能に秀でた「防臭剤」になると。日本映画を例にあげると1980年代の日本映画はロック調で演奏もエレキギターの音色を効かしたものが多かったが、そういった状況の中で「Wの悲劇」という映画はサティのジムノぺディ(それもドビュッシー編曲版のもの)を流していた。これがその作品の鮮度を保たせているとも言えなくもない。
最近のドラマはクラシックを土台にしたオーケストラ演奏が主流だけど、制作側もそのことを念頭に入れているかもしれない。ただ、ジャズが時代遅れの音楽と一部では言われているが、それには少し抵抗があるけどね。
こちらのスレは大変勉強になります。
ボケ~っとドラマ見ている自分に、気付かせてくれることがたくさんあり、ゆっくりドラマを見られる時はそういう風に見ようと心がけるようになりました。
ある客が暖簾をくぐりながら店に入る。客が店内をキョロキョロと見回しているとき、店の奥は6畳一間くらいの部屋があってコタツやらTVがあり、そこにいた店主が客のほうに振り向きながら「いらっしゃい」と声をかけながら立ち上がり、客に応対する。なにげないシーンなのだが、こういったシーンが少なくなったのはやはりコンビニの普及に関係しているのだろう。今では古本屋のような特殊な空間を持たせる演出として使用されるケースが多いと感じる。
夕暮れ、「◯◯ちゃん、ごはんよ〜!」と遊ぶ我が子を迎えに来るお母さん。コロナ事情含め、外で遊ぶ子がほぼいない今では絶滅と言っていい風景だが、コロナを登場させない(させられない)サザエさんでも最近見かけなくなったような。「カツオ、ごはんよ〜!」の前にカツオ自分で帰って来てしまうパターン増えたような。
熱血教師とちょいワル高校生達のベタな青春ドラマって無くなってしまいました。
あるいは、俺たちの旅 とか 俺たちの朝 のような、大学生の青春物。
青春って現代ではダサいのかな?
ベタですが、
「石や〜きいも〜、おいも!」
「毎度おなじみ、ちり紙交換・・・」
「竹やぁ〜、さお竹!」
「廃品回収車です。ご家庭内でご不要になりました・・・」
等、通りから聞こえてくる移動カーでの呼びこみ。
正月の初七日、おせちだけで食い繋ぐ展開(昔の正月はスーパーやデパートが休みで、コンビニも無い時代は食料調達出来なかった為)。
正月でなくても、昭和50年代ぐらいまでは会社から帰宅すると食卓の上に〝炊いて茶碗によそったご飯〟〝あたためてお椀によそった味噌汁〟〝皿に盛ったおかず〟を用意して食べる風景がドラマで有ったものですが・・・。
バブル辺りからコンビニ競争時代になり、今のドラマで描かれないのは当然としても昭和を描いた今のドラマでもその時代の風景としてあまり出て来なくなった(当時を知っているスタッフがほとんどいなくなった)のは淋しい限りです。
ドラマの中で日中、主婦がベランダに布団を干してバンバンと威勢のよい音をたてながら布団を叩くシーンがよくあったが最近はあまり見かけない。昔はホコリやダニを追い出す効果があると信じられてきたが、その後の実験や調査により、叩いてもダニなどは取れないことがわかり、ホコリが四方八方にばら撒かれてかえって逆効果であることがわかってきた。現在では布団の中のホコリやダニは掃除機などで吸い取るのが最良にして効果的といわれる。
ドラマ制作もこうした科学やさまざまなデータ、実験などにより昔は常識であったことが今では「それは間違っていた」ということになり各シーンの見せ方や役者の演技も変わっていくのだなと改めて思うしだいである。
自宅を訪れたお客さんと、玄関で座って会話するシーン。
間違いというより、昔は掃除機がなかったわけで、家事のやり方が変わってきた側面もあると思います。
主婦が手拭いを被りハタキをかけて掃除するシーンがなくなり、掃除ロボットがドラマに出てくるようになりました。
雑談ですみません。
日本の電気メーカーは 掃除ロボットを iRobot 社よりも、かなり早い段階で企画していたんだけど、その開発許可が上層部から下りなかったと言います。
その理由というのが、
「日本には仏壇に蝋燭を灯す習慣がある。掃除ロボットが仏壇にぶつかって火事が起きたら責任が取れるのか?」
という事だったらしい。 日本企業の保守性を象徴する逸話です。
そういえば、仏壇の蝋燭、線香に火を灯して先祖を拝むシーンも激減しました。 都会では仏壇がある家が珍しくなったんじゃないかな?
前の方のを読んで、仏壇に蝋燭を灯して拝むシーン、そんなに少なくなった?と思ったのは、多分、毎日やってる昔の2時間ドラマの再放送枠をよくつけている(いつもちゃんとは見ていない💦)からだと気が付いた。
仏壇に蝋燭を灯して拝むシーンは、昔ながらの捜査ドラマによく出てくるシーン。
殺された人の遺族宅を刑事が訪ねて話を聞く前後に手を合わせたり、身内の復讐がらみの犯人が殺された人の遺影に話しかけたり眺めたり。
ホームドラマの朝ドラなんかだと、亡くなった祖母とかがナレーション役だったりして、毎回のように仏壇が写るシーンがあったりするけど、仏壇シーンと言えば、殺された人の遺影を出す為のシーンが多い。
刑事が歩いて捜査するような定番の捜査ドラマが減ったことが、仏壇シーンの減少に繋がっているのかも?
昔ながらの刑事ドラマは、仏壇が大事な小道具だったんだなぁと初めて気付いた。
まぁ、まさか刑事ドラマを見て、この仏壇いいな、と購入する人もいないと思うので、仏壇の宣伝効果はなかったかもしれないけど、そういやクレジットに、以前は仏具屋さんの名前をよく見かけた記憶はある。
刑事ドラマも今は色々変わり種?が出てきているし、遺族に会う場所も遺族宅ではないことが多くなってきているので、仏壇の出番が減ったのも頷ける。
銭湯風景。めっきり減ったな。昔は男風呂でも女風呂でも中の様子までナチュラルに撮っていたけど。
昔のドラマにはあまりなかったが今のドラマには多いという逆説的な考えで言うと、女性経済社会進出に伴ってビジネスの中心に若い女性が君臨するというスタイル、これは昔のドラマでは目にすることはなかった。
女性が男性と対等に働くシーンが増えましたよね。
男性が家事育児をするシーンも増えました。
バブル期より生活が質素に描かれていること、母子家庭の設定が増えたことを感じます。
菓子パンと箱牛乳で張り込む刑事。
刑事の張り込みシーンもそうですが、「太陽にほえろ!」の初期の山さん(露口茂さん)のように〝情報屋に折った札を包装ビニールにはさんだタバコの箱を渡すシーン〟〝雀荘でマージャンしながら情報収集するシーン〟も無くなりましたね。
「太陽〜」の後期(神田正輝さんのドック登場以降)には既に山さんのこうしたシーンは無くなっていて寂しかったですが、今は更にタバコは電子タバコになり札がはさみづらくなった上にコンポライエンスでドラマ内で喫煙シーン自体が出せず、昼間からマージャンする刑事を出したら職務怠慢とクレームつけられてしまうんでしょうね。
昔の刑事ドラマは一見、そういう不謹慎だけど実績はあげている(=結果的に犯罪は減っている)小さな必要悪の部分もちゃんと描かれていて、凄く説得力あったんですけどねえ。はさまれてるのが千円札じゃなくて一万円札だったら「あっ、この情報屋は大変なネタを仕入れて、山さんは労をねぎらってやってるんだな」とわかったり、雀荘で良い情報を掴ませてくれた相手にわざと負けてやって報酬がわりに払ってやったり、そういう〝人間関係のヒダ〟が垣間見えるほうが俄然味があるじゃないですか。
昔の刑事ドラマの一見、不謹慎だけど実績はあげている(=結果的に犯罪は減っている)小さな必要悪のシーン
映画館やプラネタリウムで刑事と情報屋が待ち合わせて、暗い人目につかない中で証拠のブツを渡したり報酬を渡したりするシーンもそうですね。
家に帰って来ると和服やガウンに着替えて室内でくつろぐお父さん。
今はそこまで年相応に老けてお茶を飲んだり新聞を読む父親もドラマで出て来なくなり、タブレットやスマホでニュースを読んだりコロナで「ラフな服装のほうがいいや」という人が殆どというところでしょうかね。
昔は夜遅く帰って来て、10時・11時台の女性の裸を織り交ぜた番組を酒をかっくらいながら見てクダを巻くサラリーマンのお父さんのシーンなんかもありましたね(酔ったまま寝てしまい、当然12時半過ぎたりすると番組は終わり、TV画面は砂の嵐・・・)。残業して帰り飲んで、へべれけになって紐で結ばれた土産をぶら下げ、千鳥足で帰って来て玄関入ったらそこで大の字なお父さんのシーンなんかも(サザエさんの波平さんは今もそう?)。
今は残業削減で、コロナで出歩きもしてられないからそこまで遅くなるお父さんがいない。退社時間は早くなったのに仕事は増えてたりして、大変なのに息抜き出来ないみたいな。だからよけい昔のクダ巻いたりへべれけだった時代の風景が懐かしくなる。
出前シーンがめっきり減ったなぁと思う。昔は「ガラスの仮面」で舞台女優になる前の北島マヤとか「眠れる森」でも出前シーンはあったかあまり憶えてないけど路地を入ったところに大衆食堂であたふたと従業員が仕事をする場面とか、そういう店先で何か活気に満ちているようなシーンが減った。
そういや寿司や蕎麦を幾重にも重ねて、それを片手に持ち自転車やスクーターで出前するシーンって無くなりましたね。昭和のドラマはそれで誰かにぶつかりそうになりよけて電柱に激突!か転んで出前を台無しにするのが定番でしたよね。
おかもちの出前って確かにTVで出て来なくなった気しますね。昔の刑事ドラマだと人質になった刑事に出前に化けておかもちの中や裏に貼って隠した武器を渡したり、逆に凶悪犯が出前に化けて署に潜入しおかもちの中から武器を出して立て籠もったり、出前を装って爆弾を届けたり・・・。「出前」が結構、物語の重要なファクターとして使われたんですけどね。
今は宅配、ウーバーイーツの時代。
出前を営む料理店自体ないでしょ。
仏壇の前に正座してチーンと鳴らし手を合わせるシーンをあまり見なくなった。昔のホームドラマなどでは頻繁に行なわれていた記憶がある。
昔のドラマはネットなどを気にする必要がないから、その制作過程において思い存分作り込めたわけだが、今は「こういう演出をすると何故、SNSの機能を使わないのか?」ということになり、どんどん新しい機能が積み重ねられるIT機器に遅れないように、そちらのほうにも気を配らなくちゃいけない。制作がかなり難しくなってると思う。
SNSのような科学技術分野だけでなく、以前から続いた視聴者からのクレーム、ドラマの真似をして世間に迷惑をかけたりなどで、年々作りづらくなるのは仕方のないことかもしれない。このスレのテーマもそういったことを含めてのものだろうしね。
瓶の牛乳を飲むシーン…確か記憶では「眠れる森」が最後だったような…そんなことないか。でも最近は見ないな。銭湯はどうなってるんだろ?若い頃はよく通ったけれども。
朝ドラなんかでよくあったけど、次回に続く…という際の最終シーンで、人物がある表情やポーズをしてしばらく不自然にじーっと動かない、のがお決まりだった。
役者さんも大変だなあ、と思ったことを覚えていますが、今は自然にあっけないくらいスバっと最後を切りますね。
再放送群では比較的新しい方の、「芋たこなんきん」もそうだったから、あれ?と思いました。
2007年だったか、2008年だったか。
とすると、最後あっさり終わりは、ここ5〜6年のトレンドなのかな。
『人物が動かないで「つづく」が出る最後のシーン』が無くなったのは、地デジ化・ハイビジョン化した2011年以降じゃないですかね。
番組がオールハイビジョン制作(NHKは一番率先してハイビジョン開発していた局ですから2000年代途中からハイビジョン制作の番組作ってましたが)になってから減っていった印象が有ります。高画質で容量が増え、余裕が出た分だけ技術も進み画面編集がスムーズになった分、じっくりした場面作りよりスピーディーなカット割りが増えたような。
エンディングのスタッフ名表示が『消えてまた次の人が表示or下から上へスクロール』だったのが『右から左へ早くスクロール』するのが増えたのもその頃からの気がします。
スポンサーリンク