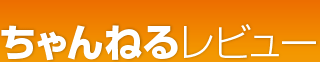昔のドラマはテーマソングに歌詞の字幕がついたりしなかった。子供向けの番組の場合は人によりどのように聞こえるのか差があって、子ども同士で言い争いになったりしたものだ。その後子供番組に限り字幕がつくようになり、やがて大人向けのドラマにもつくようになった。
昔のドラマの俳優は考え込む顔をする際、まゆげを寄せて顔をしかめる場合が多かった。
今のドラマの俳優は一見、ボーっとした表情に見せながら目線を少しずらして
2~3秒静止するような場合が多い。これはリアルを追求した結果だと思う。
実際、人間が考え込む瞬間の顔は人それぞれだが、まゆげを中央に寄せる人は少ないなぁ。
リアルを追及するといっても、第一話目でやたら余計なことを話すのは変わらない。そうでないと登場人物がどういう人であるかさっぱり分からないから。もしくはナレーションで説明を入れるかだが。
確かに第1話でひと通り説明しなくちゃいけないよね。
しかし昔でも今のドラマでも上手く登場人物を紹介していくドラマもあれば
初お目見えの人物に字幕で名前を記される(芸はないが分かりやすい)の
2種類があるけど毎回毎回字幕出されるケースって昔はそんなになかったかな?
91さんへ。
まだあったんですかぁ~、行ってみたいです。
今はコロナなんでそんな理由で外出できませんが。
91さん
ほ、本当にまだあるんですか?ビックリだー
昔のドラマでは入院患者の病室入口にはちゃんと名前が掲示してあって見舞客も「ああ、この部屋ね」と確認できた。今は個人情報があるから部屋番号のみの表示が多い。
橋田壽賀子ドラマはここ数年ライフワークともいえる「渡鬼」特別編と単発ドラマに限られるようになった。長ゼリフでテレビを見ていない主婦にも分かるようにする手法も遠くない将来過去のものとなるだろう。
家の中の様子で映し出されるのはキッチンのある部屋が多いが、
昔のドラマは食卓で何を食べているとかあまりこだわらなかった。
昔は赤ちゃんを抱っこするシーンは人形が多かった。実際に赤ちゃんが出てきても設定よりは明らかに大きい子、新生児なのに生後3か月くらいの赤ちゃんとか出てた。
今でも新生児を使ったりしていないと思う。さすがにそんな赤ちゃんタレントはいないだろう。というより、生まれてすぐに登録できるはずも無いが。声だけ流して姿がはっきり見えないというものが多い。
「コウノドリ」「透明なゆりかご」では本物の新生児も登場しました。
医療ドラマは昔から今の時代に至るまで目覚しい進化を
遂げているようだね。中には後退してしまったシリーズもあるけど。
白い巨塔(1978)=白い巨塔(2003)>>>>>>>白い巨塔(2019)
自分としては1978年度版と2003年度版は同等のクオリティ。
今のドラマって説明が多い気がする。そのかわり体が動かない。
横に広くなった画面を映像を見せるというより、タレントをなるべく多く
カメラ内に収めて見せるためのものになっているのも気になる。
昔の役者のセリフってやたら大袈裟だった。現実だったら絶対に言わないような臭いセリフが多かったのは確かだ。
昔のドラマは芸能事務所が前面に出てきて制作側に注文をつけることが
少なかったから、制作側主導のヘンに凝った作品もあったりした。
今はジャンルそのものが狭くなる代わりに事務所受付カウンターだけが広くなった。
昔のドラマでは役者が制作に絡んでいるケースがあった。
石原裕次郎、勝新太郎、田宮二郎など、何らかの形で
制作側といっしょになってドラマや映画作りをしていた。
今は事務所が完全にタレントを管理していてドラマの制作に
携わるというより、ドラマの制作に「はめ込まれる」という感じ。
昔のドラマは「おっさんずラブ」とか「きのう何食べた?」のような
テーマを持つドラマはなかった。男は基本、女がいて「男」がいる、という
意味合いの「男」で合致していた。そもそも「テーマドラマ」というジャンルが
それほど普及してなかったし、やはりSNSの存在が大きく響いているな。
たぶん、新しいテーマを考えているうちに、ほとんど過去に
やったものが多くてそれで行き着いたのが男と男のラブロマンス
なんだと思う。昔はそういう意味では正攻法だったよね。
親子の絆をとことん描くようなドラマが減った気がする。
昔のドラマは家族では父親が親子間で活躍したものだが
今のドラマ(特に民放)では母親が軸となって子供の面倒を見る。
そうだ、昔のドラマではお父さんは帰ってきたら浴衣かドテラに着替えるんです
今それをやってるの磯野波平さんだけ
のび太のパパもそうだったけど途中でやめてる
赤井英和、桜井幸子などが出演していた「人間・失格」などは
今のドラマでは組み込めないテーマなのかもしれないな。
そもそも野島伸司とか使いづらい存在になってしまっているし。
昔は民放で20時から普通に時代劇をやっていたな。
水戸黄門だけでなく江戸を斬るとか。
民放で時代劇をやっていた頃が「昔」と思う世代もいることに驚いた。私からすればつい最近のうちに入る。
「いじめ」の描写が活劇的なシーンから
SNSにより頭脳攻撃に変わった。指先で相手を殺せるみたいな。
家なき子(野島伸司=企画)のようなドラマは今の時代では
厳しいだろうな。最近は子役が目覚しい飛躍を遂げているが、
安達祐美はいろんな意味で子役を振り幅を広げた先駆者だ。
訂正
子役を振り幅を=×
子役の振り幅を=○
失礼しました。
時代劇は、制作年代が遡るほどに台詞の言葉遣いが日本語の美しさを感じさせてくれるように思います。現代の時代劇よりも言葉遣いが難しかったり、時代背景を上手く取り込みながら虚構の世界を描く脚本になっていたりします。当時の視聴者の理解度がうかがえます。
20年前に放送された「眠れる森」などのような全話を通じて伏線を
張り巡らせたドラマは今は視聴率が思うように取れず、作られなくなった。
最近になって「テセウスの船」や「10の秘密」などが制作されたが、
今時の視聴者から「内容を覚えていない」とか「途中から見たから分からない」
あるいは「見るのが面倒くさい」などといった非難の声は避けられない。
別に考察ドラマではないが「北の国から」のようなものさえ作られなくなった。
映像処理やセリフで使う言葉の多様化など進歩しているのは事実であるが
視聴者はもっと手短に、もっと薄味に、もっと即決にといった要望があるのか
知らないが、カタルシスを得るための我慢強さの値が低くなったかな?と感じる。
昔は録画機器など無く、一話見落としても問題無いように毎回一話完結になっていることが多かった。そのためにはやたら伏線を入れたりすればわけがわからなくなるから極力避けていたのだろうと想像する。小説であれば見返すことができるからそういう設定は昔からあり、ドラマ化する際に設定を変えなくて済むようになった。
もっとも、昔は一年間放送するのが普通だったのに対し、今はワンクールで終わるものが多い。1年間ものだと長期間役者を拘束しなければならなくなり、視聴率が低い時にかなり無理な終わらせ方をしたり、何らかの理由で離脱する役者が出る時に急死させたりしなければならなくなって問題が多かったのも確か。その代り不祥事を起こした役者のキャストチェンジも昔はあまり無かった。当時はかなり問題のあることをしていても容認されることが多かったからだろう。昔のキャストチェンジは病気などの場合がほとんどだったと思う。
昔のドラマで凄いと思うのは例えば「太陽にほえろ!」のように
全718話まで飽きずに制作し続けたその姿勢とタフさである。
ひとくちに718話というけれど1時間ドラマでしかも1話完結で
ここまで作れるというのは今考えると「植物的」な生命力を感じる。
ただ、あの頃はいろんな試みが新鮮だっただろうし、過去のデータも
今ほど蓄積していないんで作りやすいといえば作りやすかっただろう。
そういえば25年くらい前に「青空にちんどん」という
ちんどん屋をテーマにしたドラマがあったが、ある意味、
昔の日本文化を伝える貴重な作品だった。このドラマの
ように日本文化を継承するようなドラマが今は少ないな。
ひとくちに言うと例えば男同士でいきなり相手を
ぶん殴るようなシーンが少なくなったと思う。
昔の漫画にバタ屋という言葉が出てきて思い出した。
昔のドラマにもあったなぁバタ屋さん。
森光子さんがやっていたドラマでも。
チンドン屋さんは昭和の終わり頃まで見かけました。
大売り出しのチラシなどを配りながら。
やってる方たちが実に楽しそうに。
今の子どもたちは知らないのでしょう。
ゴム紐を高く売りつける押し売りのシーンなどもよくありました。
万年筆で手紙を書くシーンが懐かしい。
買い物籠と御用聞き。レジ袋が生まれた時からあった人は知らないだろうな。「買い物籠」はスーパーの中で使う籠のことではないので念のため。
最近は特に傾向が強いと思うのが、残虐なシーンやリアルな死体のシーンだ。
放送コードが規定されているのか自主規制によるものか分からないが、刑事物やサスペンスでそこの部分を飛ばされると、犯罪者の心理なども薄っぺらに見えて、ドラマ自体が平坦になってしまう。
最近のドラマは、いろいろなところに配慮しなければいけないから制作側は大変だと思うが、そのマイナス要素を補って余りあるドラマを作ってもらいたいと思う。
ゲゲゲの女房に買い物かごを買って買い物するシーンがありました。今はレジ袋が有料化されたので、エコバッグを持って買い物に行く時代になりました。
今はスーパーで買い物するシーンだけど、むかしは商店街の酒屋や八百屋のおじさんとかタバコやのおばちゃんとかが出てきて優しかったです。
昭和懐古になってしまいごめんなさい。
レジ袋、今はポリ袋が一般的だが、一時期紙袋が用いられていたこともある。かさばるためかポリ袋が普及すると使われなくなった。私の住んでいる地域では昭和50年代初め頃までだったように記憶している。ゴミ出しにも便利なためか、これと反比例するように青いポリバケツが使われなくなった。
CSで「パパと呼ばないで」が放送されたとき杉田かおるさんのインタビューで「あれ、写っちゃってますよね?」と入浴シーンへの指摘が
杉田さんは「子供だから前張りなんてしないしw」と笑ってましたが今ならコンプライアンス的に不可能な撮影
「渡鬼」でも子役時代のえなりかずきが全裸で出演している。当然ながら当時の映像を地上波で再放送することは不可能だろう。
昭和のドラマのオープニングは、たいがい主題歌から入り、その後、民放ならスポンサーの紹介(この番組は〇〇の提供でお送りします)その後、そのスポンサーのCMを数本流してからドラマ本編に入っていた。
今はいきなりドラマ本編から入り、しばらく経ってからスポンサー紹介、しかも昔のように画面がブルーバックにならず、ドラマの映像をそのまま映しながらやっていて、しばらくCMは流さない。
出演者、スタッフのクレジットも、ドラマの映像を映しながらやっている(例外はNHKの朝ドラで、昔のように主題歌の中で出演者、スタッフをクレジットしているが、これにしても最初にドラマ本編を少し流してから始めている)
そして昔は初回だろうが最終回だろうがスペシャル、拡大版など無かった。
どの回であろうが1時間なら1時間と、キッチリ決められていた。
続編やシリーズはあったけど、スピンオフドラマなど、なかったよね?
昔はドラマに限らず、次の番組との間には必ずCMが入った。最近はトイレ休憩に入られたりその間にチャンネルを切り替えられたりしないようにするためなのか、すぐ次の番組に入ることも多い。その代わりといっていいのか、前の番組の終わり辺りははやたら細切れにしてCMを入れたりしている。
大雑把に言うと昔と比べてCMの入れ方がやや雑になった
印象があります。ドラマはともかくとして映画などは
それを強く感じます。せっかち気味と言おうか…。
NHK bsで再放送されているけど、刑事コロンボの中でも最高傑作の一つと言われている「別れのワイン」ではコロンボも犯人もレストランで秘蔵高級ワインを楽しんだ後、平気で飲酒運転している。
スピンオフドラマと呼ばれるものは無かったが、ウルトラシリーズの後に単発番組として夕方の時間帯に放送されていた「ウルトラファイト」は今思えばスピンオフと呼べないことも無いと思う。
昔のドラマは夏の設定ではハンカチで顔を拭きながら歩く人が多かったが、
最近のドラマでは汗を拭く以前にハンカチを持っている姿をあまり見かけ
なくなった。汗をかいたらかいたで放置状態。
スポンサーリンク