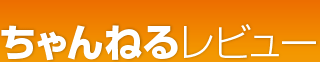249さん、企んでいる女さん、ご投稿ご配慮ありがとうございます。
栄一は柔軟ですね。今後は中村芝翫さんの岩崎弥太郎との対決とかが面白そうです。弥太郎は豪農の栄一と違い武士の最底辺の地下浪人の出で、貧農から武家奉公人の中間になった伊藤博文とよく似ています。叩き上げなのです。どうなるか楽しみです。
「鎌倉殿の13人」は盛況になると思います。「麒麟がくる」がそうでしたから。学者の本にも載ってないような内容を書く人が何人も投稿され、今度はしかも三谷幸喜さん脚本でチーフ演出が「エール」と同じ吉田照幸さんですから、これは絶対面白くなると思います。
私がスレは立てずとも盛り上がるでしょう。わくわくしてきますね(^▽^)/。
栄一と平岡円四郎を通じた一橋慶喜との出会いは感傷的で感動的だった。円四郎自身が慶喜との出会いで農人形で百姓の勤労に感謝し飯の盛り方から教わり、藤田東湖を徳川斉昭の諍臣として心を打たれる場面があった。今日も慶喜は駿府での商法会所でのビジネスで慶喜に尽くそうとする栄一に東京の明治新政府に仕えよ、と静かに諭した。それはこれまで同様に感動的だった。
一方の明治新政府であるが、これはコメディタッチで大隈重信は日の本を支える八百万の神たらんと栄一を説得する名言を吐き、さすがの栄一も感服するのだが、酒の勢いを借りて談じねば栄一の気力に圧倒され妻や伊藤博文の前でオタオタするし、大蔵省と間違えて明治新政府の最高会議に乱入し言いたい放題の栄一に制止する大隈は腕をねじ上げられて吹っ飛ばされるし、岩倉具視は脅えて「何や、あの無礼な男は」と席を立つし、武家出身の大久保利通と松平春嶽ら以外の狼狽が実にコミカル。伊藤博文も制止に加わり大蔵省でなく新政府の最高会議と知って慌てて土下座の栄一。面白すぎます。ドラマのトーンが慶喜との感傷的感動的設定からスラップスティックコメディーの世界に。
同じようなトーンだと長期作品は飽きが来るのを見越してコメディタッチに変えたのは朝ドラだと「すずらん」「カーネーション」と「ひよっこ」もややそうかな。「青天を衝け」はこのところ視聴率が長期的に低落傾向でしたが、この手法で上述作品群は後半に視聴率が上昇モードになり、大森美香さん脚本は「あさが来た」同様に視聴率を意識した展開が上手いと思いますね。
栄一の新政府デビューがまさかのコント風😆
大倉孝二さんが大隈重信だと、どうしてもコメディタッチになりますね(^O^)
多くの出会い、再会、別れが泣ける回でした。
仲睦まじい慶喜と美賀君が素敵でした、やっと夫婦らしく穏やかに暮らせますね。
そして栄一には「大義であった、息災を祈る」と告げる優しい慶喜ですが、2人の交流はまだまだ続きますよね?
静岡の杉浦愛蔵や商法会所の仲間との別れがちょっと寂しい…
「ここはもう立派なコンパニーだ」と、波岡一喜さんが珍しく笑顔になって栄一を送り出す場面は可愛い、じゃなくて頼もしかったです。
旅の途中で猪飼様とも再会出来ました。
ところで「おかえりモネ」の漁協組合長さん役の菅原大吉さんは「この人、つい最近別のドラマで見た気がするけど何だったかな?」と思ったら、青天を衝けの「伊達様」だった!!
253さん、ご投稿ありがとうございます。
明日の「青天を衝け」は今までとは違った意味で楽しみですね。明治編はコメディタッチで来るんでしょうか。
朝ドラだと「すずらん」は「「おしん」を目指せ!」の掛け声で制作されましたが老年編で尾藤イサオさんが登場すると完全な爆笑キャラに。毎回のように噴き出さざるを得ませんでした。それまでの感傷的でシリアスな雰囲気が激変。「カーネーション」もぼっしゃん。さんの北村が2月から爆笑キャラに。これもシリアスからコメディタッチに激変。
大森美香さんはどうするのでしょうか。ちょっと、明治の重鎮が軽い連中のようになるのもこれはこれで問題はありますが(^^;)。
趣味人として生きた慶喜をもっと見たいですね。こう言う人生の楽しみ方もあるのですね。
菅原大吉さん、朝ドラには欠かせない人ですね。
「あまちゃん」で知りました。「まんぷく」でもGHQと折衝する国税の部長役でした。宮城出身ですから方言はネイティブなんでしょう。伊達宗城も殿様っぽさがよく出ていると思います。あまりにイケメンばかりだと嘘くさいと個人的には思います。
明治5年に新橋と横浜の間に鉄道が開通。
さっそく渋沢は視察に出掛けた、発車寸前の列車を感慨深げに見ていると、ホームに靴👞靴👟靴👠だらけ。あわてた渋沢は靴を手に持ちお客様靴
お忘れです!渋沢の絶叫も虚しく発車した、しゅぽ、しゅぽ。お客様の靴を手に持ったままホームに座り込む栄一、その後ろ姿にはどことなく哀愁が漂っていた。
令和のいまでもたまに電車や飛行機に乗るときに
靴脱いで乗られるお客様がおられるそうです。
たこさん、ご投稿ありがとうございます。
私の母方祖母(明治30年代生まれ)は流れ星を見て「あっ、魂や!」と叫んでいました。ホトガラ(フォトグラフ=写真)を取られると魂が盗まれると言っていた人もいたそうですね。
最近、は電車で靴を脱いで前の座席の上に足を乗せる不届きな高齢男性が時々いて、通常は放っていますが、高齢女性が座っており困惑してると、止めるように、と言っても聞かないので車掌に通報したことが何度かあります、はい(^^;)。私の年齢で高齢は70代以上です。
2018年にnhk bsで、明治5年の鉄道開業「蒸気機関車が走った日」のドラマやってました、ドキュメンタリー仕立てのドラマで、鉄道マニアの六角精児さん主演だったような?
とても面白かったので、もう一度見たいな、と思いました(今年になってから再放送されたようですが、見逃しました)
鉄道敷設には大隈重信が賛成、西郷隆盛が(お金がかかるので)反対、この2人が激しく対立、六角さんは何の役だったかな?
正式な開業日には、お召し列車が新橋~横浜間を往復して走り、明治天皇をはじめ新政府のオールスターメンバーが乗り込みました、というような内容だったです、その中にもちろん大蔵省の渋沢栄一もいたようですね。
この鉄道の話もこれから「青天を衝け」の中に出てくるんですかね?だとしたらネタバレになりますね、ごめんなさい。
渋沢栄一がホームにあった靴を手にもちお客様と叫ぶのはいつものオリジナルです。😄
ドラマでぱくるのは自由です、遠慮なくぱくっていただきたいと思います。
257さん、ご投稿ありがとうございます。
ご指摘の「ニッポンに蒸気機関車が走った日」はBSプレミアムの3年前のプレミアムカフェのドキュメンタリードラマですね。六角精児さん、矢柴俊博さん(「まんぷく」「ハコヅメ~たたかう!交番女子~」でもお見掛けしました)が出っていたようですね。オンデマンドでは見られるようですが加入していないのです。
ぜひ地上波でやって欲しいですね。
他作品で史実ですからネタバレにはならないと思いますから大丈夫ですよ(⌒∇⌒)。
「青天を衝け」でも描写があるといいですね(^▽^)/。
「青天を衝け」は本当に斬新なドラマですね。
私はかねてから大河が薩長藩閥政府を肯定する作品に偏り、「徳川慶喜」は戊辰戦争後の明治維新で終わってしまい、唯一、山田太一さん脚本の「獅子の時代」が民衆の立場から明治政府を批判的に描いており、「新平家物語」と共に好きな大河の代表作でしたが、これとて伊藤博文は自由民権運動を制圧する側ですが大久保利通は改革に理解ある人物で、黒田清隆の細君を泥酔し斬殺した事件の隠ぺいは娯楽作なので省略はいいのですが、秀作ながらトーンがあまりに暗い。監獄で反体制の指導者が拷問死等がそうです。
「青天を衝け」はとにかく明るく前向きです。幕臣も薩長土肥もない。後の英国の労働党のラムゼイ・マクドナルドや保守党のウィンストン・チャーチルの挙国一致の政府で国難を乗り切る姿勢に通じるものを感じました。大隈重信が大久保利通と合わずに職を辞し代わりの井上馨が派手に登場し、栄一が「これまた癖の強い(人物が上司かあ)」と呟くのには笑ってしまいました。
栄一の両親もいい人ですね。息子を殿様呼ばわりする市郎右衛門。好人物ですが昔気質なんですね。家族愛が伝わってきて温かい。
郵便制度も整い栄一の努力が実る一方で、大久保利通らは相変わらずの権力闘争。侍の性なんでしょうか。ついに岩倉具視が引導を渡すのでしょうか。
見ていて晴れ晴れとする大河です。
郵便がでてきました、当時は郵便の強盗が多発したため、明治6年に短銃取扱規則ができ、郵便員に短銃を持つことが許されたそうです、田舎の山道なんかではいつ山賊に襲われるかわかりませんからね、ほんなこつおそろしかばい😱
たこさん、ご投稿ありがとうございます。
そなたは薩摩であらっしゃいますか。短銃取扱規則のこと、調べてくらはって、おおきに礼を言いますぞえ。しかし、岩倉はん、貫禄十分で好演であらっしゃいますけど、「西郷どん」の国広富之はんと比べて、どうにも浪速の言葉であらっしゃいますなあ(^^;)。
大隈重信はホントに「〜であーる」が口癖だったらしいですが、市郎右衛門さんが栄一夫婦を「殿様、奥様」と呼んでいたのも事実、とネットの記事で知ってびっくりでした。
栄一の長女の歌さんの手記に書かれてるそうです。
とっさまは、あの頃は商売で、よく横浜まで出掛けていて、その往復の途中東京の栄一の屋敷に立ち寄る(時にはかっさまも一緒に)のですが、勿体ないと言って栄一宅には決して泊まらず、栄一が両親の為に用意していた(明治維新で国元に帰った大名屋敷から買い取った)新しい立派なお布団も使わず、いつも旅籠に泊まっていた、というのも史実だそうです。
それから、たこさんご指摘の、明治初期、郵便脚夫(配達人)の人達がピストルを装備させられた、というのは、要潤さんがタイムスリップして歴史を調査しに行く、という設定の「タイムスクープハンター」という番組でも見たことがあります。
「タイムスクープハンター」は低予算で作っていたらしい❓NHKの番組でしたが、面白かったのに、だんだん費用が嵩むようになったのか、ネタ切れしたのか、突然終わってしまい、残念でした。
共演していた杏さんが、朝ドラでブレイクして、ギャラが高くつくようになったので終わっちゃったのではないか、という説も有りました。
タイムスクープハンターの新シリーズ、始まらないかな、と期待しています。
263さん、ご投稿ありがとうございます。
「タイムスクープハンター」、時々見ていました。要潤さんは「嫌われ松子の一生」以来のファンです。「笑っていいとも」で芸能界入り前にガードマンとして紹介されてた映像を見ました(タモリが声を掛けたのではなくオーディションに受かったそうです)。好青年そのものですね。
元祖、この手の番組に「天皇の世紀」第二部があります。ギャラクシー賞受賞作です。大仏次郎の小説が原作ですが出演中の歴史上の幕末の人物に現代のレポーターがインタビューするのです。斬新でしたね。
私も「タイムスクープハンター」の再開を待ち望んでいます(^▽^)/。
「青天を衝け」は巧みに史実を織り交ぜながらドラマとしては笑いあり泣きあり、の面白い作品に仕上がってますね。司馬遼太郎が得意とした手法です。リアタイで見られるとは本当に幸せです(⌒∇⌒)。
今日も大河史上、歴史に残る素晴らしい描写の数々だったが、それは後に譲るとして、熱烈ファンとして、この作品で初めて異論を述べます。決して悪意あるものではありません。何より「あさが来た」脚本家と「ひよっこ」制作スタッフ(音楽は「カーネーション」の担当と同じ)で主に作り上げられた作品で両朝ドラの熱心なファンなのは今も同じです。
それは、栄一の不倫描写の方法です。
明治天皇に側室がいた時代です。徳川慶喜も渋沢栄一も正妻以外の女性の子供がいます。だから。それはいいのです。
「カーネーション」も不倫描写がありました。近いところでは「おちょやん」も。
だが、今回は手籠めにされる大内くにに栄一が行方不明の夫と似ており必要以上に親しげにし、女性の側に隙があったから手籠めにされた、と言う風に受け取られても仕方ない描写でした。ここは「英雄、色を好む」で栄一が大内くにと関係を持つ描写で十分だったのではないか、と個人的には思います。特に今回は父親の葬儀の回です。この件はこれまで。
良かったところは制作統括発案の家康のバックの黒子のいつもの展開で、脚本もそれに合わせて家康がタブレットでドラマを見ており「エトセトラ」とまたしても外来語。これは一種のユーモラスな表現ですね。
もう一つ、私は大久保利通をここまで批判的に描いた大河は知りません。「勝海舟」がややそう言う面もあったかな。
「翔ぶがごとく」「獅子の時代」も皆、好人物です。大久保利通の独裁強権的体質が当時と言う時代を考慮しても暗殺を招いたと多くの歴史書には書かれてあるのにもかかわらずです。改正掛を廃止し、自分の思うままに明治政府を動かそうとする大久保。対等に面を合わせる栄一が爽快です。
以上より、異論はあっても、それを上回る優れた内容でした(⌒∇⌒)。
「女性の側に隙があったから手籠めにされた」
は昭和風ストレート表現が強烈なので、ソフトに「女性のほうから近付いて来た」くらいでいかがでしょうか😅
このシーンと、栄一の靴下の繕いを千代が見る場面が気になって、家康のタブレットや、リモート廃藩置県どころではなくなっちゃいました。
しかも市郎右衛門とっさまが亡くなる回と、さらりと一緒に何気なく突っ込んで来るとは、視聴者泣かせです( ̄▽ ̄)
昨年の明智光秀は奥さん一筋、だったらしいですし、その前の四三さんやまーちゃんも愛妻家みたいでしたので、今年の脚本家さんはその辺の描写に苦労しますね。
266さんご投稿ご忠告ありがとうございます。
そうですね、気を遣って(特に差別と受け取られる恐れある表現)書いてるつもりでも、大内くに、の描写について表現が至りませんで本当に申し訳ありませんでしたm(__)m。以後、十分気を付けます。
個人的には大河でも史実に必ずしも忠実でなくてもいいと思うんです。だいたい、私が大ファンの「新平家物語」や一連の司馬遼太郎作品(「燃えよ剣」「幕末」等)自体がフィクションです。しかし、この人達はフィクションを史実と思わせる優れた文筆力を持っていました。現に司馬作品を史実と思いこんでる人が結構いるように思います。
明治維新以前に正妻一途だった人に他に小早川隆景がいますね。徳川秀忠は側室(妾が死後に側室に)がいましたが恐妻家でした。
まあ、新一万円札の肖像になる人ですからトピカルに扱ったのでしょうか。新五千円札の津田梅子の登場を心待ちにしています。
次期大河担当の三谷幸喜さんは「青天を衝け」を称賛し「これだけ面白い作品を限られたエピから創造できるのは素晴らしい。僕なんか史実自体が衝撃的事件だらけですから」と語っていますね。今年も来年も大河は期待できそうです(^▽^)/。
考えすぎかもしれませんが、この「青天を衝け」、私が思った以上に深い内容かも。もし、そうなら「あさが来た」の大森美香さんと、菓子浩さん福岡利武さんの制作統括、プロデューサーの板垣麻衣子さん、チーフ演出の黒崎博さんの「ひよっこ」組制作スタッフは凄いと思います。
能舞台でくだらない権力闘争の江藤新一、三条実美、井上馨らに外遊中の大久保利通も含みます。
栄一は妾を妊娠させますが(当時は当たり前のことですが)、この後の千代の描写に注目。土下座の栄一の前では貞淑な武家の奥方様のように(栄一は幕臣の旗本に出世しました)大内くにに同居を勧め子供も育てると寛容に言いながら一人になった時の大きな嘆息。
富岡製紙工場でも惇忠が娘の勇を女工に出させた後に「女性の社会進出の始まり」と称賛しておきながら、成一郎らの会話で「(女工に)読み書きを教えている」の台詞。当時は女性の識字率は男性よりずっと低かったにせよ、豪農の栄一ら一族の女性はもとより妾になった女中のお大内くにでも読み書きができるのに(栄一が自身宛てのくにの文を読む場面がありました)、です。平岡円四郎の妻も芸妓上がりですが読み書きはできました。つまり、読み書きもできない貧農の娘が集められた、と言うことです。女工哀史、つまり「おしん」で描かれた姉の死を通じての富裕層による貧農からの搾取です。
大河らしい英雄譚を明るく描きながら、「獅子の時代」が民衆からの抑圧者の明治政府なら、「青天を衝け」は女性の地位がまだまだ低く恵まれているのは大隈重信ら特権階級の妻らに過ぎない、とさりげなく台詞と演出で見せているなら実に深い素晴らしい大河です。
能舞台の空しい権力闘争を横に一人沈黙を守り俗謡を呟く西郷隆盛。「このままでは徳川慶喜公に申し訳ない」と言う趣旨を栄一と杯を重ねて語ります。
まだまだ男尊女卑で金持ちだけが栄え、薩長と公家の権力者が空騒ぎしているのをストレートには描かず、明るい大河の中にさりげなく入れたのなら、凄い大河です。
「青天を衝け」出演陣が新発表されました!
栄一の息子の篤二:泉澤祐希さん
豪商伊藤八兵衛の娘の伊藤兼子;大島優子さん
篤二の息子(栄一の孫)の敬三;笠松将さん
栄一の娘婿の穂積重信:田村健太郎さん
上に同じ、の阪谷芳郎:内野健太さん
栄一の娘の琴子:池田朱那さん
井上馨の妻の武子:愛希れいかさん
井上馨の姪で養女の末子;駒井蓮さん
益田孝の妻の栄子:呉城久美さん
大倉喜八郎:岡部たかしさん
大倉喜八郎の妻の徳子:菅野莉央さん
岩崎弥之助男爵(弥太郎の弟):忍成修吾さん
佐々木勇之助:長村航希さん
新五千円札の津田梅子はなかったが、他の女性陣で栄一の女子教育への熱情を描かれればいいなと個人的には思っています。
伊藤兼子役の大島優子さん、大河初出演なんですね、楽しみです。
富岡製糸場って建物が創業当時のものが残ってるんですね、木の枠とレンガって凄いです、戦争中の空襲にも遭わなかったらしいし、昭和の終わり頃まで操業してたとは。
工女は士族の娘も多く集められたし、いろんな身分の人がいたようですよ、惇忠が読み書きを教えている、というのは富岡製糸場に工女の余暇を利用した学校のような物も造られた、と聞いた事があるので、塾の先生をしていた惇忠が教育熱心なので、始めたのかな、と思いました。
多忙な一日がやっと終わりました。
270さん、ご投稿ありがとうございます。
私は昭和史は幾つか専門書がありますが、明治期はそれに比べれば弱いので今改めて専門書を見ました。
富岡製糸工場は明治政府が作った官営の模範工場で外国人技師の指導の下で各地から優秀な娘を集め(惇忠の娘も)西洋の進んだ製糸技術を伝習させ、次いで彼女らが帰郷等で各地にそれを広めた、とあります(井上清京大名誉教授)。伝習工女と呼ばれる人達ですね。
一方、炭鉱労働は土地を失った流浪民や江戸時代に差別されてきた人達や囚人等で過酷な労働に耐えかね大暴動が起こった、とあります。
ところが日清戦争後に産業革命が進むと、明治政府の作った富岡の模範工場のようなことが資本の乏しい製糸業者は模倣できなかった、とあります(隅谷三喜男東京女子大教授)。
渋沢栄一、大倉喜八郎らは経営者の家父長的な温情主義により労働環境は改善できると主張したようですが、明治36年に明治政府の農商務省が女工の実態を調査した「職工事情」によると零細の織物業において年少労働者の酷使、深夜労働、経営者側からの暴力と言う女工哀史の世界が公然となされていた、とあります。
つまり、私も誤っておりお詫びして取り消さねばならないのですが、富岡の官営の製糸工場は厚待遇であり伝習工女もパイオニア的な指導者的地位があった。それと、日清戦争後の零細企業が多数を占める織物業の女工哀史は全く別のものだと言うことです。
これをごちゃまぜにし、模範工場の官営富岡製糸工場と零細織物業での女工哀史を結び付ける人が多いので混乱する訳です。
こう言う専門的な話題は本スレには投稿できないですね。
それはそうと、ネタバレにならない範囲で書くと、栄一の孫までがアラサーの俳優さんで演じられると言うことは大正時代末期も描かれると言うことです。栄一は昭和6年11月に亡くなりました。5.15事件で犬養首相暗殺の半年前で、既に6月には国粋主義の暴漢に浜口雄幸首相が昭和5年に襲われた後遺症で亡くなっています。
このスレは政治思想は断固お断りですが、平和への願いと言う一般的な観点で書くと迫りくるファシズムと軍国主義の前で栄一がどう対処したか、どう描かれるか見ものです。
私個人はある程度の創作があってもいいと思います(希望であって予想ではないのでローカルルールには反していないと思います)。
このスレに政治思想関係は一切お断りとローカルルールを作っておいて良かったです。
あまり、ここでの大絶賛投稿は絡まれたくないので本スレに投稿できなくなるかもしれませんね(^^;)。他スレの言及もローカルルールで禁止されておりますし。
追加です。
津田梅子は出ないけれど、大島優子さんらが鹿鳴館で洋装で踊る姿が見たいと思います。ダンスは得意でしょうし(^^;)。
270です、返信ありがとうございました。
大島優子さんが演じる伊藤兼子、注目ですけど、詳しく書くとネタバレになるし、ちょっと悲しいし😢
新キャストの大島優子さん以外の俳優さん、ほとんど知らない人ばかりで…
富岡製糸工場について、私も世界遺産になるまで誤解していました。
「花子とアン」の中でも(あれは大正時代ですね)妹が酷い工場から逃げて来たのが描かれてましたが、ああいうイメージを持っていました。(大正時代は蟹工船とかもあるし)
「青天を衝け」で初代工場長の尾高惇忠のことを知れて良かったです。
長くなってすみません。
昔「夜会の果て」というNHKのドラマを見たのを覚えているんですが、黒田清隆の正妻(後妻)役の黒木瞳さんが、複数の黒田の妾さんを月に一回屋敷に集めて、月々のお手当(生活費?)をそれぞれに渡すシーンが有りました。
黒木瞳さん演じる妻は夫に、結婚当初は「そんなことしたくない」と訴えますが、武勇伝でいっぱいの黒田清隆は「正妻の務めだ」と言って取り合ってくれません。
ここまでくると、家庭内のドロドロというより、従業員に給料を支給しているようで、ぶっ飛びました。
今日は今週初めて11時過ぎに介護タクシーが透析の迎えに来るまで時間があるので、ここに来ました。
そしたら朝から嬉しいじゃありませんか。273さんのご投稿がとても楽しい(⌒∇⌒)。
黒田清隆の後妻さんの話ですね。これも専門書で確認しましたが、黒田清隆は酒乱の気があり旗本の家柄の先妻を泥酔し斬殺した、とあります(色川大吉東京経済大学教授)。ウィキには含みを持たせ先妻は肺病で亡くなったとされたが新聞にすっぱ抜かれた、とあります。先妻の遺体の検査もぼかして書いてますね。榎本武揚の助命を剃髪して嘆願した侠気ある人物ですが、酒乱で民間人の死傷につながったこともある様々な騒動を起こした、と書かれているネット記事もありますね。司馬遼太郎は「燃えよ剣」で戊辰戦争の頃からこの気配があったことを書いてますが、司馬さんが上手いのは肥前藩や長州藩の新政府高官に酒乱をこっぴどくとっちめられる模様をユーモラスに書き読み手を楽しませているところです。
ただ、当時は伊藤博文の女癖の悪さにも定評があり、大河ドラマでは明治維新の英雄群像を多分に美化しているので、それを割引かないといけませんね。昭和の時代は専門書も幾つもあり比較しながら日本だけでなく欧米の様子も相当詳しく書けるのですが、明治ははあ、難しい。どうか、273さん、折に触れて、私にいろいろお教え下さればとても助かります。歴女でいらっしゃるのでしょうか(^▽^)/。
歴史がよくわからないのですが、明治時代が明るく楽しみになる大河ドラマですね。栄一の息子役の泉澤祐希さんは、吉沢亮さんより少し年上です。どんな家庭が描かれるのかも見逃せません。
続けます。私が富岡製糸場に見学に行った時に映画「赤い襷」という映画の撮影が行われていました。その映画を見てないのですが、渋沢栄一を豊原功補さんが演じています。
275=276さん、ご投稿ありがとうございます。
今、帰宅しました(^^;)。
「赤い襷」、予告編を見ましたが素晴らしい映画のようですね。
私の印象は「キューポラのある街」「若者たち」や朝ドラ「ひよっこ」の向島電機の女子工員の人々の世界ですね。世界に誇る伝習工女の世界です。これらは戦後の労働運動華やかなりし頃、昭和40年頃の働く熟練労働者の女性の世界を思わせます。
フランス流の進歩的な労働環境で一生懸命働く若い伝習工女の皆さん。
それが日清戦争後の産業革命による資本主義の発達に伴い民間零細企業が織物工業に携わるようになっていくと、官営富岡製糸工場の理想と誇りとは天と地ほどの開きもある劣悪な女工哀史の世界が広がっていく。この辺、「青天を衝け」の理想主義者の栄一がどう対応するのか楽しみにしたいと思います。何より道徳を経営に持ち込んだ元祖松下幸之助のような人ですから。
お返事ありがとうございます。そうですね、深谷にある渋沢栄一記念館に行ってみましたら、アンドロイドの渋沢栄一が「道徳経済合一性について」という講演をしていました。この発想がドラマで、どう描かれるのか楽しみです。
前回、官営富岡製糸工場で不正確な投稿をしたので、反省の意味で今回は大河はここのみの投稿・ロム専に致しますm(__)m。
資本主義の神様の栄一が母ゑいとの思い出で「皆が幸せにならなきゃいけない」と言うのはここで禁じられてる政治思想のマルクスとかとは全く無関係の論語の「寡(少)なきを患(憂)えずして均(等)しからざるを患(憂)う」と言う孔子の言葉だと思います。何せ「論語と算盤」で道徳と商いは両立すると説いたのが栄一ですから。
一方で、大隈重信への岩崎弥太郎のどす黒い笑み。司馬遼太郎の世界に親しんできた人は大久保利通の悪役に近い描かれ方と言い、驚いてる人もいるんじゃないでしょうか。弥太郎は土佐の地下浪人の出。武士とは名ばかりの足軽以下で豪農や豪商からも見下される貧しい身分からのし上がってきた叩き上げ。豪農出身で教育もある栄一の言うような「子曰く」の四書五経のきれいごとでは済まさない迫力を感じました。中村芝翫さん、役作りで太りましたか。この弥太郎の孫の沢田美喜が終戦直後にエリザベスサンダースホームを作ったクリスチャンの福祉事業家と言うのも面白いですけれど。
そうですね。やすさんも久しぶりで嬉しかったですが和久井映見さんと共に志尊淳さんも今回でオールアップみたいですね。
この時代、まだまだ男尊女卑で(「シャーロック・ホームズの冒険」の英国でもそうですね)、私は大島優子さんの登場を待ち望んでいます。
誤解があってはいけないので。
栄一の後妻役の大島優子さんの登場を待ち望んでいると言うのは、先妻の橋本愛さんの退場を望んでる訳では全くありません。ただ、封建時代を夫に尽くす妻としての描かれ方。鹿鳴館でバザーを催したりした大島優子さんの兼子の生き方も見てみたいなと思っただけです。
三野村利左衛門はナレ死だったが、小栗忠順の遺児の面倒を見る好々爺の一面もあり、人間は一面的に判断してはいけないと感じる栄一が印象的でしたね。
井伊直弼大老の暗殺が大河屈指の名場面だったのに、西郷隆盛の自刃、大久保利通の暗殺はそっけなかったですね。江藤新平に至ってはスルー。西郷は生前の栄一との思い出が回想で出た分ましでしたが。また、私の偏見になってしまうかもしれないのですが税収と西南戦争での出費を比べ、戊辰戦争にも加わらなかった栄一は権力争いより国の財政を建て直すのが先決と言う感じですね。私は彰義隊の戦をよそに米国の経済学者ウェーランドの原書講読を塾生としていた福沢諭吉の先見の明に通じるものがあると思います。この点、司馬遼太郎ファンの多くは剣に生き剣に死んだ人々を讃えて私とは考えが異なりますが、フランスのパリコミューンを見ても近代国家に至るには流血は避けられないのかもしれません。英国も世界各地で戦争を繰り広げていた訳ですし。
ハンティングウェアで狩猟から帰ってきた慶喜。亡き平岡円四郎の妻のやすの困窮する元幕臣に対する美賀君への叫び。
論語は今日から見れば慈悲深い君主の家父長的な恩恵思想で、清朝の戊戌変法の康有為等が四書五経に通じ改革を行おうとし西太后に潰されますが、後の大正デモクラシーと言う西洋流の民主的な考えに近い流れに栄一がどう反応するか見届けたいと思います。貧しさからの脱却は儒教政治だけでは救えません。
今日も本スレには投稿しません。
イッセー尾形さんの圧倒的な名演回でした。
土下座する小野善右衛門、「半沢直樹」を彷彿とさせる演出ですね。
ナレ死、新聞記事死、台詞死で、要人たちが次々退場で時代の転換点を感じました。
草彅剛さんは断髪とおしゃれな洋装で、もはや慶喜じゃなくてフツーに草彅くんでしたね😅
やすも登場しました、栄一が慶喜に政財界の話を仕掛けても、(わざと)関心を示さず、趣味人としてのみ生きる慶喜は、明治の世になっても苦しい立場なんですね。
「勝海舟が静岡に届まるように進言した」と告げる変わらない忠臣の猪飼勝三郎も洋髪になっていました。
(猪飼役の遠山俊也さんは「白杖ガール」では誠実な対応をしてくれるスーパーの店長さんでした、栄一や喜作が一橋家に仕えた時も親切にしてくれたのを思い出しました、「エール」や「ひよっこ」「モネ」にも出演のおなじみ俳優さんだったんですね)
282さん、ご投稿ありがとうございます。
イッセー尾形さん、いい俳優さんですね。「意地悪婆さん」に交番の巡査役で出て「ばっちゃん(青島幸男の意地悪婆さん)」を少し訛りのある言葉で話していました。「スカーレット」の陶器の絵師では「ええよお~」が記憶に残っています。この人の役は記憶に残りやすい感じです。
小野善右衛門の小倉久寛さん、映画「夢見通りの人々」では南果歩さん相手に気弱な小市民役。「翔ぶがごとく」では伊藤博文役でしたが、今回のような庶民的な役柄がよく似合ってると私個人は思います。
慶喜は一見、趣味人で優雅そうですが、田安亀之助こと十六代様と言われた徳川宗家の徳川家達の管轄におかれ、公爵として華族になったのは明治35年ですからね。でも、ウィキで見たら司馬遼太郎が言うほど冷遇されておらず明治21年には従一位にも50過ぎでなっていますね。でも、天領400万石から駿府70万石余にされ、家臣は窮乏したのは想像に難くありません。
遠山俊也さんは個人的には「ひよっこ」以降、結構重要な脇役が増えた気がするのですが。
来週から、ネタバレで書けませんが大物俳優女優が出てくるようですね。楽しみです。
栄一に対峙する岩崎弥太郎が好対照に描かれていました。
西南戦争はともかく台湾出兵で余計な戦費で財政を悪化させた、と嘆く栄一に対して、兵員の輸送費で儲かったと喜ぶ死の商人さながらの弥太郎。
宴席でも大衆の小口投資家の富を結集し国を強くすると言う現在の資本主義制度に近いことを言う栄一に対し、才覚ある者に富を集中させ儲けさせることこそが肝要と言う弥太郎。
これだけなら清廉潔白の栄一に対し私利私欲の腹黒い弥太郎と言う構図ですが、私は両者の生育環境が全く違ってた事も原因かと思います。郷士だと弥太郎は大笑いしてましたが郷士や豪農からも中間のような武家奉公人からも蔑まれていた地下浪人が岩崎弥太郎の出自です(郷士の地位を売って金にした家柄が正確)。吉田東洋に聡明さを見込まれ探索等の役を下横眼として命じられた家柄で「龍馬伝」では香川照之さんが貧しさを強調するため泥水で顔を洗ったと言うエピがあります。
一方の栄一は豪農の出で四書五経に通じ漢詩を読むくらいの教養人です。パリで西欧の進んだ考えにも接しています。
この辺の違いもあるかなと個人的には思うのですが。
大島優子さんが伊藤兼子役で出てきましたね。「妾はお断り」と言うので同じ大森美香さん脚本の「あさが来た」の三味線師匠の美和を思い出してしまいました。
やすさんは夫を亡くしても元気に振る舞っていますね。気丈な人で江戸っ子言葉が心地よいです。
鹿鳴館はグラント将軍の来日以降にできたもので、不平等条約撤廃のために舞踏会の真似事までするみたいですね。
本スレには当分投稿しないと思います。
千代の橋本愛さんが【35歳の少女】等で好きな女優でしたが、どんどん美しくなり今回の養護院でしょうか?の場面の裁縫を教える所や、女の子に泣きたいとき泣いて良いのです。と言う場面、良かったです。
お前様 と栄一を呼ぶ言い方等も。
妻妾同居等すべてを飲み込んでの良妻賢母は何処か哀しげです。それが大人の女性になったと言うことでしょうか?彼女の内面の苦悩をよそにたおやかな佇まい。首から肩のラインがとても綺麗なので和服や日本髪が似合ってます。
書生達をビシッと叱る所等も、キリッとして良かったです。
でもあの書生達、あまりに思慮浅く何だか知的な感じしなくて誰でも渋沢家の書生になれるのかなあ?と思ってしまいました。
余談ですが、橋本愛さんを初めて見た【あまちゃん】ヒロインの、のんさんにもドラマ出て欲しいです。
私も橋本愛さんは、あまちゃんの時の女子高生役から成長したなぁって思って見てます。いだてんに続いて、このドラマでも、キッチリ役にハマってるのを感じて応援してます。
養護院のような施設の世話係の怖い感じのおばさんは、何と【おちょやん】のかめさん役の女優さんでした❗
鳩さん、お大事に。
大阪朝ドラ常連の楠見薫さんですね、「のほほんふたり暮らし」にも出演するそうで楽しみ。
橋本愛さんの千代はいつも謙虚で綺麗です。
今週も書生さんを一喝したり、擁護院で子供たちの世話をしたり、凛々しくて優しい千代に見惚れました、でも妾さんと一緒に縫い物をしながら笑っているところもあり複雑。
橋本愛さんの登場場面をもっと長く見ていたかったです。
しかし今回の見せ場は渋沢栄一とはずーっと対立していたという岩崎弥太郎がメインなんですね。
私、歌舞伎役者に詳しくないので、歌舞伎俳優は演技がやっぱり独特で上手いなと思いながらぼーと見ていたのですが、あの弥太郎役の中村芝翫って、三田寛子さん旦那だった❗️ことにしばらく気が付きませんでした。
岩崎弥太郎を演じるのに体重を増やしたそうです、さすがですね、弥太郎の肖像画にそっくりで成りきってましたね。
大河の主役をやったり、「御宿かわせみ」など若い頃のイメージと変わってしまってた。
はあ、今日は一日、病院で潰れたよ。と自分語りはここまで。
皆さん、遅い時間に登場で申し訳ありませんm(__)m。
285=287さん、286さん、ご投稿ありがとうございます。
そうですね。橋本愛さん、私個人は大人の女性の魅力が出てきた感じがするんですね。「あまちゃん」で初めて知りましたが「35歳の少女」での俺たちの菅沼じゃなかった坂口健太郎さんとの掛け合いとかコミカルな役から「西郷どん」での笑わない能面の西郷の最初の妻、「いだてん」の銘酒屋の女、そして今回は封建道徳の下で健気に生きる豪農と言うより武家のしっかり者の奥方様。
渋沢家の書生、確かに「警察に通報じゃ」って電話も普及していない時代に言うよりは剣術なり柔術くらい心得ておいて欲しいのもですね。栄一は若い頃、剣術に入れ込んでいました。桂小五郎(木戸孝允)、坂本龍馬は剣術にも秀でてました。この時代、シャーロック・ホームズはボクシングの他に講道館柔道を心得ていました(架空の話ですが)。
のんさん、トータス松本さんや上野樹里さんと同郷の播州人なので、個人的には大阪朝ドラで関西弁を披露してもらいたいです。大河ももちろん出て欲しいですね。
そう言えば、楠見薫さん、出ていましたね。大阪朝ドラ専属かと思いきや東京制作の大河にも出てくれるのは嬉しいですね。
ええ、元気にやっていきますよ。皆さんの感想を支えに気力に変えていってます(⌒∇⌒)。今後ともよろしくお願いいたします。
田辺誠一さんがナビゲーターをしている『にっぽん歴史鑑定』で「渋沢栄一の従兄弟尾高惇忠と冨岡製糸工場」があったので見たかったのですが、見られませんでした、残念😮💨
「備前堀事件」という水路計画が有った時、惇忠が訴えた説が理路整然として優秀さが認められ、まず惇忠は新政府に登用された、そこで、先に官吏となっていた渋沢栄一が自らが任されていた製糸工場の建設を、養蚕に詳しく通じていた惇忠に一任した、と解説にありました。
ドラマのクランクアップ映像で白髪の吉沢亮さんを見て晩年までやるのだと思いました。お疲れ様と思うと同時に、深谷の渋沢栄一記念館にあった葬儀の時の写真で、車の列の多さを思い出しました。
290さん、291さん、ご投稿ありがとうございます。
『にっぽん歴史鑑定』「渋沢栄一の従兄弟尾高惇忠と冨岡製糸工場」は11月1日のものですね。これは私も見たかったですね。「青天を衝け」では西欧の先進国だったフランス人の女性技師の指導が描かれていましたが、教えて頂いた回は官営富岡製糸工場は超ホワイト企業だった、と紹介されていますね。昼休みが4時間、福利厚生も充実なんですか。これは私の持ってる専門書にも多分ないでしょう(「麒麟がくる」足利義輝暗殺も簡単に一行で済まされている)。
司馬遼太郎さんは明治期のこれらの業績を誇り、従軍した太平洋戦争末期を顧みて「いつから日本はこんな国になってしまったんだろう」と嘆いてますが(戦争への反対で政治思想的なものではありません)、日清戦争後から零細紡績業で女工哀史の世界になったのを渋沢はどう見ていたか「青天を衝け」がどう描くか興味あります。
「備前渠取入口事件」は尾高惇忠は明治政府がやろうとした変更計画に地元農民と共に反対し尽力したそうですね。民百姓あっての政治と言う点で、栄一にも徳川慶喜にも通じている気がします。
栄一が亡くなる昭和6年まで放送すると菓子浩制作統括は語っていますね。前年に浜口雄幸首相暗殺未遂事件が起き、栄一の旅立つ直前に闘病の末に亡くなっています。翌年5月には「いだてん」で詳細に描かれたように犬養毅首相暗殺事件が起きています。
日増しにきな臭くなっていく世相に栄一はどのような思いを持っていたのでしょうか。このスレでは政治思想的なコメントはご法度ですが、大久保利通らに栄一は無駄な出費だと戦費支出を反対し、兵員輸送料金で儲かったと言う政商の岩崎弥太郎と対立します。
栄一がファシズムの足音が近づいてくる時代の波をどう見ていたか、も見ていきたいと思いますね。
グラント将軍の歓迎式典と岩崎弥太郎の野望、自由民権運動の高まり等、盛りだくさんでしたね。
明治12年(1879年)ですね。この頃のパリのモンマルトルの丘のカフェでの「ムーランド・ラ・ギャレット」と言う富裕層の庶民のパーテイーを描いたルノワールの絵画、ベルリンのウィルヘルム1世の宮廷舞踏会のアドルフ・メンツェルの絵画を見ると非常に豪勢で、栄一らのもてなしはまだ貧しかった日本が精一杯の金を掛けての接待だったと思います。もっとも、米国も当時は英国やフランスに遅れた国だったので、十分満足したと個人的には思います。岩倉具視とは1872年の訪米時に面会していたのですね。
井上馨の後の鹿鳴館政策につながる露骨な欧化政策がこの頃からあったんですね。でも、現代的な驚くべき進歩的な発言が接待する女性の側からありましたね。ハイヒールやコルセットを「(欧米でも)男性は女性を飾り物として見ているのが分かりますわ」。実話でしょうか。江戸時代を生きてきた女性が言うのは想像しづらいですが。明治末期や大正時代なら分からないでもありませんが。
橋本愛さんも英語ができるようになっていたんですか。これはありえますね。
伊藤博文が「井上馨や福地源一郎は喜んでるが英国、フランス等は冷ややかに見ている」と言うのも欧化政策批判のようでかなり先見性ある発言ですね。
これ、一つ一つ調べるのは大変なので(昭和史に比べて)、ドラマとしてはよし、としたいです。
北海道や台湾は農業に向かない土地でした。先住民のアイヌの人々や高砂族は狩猟民族です。はて、岩崎弥太郎が北海道開拓に尽力したのか、見ていきたいですね。「獅子の時代」では過酷な囚人労働があったような。屯田兵とか客土とかコメの品種改良とか、これは残りの回数では描き切れません。
先週申し上げた通り、本スレは見ないし投稿もしません。
千代をはじめ、奥様がたのおもてなしが華やかで楽しかったです。
井上武子役の女優さん、華麗なドレスで軽やかなダンスを披露していると思ったら、元宝塚スターの人なのですね。
よしがグラント将軍を見て「穏やかそうな小柄なおじいさん」と言ってました。
「南北戦争の英雄のグラントさんて小柄だったの?」と疑問だったので調べてみたんですが、実際は182、3cmの身長が有ったみたいですよ。
グラントは大統領の任期を終えた後、ジュリア夫人と息子(たぶん)のジェシーと一緒に世界旅行に出て、来日した時は50代後半、当時なら「おじいさん」の年齢だったのかも知れません。
日本に来る前はシンガポールや清も訪問し親善だけでなく国際政治アドバイザーみたいな役割を果たしていたようです、栄一達にも欧米の商人がアジア人にどう対応しようとしているか伝えていました。
岩倉具視邸に招待された時は(岩倉さんとはグラントが大統領就任中にアメリカですでに会っていたんですね)能や狂言を鑑賞し、賞賛して、能の復興に取り組んでいた岩倉具視に「このような芸術は廃れやすいので、大事に保存して」と後押ししたそうです。
294さん、ご投稿ありがとうございます。
いろいろお教え頂いて、とても助かりました(⌒∇⌒)。
愛希(まなき)れいかさん、元月組トップの娘役の方ですね。ダンスは得意でしょうね。バレエや日舞の授業も宝塚音楽学校であるみたいですし。
グラント将軍役の方が小柄なのは演出的な面もあるのかな。栄一を見下ろすような長身の白人の方を配役にすると、マッカーサー元帥と昭和天皇のツーショットのようになり、体格的に劣る日本人が見栄えせず当時の内閣情報局は発行禁止処分にしたものの、GHQが取り消し命令を出した例がありますからね。
そうでしたか。能楽を見て称賛されていたのですね。ラフカディオハーンのことを思いますね。日本文化は私個人は世界中の人を魅了するものがあると思います。侘び寂び、なんか、とても素敵な文化ですね。
放送回数が残り少ないのは本当に残念です。
冒頭の華やかな奥方達のガールズトークにはびっくりしました。
でも、千代達が地味な着物でも、華やかな奥方達に負けてない、臆する事なくでした。
とにかく橋本愛さんの顎から首から肩のラインの着物姿が美しい。堅実な落ち着いた所作。
橋本さん達の年代の綺羅星の如くの女優さんの中でも群を抜く品と完成された大人の女性を演じていますね。35歳の少女の突っ張りな妹役から注目してましたが、とても好きになってしまいました。
時代劇、大河、時代小説が好きなので、ドラマや映画も沢山みたけれど、昨今の若い綺麗な女優さんの話し方は現代のドラマだと良いのですが、時代ものの格式ある地位の女性を演じる時、いつも僭越ながら思うのです。
もっと日本語本来の抑揚や母音の美しさを台詞や所作で体現して欲しいと。
橋本さんは、だから好きです。
途中迄視聴ですが、
今回のメインイベント は。
おもてなしジャパンかしら?
ポトフ食べたくなりました❗
レガシーさん、ご投稿ありがとうございます。
橋本愛さん、「あまちゃん」当時と比べて、艶っぽくなり大人の女性の魅力満載ですね。「青天を衝け」では今では豪農の農婦と言うより旗本の奥方様がぴったりで「35歳の少女」でのはっちゃけた癖のある妹とは全く違います。レガシーさんの女性ならではの所作への味のあるコメントに頷いている次第です(⌒∇⌒)。
私個人の記憶では「大岡越前」の宇都宮雅代さんの言葉遣いが旗本の奥方様っぽくて良かったです。古いところでは「東京物語」原節子と香川京子。
実は私も最近洋風スープに凝っていて、ポトフとかミネストローネをレトルトで買って食べています(^▽^)/。
千代が遠い国に旅立ちました。
血洗島村から、栄一に告白されて、舅と姑によく仕え、栄一を支え気丈に振る舞い、豪農の嫁から最後は旗本の奥方様のように毅然として去っていきました。
大森美香さんは「あさが来た」でも感じたのですが、臨終の愁嘆場を長く見せるところがありますね。「青天を衝け」も栄一の両親がそうでした。
私個人は朝ドラだと「マッサン」のラストや「エール」のラスト(最終回の歌唱大会除く)のように夢の中で若い頃に戻り夫婦で駆けまわりながら実際は静かに息を引き取る描写が感慨深いですが。これは私自身が病身だから、そして亡き父の最期を看取った体験から感じることです。人それぞれです。
一つ歴史観の違いですが、薩長藩閥政権を大久保利通らへの批判で貫いてきたのに、鹿鳴館政策と同時に汚職の御大の井上馨や栄一より遥かに女癖の悪かった伊藤博文の美化が始まってきたか、と思われるところです。慶喜は農人形に飯をよそい、民百姓に感謝して食事することを平岡円四郎に教えました。はて、あの頃と作風が変わってきたかな。
まあ、司馬遼太郎も井伊直弼を稀有の大悪人としていますし、新選組は非常に美化しています。史実ではない、と割り切って「青天を衝け」を楽しめばいいかと思います。
今夜、BSプレミアム「英雄たちの選択」が明治中期以降の渋沢栄一の貧民救済政策を中野信子さん(脳科学者)、鹿島茂さん(フランス文学者)、飯田泰之さん(経済学者)、磯田道史さん(歴史学者)らで振り返る内容の再々放送をやっていた。
前回の「青天を衝け」は長州の藩閥政治家の伊藤博文と井上馨に尻尾を振っていたかにも見えた渋沢だが、このドキュメンタリー番組で東京府議会と対立してまで、慈善事業として貧民救済に「論語と算盤」に代表される道徳心を持って挑んでいる話であった。それは亡くなる昭和6年まで大蔵大臣に直談判するまで続いたそうです。
これです、これ。私が「青天を衝け」で見たかったのは。
井上馨の推進した鹿鳴館政策に便乗し、鹿鳴館でバザーを催し莫大な利益を上げ惜しげもなく貧困層への救済に当てた渋沢。
欧米のキリスト教文化が乏しい日本では渋沢は富裕層の虚栄心を逆手に取って、泥棒カバンと言われた大きなカバンを持って財界人にチャリティーへの参加を求めて歩いたそうです。三井財閥当主や大倉喜八郎が応じた記録が残っています。
「あさが来た」はお金持ちの広岡浅子をモデルにしていましたが炭鉱夫の生活に密着する等のヒロインも描いていました。
「青天を衝け」も社会事業や女子教育にも尽力した渋沢栄一の魅力を描いてもらえればいいな、と個人的には思っています。
橋本愛さんの千代はいつも素敵な佇まいで栄一の理想の奥様で、毎回美しさ優しさに見惚れてしまいました。彼女も栄一と共に長生きして欲しかった。
「仁jin」でも幕末にコレラが流行する場面が有りましたが、明治になってもまだまだ治療しきれない病だったんですね、衛生状態も悪かったのでしょうし「点滴」とかないとダメですね。
それにしても「伊達様」のまさか再登場には意外でびっくりでした。
お殿様姿ではなくダンディな明治紳士の菅原大吉さんでした、華族様ですかね?
うたさんの縁談のお世話⁈
しかも洋行帰りの好青年の良いお婿さんを紹介して良かったですね。
「くにさん」が渋沢家の子供達も居る家族団らんの場にさえ毎度参加しているのがやはり気になってしまいます。
先週などは賓客のグラント夫人の料理を渋沢家の女性たちと一緒に習っていて「遠慮した方がいいんじゃ」と思ってしまいました(ちなみにグラント将軍は奥さん一筋だったそうです)
現代の価値観に当てはめるのおかしいとはわかっているし、くにさんを嫌っているわけではないんですけど、千代を失って嘆き悲しむ栄一を見てもなんだかモヤモヤしてしまいます。
スポンサーリンク