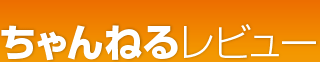先日 描かれたのが 1964年
1965年 将軍義輝 暗殺 光秀38歳
光秀 越前から去る
1966年 光秀 足利義昭に仕える 光秀39歳
本当に長い雌伏時代です
私の好きな黒田如水は43歳で黒田長政に家督を譲ります。信長も41歳で信忠に家督を継がせます。
それに対して 光秀は 42歳で長男・明智十五郎(光慶)が誕生
当時としては 20年 人生の歩みが遅い。 光秀を考える時、彼の残された時間を常に意識する必要がありますね。 焦りです。 光秀を考える時、終点として 本能寺の変があり 何故そこに至ったかで彼を捉えてしまうのですが、人間50年の時代に20年遅れてきた人という視点で彼を見れば別の面が見えるかも。
凞子が十五郎を産んだのは39歳か35歳。当時としてはかなりの高齢出産です。
光秀の人生って 常識外れ で面白い。
朝倉義景 も 妖怪 として描かれていましたね。
ドラマ内の話ですが、光秀の人選は 将軍、藤孝、松永久秀 などとの交遊関係から 京 の動静を探るのには適しているし、「家族のことは心配するな」 という言葉は、光秀の反応から、「家族を人質に取るから余計な事はするな 言われた事を忠実にやれ」 という脅迫です。
そしてアップになった光秀の髪に白髪が一本。雌伏時代が長すぎた、光秀がもう若くない とさりげなく悟らせるやり方。 上手い と思いました。
村角灯さん、コメントありがとうございます。
年配の人ほど、また「翔ぶがごとく」に触れた「西郷どん」のコメント等、司馬遼太郎と「国盗り物語」の影響を受けた60代以上の人ほど、近藤正臣さんが演じた明智光秀のイメージが強烈で光秀は既に相当の年齢だった、と言う村角灯さんのご指摘にハッとさせられた人も多かったのではないでしょうか。私もそうです。
白髪のヘアメイクに気づく等、素晴らしい観察力ですね。
ユースケサンタマリアさんの朝倉義景もそういう伏線があったとは。思わず読んでいて唸りました。
先におっしゃっていた朝廷陰謀説も近衛前久に続いて正親町天皇もでてくるので、まだ分からないですよ。比叡山延暦寺とは密接な関係らしいですし(弟が天台宗座主でやはり登場する)。
私はもっぱら、いい人の足利義昭がユニークで、そちらに気を取られてました。
これからも思う存分、健筆をふるって下さい。楽しみにしています。
今日は「麒麟がくる」放送の日ですね♪
私個人は先週から俄然面白くなりました。「国盗り物語」司馬遼太郎史観の二番煎じでない新たな視点だったからです。
考えてみれば、脚本家の池端俊作さんは「太平記」でもあの戦前、神のように崇められた忠臣の楠木正成を武田鉄矢さんを使って、ひょうきんな話し合いで民主的な解決を模索する平和主義者として描きましたからね。金八版楠木正成です。吉川英治の原作にもない描写でした。
「麒麟がくる」もどんな新解釈で来るか、楽しみです。
本日の『麒麟がくる』台風10号関連のニュースの為放送休止だそうですよ
453さん、貴重な情報をありがとうございます。
番組公式HP見たら、本当に「本日の放送はお休みにします」の文字が。わあ~、楽しみにしていたのに(涙)。
>>449 光秀20年遅く来た男 に関して 別の観点で書いてみます。
光秀 42歳で 長男 誕生。
その時、妻のひろこは何歳ですかあったかというと39歳 あるいは37歳説が有力です。
そして問題は、長男に続いて 次男、三男 と産んでいる事。 ひろこさん おそらく40歳を超えて出産を続けていたことになります。
医療 未発達の時代、人間50年と謳われはするものの当時の平均寿命は40歳に届かない。
ひろこさんの出産は極めて不自然に映ります。
おそらく、光秀がひろこさんの生前は側室を持たなかったというのは嘘じゃないかと思いますがどうでしょうか?
村角灯さん、コメントありがとうございます。
私個人はこの時代に十分あることだと思います。
豊臣秀頼の父親は秀吉ではない、と言う描写は「利家とまつ」でもありました。司馬遼太郎も同意見です。
昭和戦後でも私の幼少期にご近所でお姉さんの生んだ赤ちゃんを子宝に恵まれない妹が出生届けを自分の子として出していました。母子健康手帳の整備されていない昭和戦前ではよくあったそうです。
ただ、この時代の平均寿命の低いのは乳児死亡率が非常に高かったからで、江戸時代に入っても成人したら60代まで生きる人は多かったそうですから、熙子が生んだ可能性も排除できないとは思います。
歴史は謎のままですね。
今日は通院のため、返事が夕刻以降になります。
今日も、いい人の足利義昭(滝藤賢一さん)が登場みたいですね。
一方、向井理さん演じる足利義輝には身の危険が迫ってるようです。ここは史実通りにやるんでしょう。まさか「北条時宗」のように北条時輔が実は生きていて元に行ってフビライ汗と出会う、とかはないですよね。
今日はBSで先に見ましたが、地上波のみの人にはネタバレになり先入観を植え付けるので、地上波の放送が終わってから感想書きますね。私の場合は「国盗り物語」との比較も入るのはご容赦下さい。
他の皆さんも地上波の放送後に今日の内容へのファンとしての感想をお書き下さいますよう、スレ主として、お願い申し上げます。
早朝とは言え、足利将軍の義輝が「誰か(おらぬか)」と声を出しても二条御所は静まり返っている。孤独と言うより孤立。
一方の覚慶上人(足利義昭)の元には細川藤孝と一色藤長が警護のために駆けつける。「将軍の警護は?」と問う覚慶に藤孝が「三渕(藤英)がおりまする」と答えるが、これが半ば大嘘なのが後で分かる。光秀が信長の代理の木下藤吉郎(羽柴秀吉)から将軍謀殺計画の話を聞き、松永久秀に足利義輝の保護を求めに行くと細川藤孝が控えており義輝に愛想をつかしたことが分かる。久秀も義輝を殺さぬ代わり追放するよう息子らに言い含めてるから安心しろ、と言う。壺を例に美しいことは美しいが力なく脆い存在だ、と示唆する。
最後は三好善継が二条御所を襲う場面。
「国盗り物語」と比べ、やはり足利義昭はいい人だ。「今の自分は周囲の人に施しをできるだけの存在に過ぎない」と情けなさそうに駒に語る。襲われた時に駒を連れて逃げるが動作も機敏で、愚鈍な印象の強かった伊丹十三の「国盗り物語」の義昭とは違う。駒の芸人との踊りを人の好さそうな表情で楽しそうに見る等、善良な人柄の良い人物だと言う印象が「麒麟がくる」の義昭だ。
細川藤孝が「麒麟がくる」ではいささか腹黒い。表では義輝に忠誠を誓いながら久秀に接近し将軍追放に加担しようとしている。「国盗り物語」では竹脇無我の義輝はここまで人望のない男ではなかった。あと、義輝のどのような面が人心をつかめないかが分かりにくい。ウィキではここまで孤立した人物には描かれてない。残念なことに林屋辰三郎京大名誉教授ら学者の著書は永禄の変は一行程度の記述である。曲がりなりにも将軍の権威があったのは9代義尚まで、と言う書物が多い。
二条御所の襲撃も「国盗り物語」は夜襲だが「麒麟がくる」は白昼堂々と。学者の本だと白昼堂々とで「麒麟がくる」が近い。
興味深い記述が林屋辰三郎氏にある。畿内で一番力があったのは三好善継でも松永久秀でもなく大坂の石山本願寺だった、と言うもの。神聖ローマ帝国の大空位時代のようなものか。
幕府の力がこれでは覚慶上人が善良な人物でも誰がやっても駄目だろう。江戸幕末の水戸藩の幕政改革運動とは比べようもない。
ところで、菊丸は岡村隆史さんの舌禍事件でフェイドアウトなのか。今日は帰蝶もいなかった。なお、斎藤義龍は既に若くして亡くなっている。
今日の物語は1565年の事ですが、人物関係の前提を知っている方が楽しめるので情報提供。
足利義輝30歳、足利義昭29歳で1歳違いの兄弟。その母親は、近衛前久の叔母。
足利義昭は、興福寺一乗院の門跡で、興福寺は言わずと知れた、藤原氏の氏寺。
足利義輝の正室は、近衛前久の兄妹。
2重、3重に 貴族、仏門、武家の間で縁戚ネットワークが作られています。
ところが、義輝が殺害され、その葬儀が行われても公家は誰も参加しない。前久さえも。それどころか、すぐに義栄の将軍宣下の準備にかかる。
孤独な将軍ですね。 義輝は、松永久通と三人衆が襲撃してくることは事前にわかっていて、逃げる事もできたのに、あえて1万の軍勢に数百で戦う事を選んだ。逃げる事も可能だったのにあえて戦う道を選んだ信忠とよく似ています。
村角灯さん、貴重な情報ありがとうございます。
葬儀に公家が参加しないのは足利将軍家が無力だからか、今日の「麒麟がくる」のように将軍が義輝だからか、どちらなんでしょうか。本当に学者の一般向けの本は冷淡な短い記述で困ります。
最後の記述で剣豪将軍の名にふさわしい人物だったのだな、と思いました。「国盗り物語」の竹脇無我は返り血を浴びながらも笑みさえ浮かべ敵と斬り合っていました。「麒麟がくる」は予告編で四方から障子を楯にされていたみたいで孤独な死に方を強調してるようでした(「国盗り物語」は斬り合ってるところで終わりナレ死でした)。
「国盗り物語」では足利義輝の忠臣だった細川藤孝を「麒麟がくる」は裏で松永久秀と通じて将軍追放を画策する人物と描くなら、光秀は次女のたまを藤孝の息子の忠興に嫁がせて本能寺の変で援軍を期待するのがそもそもおかしいと言うことになる。面従腹背の男で人形佐七捕物帳(これは創作だが)の主題歌のような「義理と人情の男前」とはかけ離れた人物。
司馬遼太郎は石田三成や新選組のような忠義一途の阿呆のような人物は好意的に描き、日和見主義の人物には手厳しかった。
この辺を今後どう描くのか、興味あるところである。
460でスレ主さんも書いていらっしゃるように、足利義輝がなぜこれほど人望が無いのかが疑問ですね。
余程無能なのかあるいはひどく嫌な奴なのか。
これが半沢直樹に出演している敵側の俳優が憎々しげに毒々しく演じているというのなら、こんな人の下で働くのは嫌だな、と共感も出来るが、なにしろ演じているのが向井理さんである。
今までの登場シーンを観ても理知的で思慮深く外見もシュッとしている(!)。
話の流れとしては義輝の事を“不運な人”として描いているように見える。だったらその“不運”をちゃんと見せてくれないと。
十兵衛は京から離れた越前に住んでいるので、義輝の実態を知らないから、いまだに義輝の事を慕っているという事なのだろうか?近くにいたら、こんな人の部下なんてやってられないよ、という事なのだろうか?
将軍義輝は、戦国ドラマでもあまり扱われない人物だそうですが、当時の状況があまりに入り乱れていて、描くのが難しいというのも理由なんでしょうか。義輝は将軍というは名ばかりで、京都は三好長慶の支配下にあり、将軍側と三好側との間で小競り合いが続いていたのが現状らしいです。義輝は京都を逃れて近江に御所を移していた時期もあるので、よくよく権力的には無能だったんでしょうね。そこのところがあまり詳述されていないので、「麒麟がくる」では義輝像が少々、表層的になってしまうのでしょう。時間が足りないせいもあるのでしょうが、そこは少し不満な所です。
将軍に武芸が必要か? という事でしょうか。
義輝は11歳で将軍になり 30歳で暗殺されます。
年代から考えて、光秀が最初に将軍に会ったのは義輝がまだ15歳に達しない時期です。
この15歳くらいの時に義輝は最初の三好長慶暗殺を企てます。 そして晩年も、光秀に刺客依頼したように、暗殺くらいしか手が無いほど力を削がれていた。
怒涛の歴史の流れを堰き止めようとしたが、世の中は既に足利幕府を必要としなかった。という事でしょう。
強い血縁を持つ近衛前久など朝廷との関係も良くなかったと言われています。20年間の将軍在位中に5回しか参内していないそうです。
1560年 桶狭間の年ですが、近衛前久は越後に下向して長尾景虎の上杉氏の継承及び関東管領就任に尽力しています。 上杉氏は藤原北家と先祖を共通にする近衛家の同族です。
義輝は強い血縁でありながら、朝廷を軽視した。朝廷の方も近衛前久の行動にあらわれるように義輝に期待していなかった。
義輝は将軍親政を目指したが、そのやり方が政治的で無かったのだと思います。剣は強くてもあくまで個人の事、政治力が無いのは致命的だったのかと。
もう一つの原因は 後ろ盾になる六角氏の弱体化です。
今から通院の準備をしますので、返事は夕刻以降までできません。
何卒、ご了解下さい。
私は気づくことができなかったのですが、義輝の孤独のシーンで甲冑が映り、それが足利将軍家の家宝である、足利尊氏の鎧 「御小袖」 であるとのコメントを某所で見ました。
将軍家に災いが発生する時、この鎧が鳴動すると言われていて、義輝は、それを無視したから三好一党に殺害されたという言い伝えもあるようです。
来週、もしかしたら 「御小袖」が鳴動するシーンがあるかも。
史実としては、義輝が力も無いのに将軍親政を強行する為、この時点で既に 義輝--三好、義輝--朝廷 のラインは共に冷え切っていて、三好一党は 義輝の退位と三好が担ぐ義栄への将軍職禅譲を義輝に要求している状況だったようです。
藤孝は細川家の立場を乗っ取った三好とは組めないので、義栄擁立には参加できず、義昭擁立に向かうという事のようです。
藤孝は策士です。 本能寺の後に光秀への協力を断った事が有名ですが、もう一つ意味がありました。 丹後の細川藤孝を警戒するために、光秀は丹波に残していた丹波衆を藤孝の警戒の為に動かす事が出来なかったのです。その結果、山崎の合戦で兵力差が大きくなったという面もあったようです。そして、本能寺後、藤孝は、近畿の情勢をセッセと秀吉に知らせ、天王山後を画策しています。 クレバーな奴ですが、私は割と好きですね。
そして、ドラマでは隠れて出てこないのですが、義輝の政堂の中心にいて失脚した伊勢氏。 本能寺の変で光秀軍の中核的位置にいました。この後、摂津春門が登場するようですが、摂津氏⇔伊勢氏 のバトルもこの頃の歴史の大きな要素のようです。
やはり、戦国時代の歴史は楽しいです。
村角灯さん、おはようございます。
いつもながらの鋭いコメント、素晴らしいです。
学者の一般向けの本にはここまで載ってなくて「国盗り物語」頼りですが、義輝が殺されたのを夜襲としてますが他の文献では白昼堂々と、とあり、司馬遼太郎は創作を史実のように見せかけて臨場感あふれる描写で読者を魅了する術の作家なので、物語としては面白いですが史料にはならないですね。
唯一、疑問は光秀は、この細川藤孝の息子に次女のたまを嫁がせますかね。私が光秀なら油断ならない相手で戦略的互恵関係に過ぎず、司馬作品でなら「関ケ原」の石田三成や大谷吉継、「燃えよ剣」の松平容保(会津藩主)・定敬(桑名藩主)兄弟のように忠義一途の人物を選びますね。
465です。本スレよりこちらの方が本格的な内容で興味深い。
ただ本スレのほうは時々は投稿するのですが、
こちらはレベルが高くて、なかなか勇気が出ないです。
でも時々寄らせてもらいますね。
お蔭様で、これまで余り関心のなかった日本史に
興味がわいてきました。
スレ主様
このスレを時々読ませていただいております。中傷には負けないでください。
471さん、472さん、コメントありがとうございます。
471さん、吉法師さんが多忙で抜けられ、一文字三郎直虎さんも病気療養中ですので、本来ならもっと凄いメンバーですが、おっしゃるように普通のドラマの感想が書きづらい、と言う方々が過去にいらっしゃいました。そのために「自称うなずき人間(「オレたちひょうきん族」の漫才コンビのボケの側の愛称。相方にひたすら、うなずき「そんなアホな」「よしなさいって」と言う)」の私がおります。
尾野真千子は色っぽい、麦ちゃんは可愛い、のようなものでも結構ですので、どうかよろしくお願いいたします。
472さん、「いだてんファンスレ」スレ主の時は大変でした。投稿内容への怒りの抗議の人が時折いたり本スレで批判されたり、スレ主としてよく仲裁したり謝罪したり。
「麒麟がくる」は最近は順調なので、472さん他のここの投稿者の皆さんのお陰と深く感謝する次第です。今後ともよろしくお願いいたします。
村角灯さんやスレ主さんのお話、とても勉強になります。歴史(特に日本史)音痴ですが、もう少し調べてみようか・・・という気持ちにさせてもらえますね。これからも時々思いついたことを投稿させて頂きます。やはり最近感じたのは、義輝と三好、松永の権力闘争をもう少し具体的に描いてほしかったという事でしょうかね。十兵衛がときどき京に赴いて、その時だけ戦いに参加している…という描き方で、正直、分かりづらかったです。緊迫感もいま一つですし。
細川藤孝はなかなかの策士だったとのこと。あえてそういう人物の息子に愛する娘を嫁がせた光秀には、どのような思惑があったのでしょうね。
村角灯さんのお話では、光秀は丹波に残していた丹波衆を藤孝の警戒の為に動かす事が出来なかったということなので、光秀の本能寺の変が失敗したのにも、藤孝の動きが大きく影響していたのですね。
義輝が殺害されても、その葬儀には公家は誰も参加しなかったということだから、よくよく孤立していたのですね。村角灯さんがおっしゃるように、朝廷との仲もいま一つだったせいでしょうか。
あの「足利将軍の義輝が「誰か!」と呼ばわっても二条御所はしんと静まり返って返事も返ってこない」というシーンは、池端さんらしく義輝の孤独を鮮明に表現していたと思います。松永が壺を叩き割っているシーンも象徴的な描き方で良かった。ただ、しかし欲を言えばそれに見合うだけの裏付けが欲しかったというか、やはり義輝と三好、松永の権力闘争の描き方が、私には物足りなかったかな・・・。
474ですが、十兵衛と義輝が別れを交わすシーンが圧巻だっただけに、
余計に惜しかった思いも強いのでしょう。
あのシーンは美しくも哀しかったです。
>>474さん 十兵衛と義輝の別れ 確かに美しかった。義輝の烏帽子を透かして見えるモミジの朱色が、長く生きられないという義輝の未来を暗示しているようでした。
麒麟が来るよりもう少し後の戦国は今までにも頻繁に描かれたのですが、三好時代は知識の空白時代というか、三好氏の歴史はややこしすぎて理解不能だっただけに、今回麒麟で少し状況が分かってきたのがとても嬉しくて。自分の都合で投稿して皆さんに窮屈な思いをさせているとすれば申し訳ない。
みなさんの感想を読むのも大好きなのでぜひ投稿してくださいね。
474=475さん、コメントありがとうございます。
全く同感ですね。義輝と光秀の別れは感傷的で武人と言うよりは公達のようでした。
だけど、なぜ、義輝が孤立したか、幕府自体が実質瓦解していたのでは、と思う描写を今までしてきて、今回は義輝個人の資質の問題にしてしまう。それなら今までそう言う描写をしてくるべきでした。
あと、光秀は信長に将軍義輝の理を弁じようとしますが信長は秀吉に接待を任せさっさと席を立ちます。理屈建前が先行し傍観者(バシリは言いすぎでしょうか)に留まざるをえない光秀の頭でっかちの面も見た気がします。
向井理さんは徳川秀忠(江~戦国の姫たち)でなく、「草燃える」で篠田三郎が演じた源実朝とか、今回の義輝のような繊細で心優しい雰囲気を持つ気品ある悲劇的な人物には非常に合っていると思います。実際の義輝は剣豪将軍と言われた人ですが、百人一首の和歌(秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞ驚かれぬる、と言う藤原敏行の平安貴族のもの)を詠むところは向井さんならではの気品がありましたね。
スレ主さん
百人一首の和歌に関して伏線があったようです。
義輝は、
「秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞ驚かれぬる」
と言う貴族の歌を詠じる。
それに対して秀吉は 帰蝶から 武家としてやっていくなら民衆が詠んだ 万葉集 雑歌を読むことを勧められる。名も無き人々の声を聴けという政治の根幹の事。
「我が宿の花橘は散りにけり悔しき時に逢へる君かも」
これは 義輝の事ですね。
その対比が義輝と秀吉の差を際立たせているのではないでしょうか。
村角灯さん、コメントありがとうございます。
以前の回の細かな描写もよく覚えてらっしゃるので素晴らしいです。
確かに秀吉は帰蝶に万葉集を読むことを勧められていましたね。
「我が宿の花橘は散りにけり悔しき時に逢へる君かも」。作者は不詳ですね。花橘が咲き誇っていた時にあなたに会いたかった。
もう少し早く光秀に会いたかった、と義輝が光秀に涙ながらに話した内容と見事に符合します。
単に歴史に詳しいだけでなく、ドラマの細部まで把握されているのですね。できれば私の大好きな「新平家物語」の解説も頼みたいですが、古くて総集編等しか残ってないのが残念です。
スレ主さん
それは違います。 この情報も別の所で教えてもらったもので、私はボーと見てました。 壺を割るシーンの比喩は気が付きましたけど。 蔵之介さんの秀吉 意外といいな と漠然と考えていただけでした。
村角灯さん、お返事ありがとうございます。
でも、日頃の村角灯さんの投稿内容なら十分ありうると思いましたよ。
佐々木蔵之介さんは確かに味わいがありますね。秀吉にしては長身ですが雰囲気は十分あります。
義輝と三好一党の争い というのは、こういう事だったようですよ。 描かれていました。
三好長慶が死んで、三好一党の中は微妙な状態に変化した。嫡男が既に死亡していた為、甥の義継に家督を譲るが、求心力が低下していた。
これをチャンスとみた義輝は、各地の大名に御内書を出して上洛を促す。 これは、京都に来て、足利幕府復権のために、三好一党と戦って滅ぼせ、あるいは京から追い出せという意味。
上杉謙信、毛利元就、織田信長などに上洛を促すのだけど、それぞれ、武田、尼子、斉藤とバトル中でそれどころでは無い。
光秀が信長に持参した御内書もそういう意味ですから、実質支配者の三好としては義輝を捨ておけるわけもなく。
義輝ーー三好 の構造は、義昭ーー信長の構造とよく似ています。
さすがに、将軍殺しの汚名は拭難く、三好氏の評判は落ちてしまったようで、にわか義輝人気が発生したようです。
信長は、これを見て、義昭がどれだけ反逆しても殺すことはしなかった。三好に続いて主君殺しをしてしまうのが皮肉なことに光秀です。
義輝=善 というイメージは、信長=善、信長と終始対立した三好=悪、悪の三好に殺された義輝=悲劇の将軍 という後世に作られたものではないでしょうか。
村角灯さん、おはようございます。コメントありがとうございます。
いつもながら鋭い解説ですね。大いに勉強になります(学者の一般向けの本はそこまで書いてないものが多い)。おっしゃる通り、最後にお書きになられた部分は江戸時代に出来上がり定着したイメージでしょうね。
今回は、しかし、松永久秀は割と共感できる面もある常識人、足利義昭に至っては善良で庶民を大事に思う心優しい人物と言うのが斬新で、そちらから本能寺の変はどう描かれるかも興味津々です。脱「国盗り物語」・司馬遼太郎史観の面白い展開を期待しています。
今後ともよろしくお願いいたします。
土曜スタジオパークのゲストに覚慶上人(足利義昭)役の滝藤健一さんが登場。
前回の足利義輝役の向井理さんがクールで松岡アナが何とか盛り上げようとする必死さが見る側に伝わりハラハラしたが、今日の滝藤さんは「趣味の園芸」にも出てる園芸マニア。そちらで盛り上がり、収録でゲストの門脇麦さんと他作品で一緒の水野美紀さんから他仕事でバリバリの筋肉マン(ボディービルダー?)の体になっていて演出も一部裸を見せる場面を入れたとか。門脇さんとの共演場面が結構あるみたいでインタビューに答える門脇さんの衣装から側室か侍女になる可能性もあるのかな、と思ったり(一切ネタバレじゃないよ)。
仏僧の坊主頭はカツラとのこと。義昭は演じるのが難しい役で混乱することもあったが門脇さんから義昭自身が精神的に混乱してるのでそれでいいと思う、と言われたとか。
「麒麟がくる」では撮影現場で会うことはなかったが別の現場で向井理さんと会い、話を聞けて良かったとか。兄の向井さんが敬語で滝藤さんがタメ語だったらしい(実年齢は滝藤さんが5歳上)。
明日の放送が楽しみです。庶民目線の慈愛ある将軍になるなら私の頭の中の「国盗り物語」・司馬遼太郎史観は崩れたことになります。
今日もBSで「麒麟がくる」を見てきました。
もっとも、地上波の放送が終わるまではネタバレになるので、感想は地上波放送終了後に書くこととします。よろしくお願い申し上げます。
冒頭はあまりに寂しい足利義輝の死に様でした。
民放の「新書太閤記」、大河「国盗り物語」の永禄の変や本能寺の変でも襲撃される側にはある程度は武士がいて少数ながら果敢に戦いましたが、今日の永禄の変では奉公衆の細川藤孝、三淵藤英、一色藤長までが松永久秀と通じ、義輝を追放し覚慶上人(義昭)を擁立しようとしており殆どいない僅かな手勢で三好善継の軍勢に白昼堂々と襲撃され、太刀を持ち父親の義晴から教わった武人の心得を思い起こしながら最後はたった一人で勇戦し三方から障子を楯に刺されて死んでいきました。
「国盗り物語」司馬遼太郎史観との決定的違いは松永久秀は阿波にいる足利義栄を担ぐ息子の久通や三好善継の義輝殺害計画に反対で、義昭を担ぎ細川藤孝ら奉公衆と幕府再興を考えている穏健派のところ、永禄の変が夜襲でなく白昼堂々で義輝側に人が殆どいないこと、覚慶上人は気弱で心優しく殺生を嫌う僧侶で全く野心がないこと等。
光秀は武人としては人の好すぎる覚慶上人は将軍にふさわしくないと考え、義昭擁立を思う朝倉義景に反対します。
よく分からなうのが伊呂波大夫。近衛前久関白ともあろう人がいくら朝廷の権威が落ちたとはいえ、三好側の武士に見張られ粗末な東庵宅で伊呂波大夫とタメ語で打ち合わせ。駒は相変わらずよく分からない薬を作り伊呂波大夫に言われるままに売っていること。
早く信長の上洛が見たい。松永久秀は従来の歴史もの通りには描かないのかな。今のままでは至って普通の人で悪役ではない。
光秀も武将としての才覚を見せて欲しい。バシリでは本能寺の変のインパクトも今一つである。
向井理さんは以前『そろばん侍』(すみません、正確なタイトルを忘れてしまいました)をやられた時に、刀を持った時の立ち姿が美しいと思ったんです。
今日少しだけでしたが、それが観れて良かったです。
487さん、おはようございます。コメントありがとうございます。
2年前の土曜ドラマ「そろばん侍 風の市兵衛」ですね。主演だったんですね。
松永久秀も壺に例えて義輝を「美しい」と言ってたのは向井さんの佇まいもあったのかな、と個人的には思ったりしています。
足利義輝はまさかの「アバン死」ということで、結構話題になっていますね。コロナのせいで、練習も本番前に一回やれただけだったとか。なのに向井さんは殺陣の動きや演出意図をすでに理解しており、最初から義輝の心情の描写というより深い部分に踏み込んでいったそうで、この回に賭けた並々ならぬ情熱がうかがえます。
それにしても、事前に殺陣の先生がつけた動きを動画に撮って向井さんに送るという方法だったそうですから、つくづくコロナでスタッフの方たちがいかに苦戦しているかが分かります。まあ不満をいえばきりがないけど、そういう状況を慮ると、むしろ労いたいという思いのほうが強いですね。
こんにちは(*^^*)
相変わらず要領が悪く、時間をほとんど作れていないのですが…(^.^A
向井理さんの足利義輝に触発され、シルバーウィークでちょっと余裕、少しだけ復活させてもらいます。
長くなりましたので、内容は次のレスで…m(_ _)m
足利義輝が三好に殺害されると、義輝追善には7~8万もの庶民が参加します。朝廷は義輝に従一位を追贈し、上杉謙信等は三好達に激怒します。
義輝は、政権運営に責任の無い一部の公家・遠国大名・庶民には、人気があったようです。
彼らは、戦乱の終焉・秩序回復≒天下静謐を望んでいました。
だから将軍親政≒天下静謐を目指す義輝に期待したのです。
ドラマでの越前の某寺子屋師匠もそうかもしれません(^.^A
しかし、曲がりなりにも政権に携わる三好・松永には、義輝は薄情で不快、無能な危険人物に見えたでしょう。
義輝が親政など出来る訳がない。三好・松永が政権に携われたのは、足利将軍や守護等が、死や苦労を伴う実務を、結果的にですが、放棄したからなのですから。
義輝は、自分では何もできないのに、三好・松永を成り上がりの強欲者と扱い、弱味を見せると、替わりはいるとばかりに切り捨て、他の丸投げ相手を見つけようとする。
(実務例:銭・兵糧の徴収、軍の組織、戦の指揮、治安維持、公正な裁判、インフラの整備、経済運営etc)
(実務の推移。足利→細川→三好→松永)
だから長慶を亡くし弱体化した三好・松永は、危険を感じ、先手を打ち、将軍を義輝から他の『言う事をきく』足利にすげ替えた。
実務者に替わりがいるように、将軍(足利)だって替わりは居ると言う訳です。
しかしすげ替え方は殺すと言う最悪の方法。その後内部分裂し、戦乱を伴う権力争いまで始める。
結局、三好・松永らは政権実務の一部(徴税、軍の組織、戦闘)を行い、政権担当者に見えても、治安維持、公正な裁判、インフラの整備、経済運営等は不充分。
彼らは政権No.1であっても、政権運営者ではない。私権拡大の為に政権に入り込んだ私人だったと言うのが適切かと思います。
天下静謐など期待できる訳もない。庶民からも人気がないのです。
では覚慶は?ドラマで死にたくないだけの人が何故立ち上がる?同じ還俗将軍「万人恐怖」の足利義教、元僧侶?上杉謙信・今川義元との違いは?
大志と能力を併せ持ち、政権担当者に足る・麒麟が祝福する人物?…彼が天下に躍り出るには…
歴史はもう少しの時間を必要としたようです。
489さん、吉法師さん、おはようございます。コメントありがとうございます。
向井理さんは「国盗り物語」の竹脇無我さんのように勇戦し華麗に散った(絶命の場面はカット)のでなく、ほぼたった一人で大勢に立ち向かう悲壮感漂うもので父親からの「強い子になれ」等の麒麟が来るための武人の心得を胸にし悲哀感がとてもしました。撮影には十分な思い入れを持たれていたのですね。土曜スタジオパーク出演時は自分が演じたものには泣かない、とおっしゃてました。
吉法師さんの解説にはいつも唸らされます。一文字三郎直虎さんがご病気療養中ですので無理のない範囲で、私にいろいろ教えて下さい。「いつまでも司馬遼太郎史観状態」から私も脱皮したいと思っています。
村角灯さんもご多忙なのかな。
学者の一般向けの本って本当に大学受験参考書のチャート式や研究シリーズレベルです。山川の詳説日本史にちょっと毛の生えた程度。
今上方から、江戸に嫁いだ娘に会いに坂東の方に下向致しておりまして、中々時間が取れませなんだ。
昨日 ホテルに戻ってテレビを付けたら、あのカッコいいオープニング映像とテーマ曲の真っ最中。なんとか間に合ったと安堵したのですが、オープニングが終われば 永禄の変の後ーーー というナレーション。 昨日の回の見せ場をオープニング前に済ませてしまうなんてそれは殺生な。
という事で、義輝暗殺にシーンは見れなかったのです。
永禄の変前後の話は次のコメントで。
村角灯さん、催促したみたいで本当に恐縮です。申し訳ありません。
今は1週間以内ならNHK+で地上波の1週間分の放送が無料で見られますが、ご自宅には現役世代はなかなか戻れませんね。私も泊まりの出張が多かったので、ある時期の大河は殆ど見られていないのです。
「国盗り物語」の笑みさえ浮かべ松永久秀側(今回は殺害には反対し三好善継に怒る)と果敢に斬り合った竹脇無我さんを思うと向井理さんの父親の言葉を思い起こしながらの孤立無援の剣術は「勝海舟」序盤で勝海舟の知人の町娘を悪人の浪人者が騙して竹やぶに逃れたのを寄ってたかって切り殺した弱い者いじめの感じを思い出し気の毒でなりませんでした。
解説を楽しみにしています。
今回、久秀や義昭も常識人やいい人に描かれると、信長がその分悪人になってきますね。
スレ主さん
ありがとうございます。
私のレベルで教えるなんてとんでもないです。また時間を作れなくて申し訳ありません。
「麒麟がくる」にリンクしているであろう、スレ主さんに教えて頂いた「国盗り物語」の感想を少し書きますね。
先ずは、なんと大胆な!司馬遼太郎さん、意欲作だな?と感じました。
当時、戦後の価値観・高度成長期の社会風潮?(旧弊打破・合理性の権化?・出世至上主義?)に沿う?一方、一級資料・一次資料にはほとんど沿っていないからです。
そもそも、信長編は、何故か明智光秀の目線から語られています。
内容も含めますと、国盗り物語の下敷きが、一級資料の「信長公記」ではなく、誤謬充満と評される「明智軍記」なのではないかと思い付きます。
「明智軍記」が元なので、信長編なのに光秀視点が多いのだと言う事です。
「明智軍記」は、不詳ながら明智・斉藤の縁者が書いたと言われ、親 明智・斉藤で、反 織田。
反 織田で、多くの幕府御用学者と共通していた為か「明智軍記」の信長評は、江戸時代には広く流布され、逆に明治以降には否定されつつありました。
司馬遼太郎さんは、信憑性が高い説より、敢えて、当時として意表を突く?説を元に魅力的な小説を書き上げようとしたのではないでしょうか?
史実よりも、面白い小説を書くために。
ちなみにWikipediaに因ると、麒麟がくるの、小和田哲男さんは「明智軍記」も、全く史料的側面がないわけではないと、おっしゃっているようで、麒麟かくると重なるのは、それが原因かもしれません。
確かに誤謬充満であったとしても、幾ばくかの真実が含まれていてもおかしくはありませんが、読者・視聴者を混乱させる元にもなりそうです…
例えば「明智軍記」の光秀は、日本中を自由に飛び回り、数十名の大大名に一介の浪人の身なのに何故か会えています。
まさに「麒麟がくる」で評判の悪い部分に似ていますが、「明智軍記」を元資料とするなら資料に忠実!むしろ会わなすぎると言う状態です。
吉法師さん、本当に本当にありがとうございます。
「国盗り物語」は明智光秀目線でしたか。濃姫が本能寺の変で討ち死にと言うのも批判があっても多くの人は信用してますものね。吉川英治「新書太閤記」も信長と光秀の関係では似ていて、信長の傍若無人さにインテリの光秀が次第にノイローゼ状態になり本能寺の変につながる描写です。学者の本で照合したくても林屋辰三郎京大名誉教授でもチャート式に毛の生えた程度の記述。
ここで吉法師さんや他に村角灯さん、一文字三郎直虎さんの詳細な解説を聞くと目から鱗なのです。
ウィキで見ても「新書太閤記」で牧の方が波多野秀治の家臣に宙づりにされ処刑されるのは江戸時代の創作とされています。
これからも忌憚ないご意見を心待ちにしています。
スレ主さま
こちらこそ、ありがとうございます。
入院なされると伺いました。無理をなされずご自愛なさって下さい。
戻られたら、また色々お話聞かせてくださいね(*^^*)
永禄の変の時代に京都にいた朝廷、将軍家、三好氏がどれも人気が無かったようです。
① 三好氏の人気が無いのは、彼らが室町幕府の枠組みの中で権力を握る道をとった為
② 将軍家の人気が無かったのは、反天皇の行動が際立っていたから
③ 朝廷の人気が無かったのは、お金も力もなかったから。
【三好氏の動き】
永禄の変の後、四国から足利義栄を迎えることで、傀儡将軍擁立を考えます。三好長慶の跡目相続した三好義重は、永禄の変の首謀者でありながら、それまでの名前義重を改名して義継とし、足利幕府を継承する意図を明確にします。あくまで寄生樹の道を選ぶ氏族です。
【将軍家の動き】
義輝の本葬は永禄の変の1か月後の1565年6月に足利氏の菩提寺である等持院で行われるのですが、その様子を書いた「言継卿記」によると、生前に祇候していた昵近の公家が、その日は一人として参列するものなく、参列したのは、ただ相国寺衆と幕府の奉公衆・奉行集ばかりであったという事です。
【朝廷の動き】
正親町天皇は、義輝に対しては従一位、左大臣を追贈するのですが、三好氏に対しては何の非難もありませんでした。それ以前にも正親町天皇と足利義輝の関係は冷え切っていた事もあるのでしょう。
結局不人気の三すくみの中で発生した永禄の変の後、にわかに反三好、親義輝のブームが起こります。そして、吉法師さんの言われるように義輝追善には7~8万もの庶民が参加します。
【次期将軍をめぐる動き】
客観的に見るために年表を書いておきます。
1565年5月 永禄の変で義輝殺害
1566年2月 義昭 還俗
1566年4月 義昭 従五位下・左馬頭(次期将軍が就く官職)に叙位・任官
1567年1月 義栄が将軍職を継ぐ立場である従五位下・左馬頭に叙任
1567年11月 義栄は朝廷に対して将軍宣下を申請したが、献金が少なく拒絶。
1568年3月 義栄に将軍宣下
1568年9月 義栄病死
朝廷は一旦、義昭を次期将軍にという動きをとり、その後義栄の巻き返しを受け入れます。義栄、義昭両名ともに正当な血筋であり、成り行きを見守っていたようです。
「麒麟が来る」では、義栄に先を越されたように描かれていましたが、実際には、従五位下・左馬頭任官は義昭の方が早く、義栄が将軍宣下されるまでに実に3年近く将軍不在が続きます。
義栄は三好、義昭は朝倉という後ろ盾があった為、決め手に欠けたようです。そこで朝廷は面白い手を取ります。正親町天皇は将軍就任の要件として銭一万疋(百貫)の献金を双方に求めます。 先に応じたのは義栄でした。義栄は一万疋を半分に値切ったのですが、1568年3月にようやく宣下を受ける事に成功したようですね。
近衛前久がいろは太夫の助言もあり義栄の推挙に動いていましたが、これは後に信長によって義昭が将軍になる時に、前久に大きな後悔を強いる事になります。この頃の前久って、失敗ばかりで面白い。
スポンサーリンク