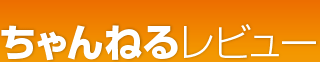すいません。途中で送ってしまいました(^_^A
朝倉攻め直前の信長の状況を書かせて頂きます。
吉法師さん、コメントありがとうございます。
グッドタイミングとはこのことです。
今日の「麒麟がくる」は事前に吉法師さんのコメントを頭に入れれば面白さ倍増間違いなしです。楽しみにしています♪
スレ主さま
ありがとうごさいます(^_^A
実力不足ですが、お役に立ちましたら幸甚です。
【朝倉攻めと織田信長の自信・猜疑心の無さ①】
信長が足利義昭と上洛してから朝倉攻めまでは僅か1年半。
ですが信長は様々な手を打ち天下の称賛を得ています。
「殿中御掟」等では、信長は政権を担う立場を獲得している事が判ります。そして国や民を豊かにする政策を次々に打ち出しています。
将軍を都に据え、堺等 都市からの矢銭等で二条城を構築し秩序を回復。
「一銭切」等で治安も回復。
更に銭を公に使う事の重要さも示しています。
インフラ(道路 橋梁等)整備を開始。産業 交易を促進し、雇用 所得を増大させ、国を持続的に成長させる基礎を作る。
経済発展の阻害、集銭目的の関所を撤廃。
不足していた市中の通貨量を増加。後年の三貨制の基となる撰銭令の発布。
増えた通貨の市中への投入。自身が金貨・銀貨で、名物の買い漁りで市中へ放出しました。
平和で豊かな世の中、「麒麟がくる」のも間近?信長は得意満面だったかもしれません。
(続きます)
【朝倉攻めと織田信長の自信・猜疑心の無さ②】
(続きです)
更に、治安を担保する兵力の基、領土の増大も順調です。伊勢・南近江を自領化。直轄領で200万石。同盟や勢力圏込みで400万石。
諸大名の中で隔絶した存在のみならず、討伐相手の大大名 朝倉(越前・若狭・加賀の一部70万石)の約6倍。
甲州征伐時の織田と武田と同レベルの差。
織田の優位は絶対的。
後は、天下静謐の大義を知らず、欲得で地方に蟠踞する大名共、朝倉等を各個撃破するだけ。
まさか、浅井長政が○○なんて…思わなかったでしょう。
この頃の信長は…スレ主さんのおっしゃる通り、まだ猜疑心は強くなかったと思いますので…
しかし現実には…
しかも、近江が敵方になると、信長の勢力圏は分断されるので、大幅に弱体化するのです。
信長の国や民を豊かにする政策は、権力者達(銭持ち達とバックの大寺院・室町幕府)の、虎の子の権益を奪う事でもありました。
権力者達は、弱体化した信長に、大人しく従うのでしょうか?
「麒麟がくる」には…まだまだ乗り越えなければならない困難があるのかもしれません…
光秀は…
この頃、長男が産まれ、室町幕府と信長を天秤にかけていた?と言われています。
吉法師さん、丁寧で詳しい解説、ありがとうございます。
武田信玄のように同じ強力な戦後大名でも中世の遺産を抱えた武将と異なり信長は社会経済史的にも近世の先駆だったのが654のご記述から伺われますね。
「麒麟」はいったい誰なのか。興味は尽きません。伊呂波大夫とか菊丸とか東庵や駒ではないとは思うのですが。
スレ主さま
ありがとうごさいます(^_^)
【信長の特異性】
信長が特殊で、信玄が一般的なので、個人的には信玄がちょっと可哀想かとも思います…(^_^A
信玄の相続?領土は20万石、全国シェアの1%。血筋も足利幕府のスキームでは二流。全国制覇(天下布武)など夢見ず、自領拡大を第一義に掲げた気持ちは良く判ります。
逆に信長は、常に「人生は短い。(私欲ではなく)死後に皆に偲ばれる事をする。その為の艱難辛苦なら厭わない」と言っていたそうです。
(織田没落後での同世代人の文より)
信長の身分は低く、信秀死去で各将に離反され、精々10万石しか相続できなかったのですが、早くも尾張統一段階で、小牧山城を「火車輪城(悪人を懲罰する)」と名付け、「麒麟」の花押を使用し始めています。
美濃攻略時の「岐阜」命名と「天下布武」印の使用より、ずっと前から、公に尽くす事。天下静謐を志していたと考えられるのです。
信長は、名を後世に残す為に、とにかく学び、考え、頑張ったようです…
連投、失礼致します。
【赤い麒麟を『炎駒』と呼びます】
麒麟ですが、残念ながら?「伊呂波大夫」「菊丸」「東庵」「駒」等、信長や光秀、義昭に近い(創作上の)人物である可能性もあると考えています(^_^A
麒麟は「平和」や「平和をもたらす聖王」その物ではなく、「平和をもたらす聖王」の元に現れる「瑞獣」(吉兆を現す受肉した生物)だからです。
「駒」さんは特に怪しい…
麒麟は、とてつもなく殺生を嫌うと言われており、「駒」さんは、京に秩序をもたらす為の戦さえ拒んでいたからです。
また、麒麟には種類があり、赤い物を「炎駒」、「炎」の「駒」と呼びます。
「駒」さんは幼い頃、燃え盛る「炎」から十兵衛の父に助けられており且つ、基本「炎の色」に近い色の着物を着ていますよね?
しかし「駒」さんが「麒麟」だったら…物議を醸しそうですね?(^_^A
いやいや、私が言うなら眉唾ものですが、吉法師さんがおっしゃるなら有力学説ですよ。駒=麒麟説ですか。将軍義昭の側室になるかもしれず、このドラマの陰の主役っぽくなってきました。
確かに、ネットでは物議を醸しそうですね(笑)。
いえいえ、とんでもございませんm(_ _)m
スレ主さんのおっしゃる通り、駒さん、陰の主役っぽくなってきてますね…
こちらもおっしゃる通り、ネット等での評価、どうなるのでしょうか?(^_^A
皆さん。 今日の 麒麟が来る は圧巻でした。
信長、家康、秀吉、光秀、役者が揃いました。 今まで、人物を掘り下げる期間が長かっただけに、それぞれの人物に感情移入してしまって。 信長と一緒に泣き、光秀と一緒に泣き、藤吉郎と一緒に泣き、凄い回でした。
光秀が表舞台に出て俄然面白くなってきました。
村角 灯さん
こんばんは(^_^)
ありがとうごさいます。
そうなんですね♪
録画で見る事になりそうですが…
楽しみです(^-^)/
村角灯さん、吉法師さん、コメントありがとうございます。
専門的な考察はお任せします。
さて、信長の朝倉攻め、台詞を拾うと、信長の重臣の柴田勝家、佐久間信盛より、松永久秀と徳川家康の方が今から見れば理に適った攻撃方法を進言してますね。
光秀が浅井長政に背後を衝かれた防御の殿軍に絡んでましたが、私が読んできた学者の本では信長が「誰ぞ、殿つかまつれ!」と言い名乗りがないのに激怒したところ、藤吉郎が「自分が」と進み出た描写でしたが今日は光秀が絡み藤吉郎の申し出を受けると言うことになってましたね。
お市の方は無名ながら「さくらの親子丼」で更生施設の性的虐待経験を持つ非行少女を演じた井本彩花さん。17歳ながら全日本美少女コンテスト優勝者ですか。将来の朝ドラヒロイン候補ですね。
ちょっと、鶴太郎さんの摂津晴門の「半沢直樹」の悪役物真似が鼻につき出しました。猿之助さんの伊佐山部長か、愛之助さんの黒崎金融庁検査官か。柳の下の二匹目のドジョウの視聴率狙いですか。私個人は食傷気味。いい加減止めて欲しい。
将軍義昭もいい人から夢見る夢男さん的になってきた。福祉施設を一つ京に作るより天下を平定し農民が安心し農産物を作り、信長の楽市楽座のように中世のギルドのような仕組みを打破することが重要で視点がやや狭い気が。交易を盛んにするのも重要だが。駒はどうするのか。
光秀もどう動くのか。確かなビジョンで天下を狙う人物になってもらいたい。
金ヶ崎崩れで殿を務めたのが、藤吉郎と光秀と描写されていましたが、真実でもあり、嘘でもありますね。
大将は摂津守護の池田勝正で、配下3000人で殿を務めました。藤吉郎は、副司令官、光秀は軍監のような役目ではないかと想像します。
藤吉郎は、ドラマ中では1000人の足軽を持つ身と自称していました。美濃の時代から墨俣城を預けられたりしていたので、それなりの兵を信長から預けられていたのでしょう。
分からないのが、光秀が持っていた兵力の規模です。義昭から預けられた兵? 経済基盤は何でしょうね? 案外、光秀と近臣だけだったかも。
そして理解しにくい事が一つ。池田勝正も、明智光秀もこの時期は幕臣です。 何故、信長は自分の配下に殿を託さなかったのでしょうか? 池田勝正は信長上洛の時、三好三人衆に与して信長と戦った人で、危険と感じるのですが。 分からない事だらけです。
村角灯さん、コメントありがとうございます。
光秀が殿を務めたのは史実なのですか。
関ケ原で織田秀信の岐阜城を攻めた東軍の先鋒は福島正則、池田輝政と言う外様格の武将でした。家康は自分への忠誠心を試したように司馬遼太郎は「関ケ原」で書いています。
今回は光秀が殿を務める合理的理由が分かりません。史実なのでしょうか。
スレ主が廃スレにした前スレに書きこんで意味不明の独り言を連投している人物がいますが、「麒麟がくる」ファンスレの皆さんはスルーして、こちらに投稿して下さい。
じつは、私は、昨日、某スレに入ったことによって、犬好き様と( ・-・)様の仲を悪くさせてしまって、責任の一端を感じています。
667さん、ここは「麒麟がくる」ファンスレで「麒麟がくる」や歴史の話をする場所です。そのようなお話はこのスレではしないで下さい。旧スレ同様にお止め頂けないなら違反通報します。
スレ主さん こんにちは。
そうなんです。先鋒の場合は忠誠心を試す理由で最も危険な任務に付けるのは常道なのです。たとえ裏切られてもこちらは手付かずの兵が背後から弓矢をつがえて狙っているわけです。
ところが、退却戦の場合は、裏切られたら退却中の自分への追手になるので外様をつけるというのは考えにくいように思うのです。
どなたか、この辺りの背後関係を教えて貰えると嬉しいのですが。
村角灯さんが分からないなら降参だ。
吉法師さんでも一文字三郎直虎さんでも他の誰かでも助けて下さい。
まさか光秀は室町幕府幕臣ながら隠れ織田家武将とか。早い話が足利義昭に対する信長のスパイ。いやいやいや、ないよねえ。
【麒麟がくる 感想】
見ました(^_^)面白かったですねえ♪
史実はさておき、信長の迫力、秀吉の如才なさ、一本気な光秀。「戦の無い世の中にするため、今は戦をする!」いよいよ時代が動き出すのでしょうか?
さて、リクエスト頂きました、金ヶ崎の退き口、僭越ですが、ご参考になれとばと言う事で記載致します。
なぜ信長から見ると、外様であるはずの池田が殿を纏めたのか?危険ではないのか?
結論を先に述べますと、私は危険ではなかったと思っています。
新説は、その論拠となる一部の資料の内容に偏る傾向にあり、その観点で見ると危険にも感じます。
しかし私は、面白味がなくて恐縮ですが、金ヶ崎の実際は旧来の定説に近かったのではないかと考えています。
その観点では、さほど危険ではなかったように思うのです。
(続きます)
(続きです)
つまり、後に袂を分かつ、義昭と信長の対立はまだ深刻ではなかった。
ですので、上洛を拒否し、反義昭・信長を明確にした、若狭・越前 他の朝倉に対し、義昭・信長は共同し、信長を主将とした連合軍(松永・徳川・三好・池田・明智等)を組織して、征伐を実施した。
しかし主将 信長の義弟?浅井長政が反義昭・信長派に寝返ると言う予想外の事件が起きた為、連合軍は大ピンチに陥った。
連合軍は、予想外のこの大ピンチから可及的速やかに脱出する為、共同して撤退を実行。殿は秀吉等が務めた。
と言った内容だと思うのです。
以上の状況ですと、秀吉に殿を任せた。そこに池田や明智もいたかもしれない。信長はそれにそれはどは危険を感じないのではないでしょうか?
内容は長くなりますので、改めて別レスにて後ほど…
尚、歴史の経緯を書きますので【ネタバレ】になる可能性があります事、お詫びと共にお知らせ致します。
ですので投稿の一行目に【ネタバレの可能性あり】と記載致します。
宜しくお願い致します。それでは、また後ほど…(^_^)
吉法師さん、丁寧な解説ありがとうございます。
なるほど、幕臣の武将と信長は堅い同盟関係にあり信長は全幅の信頼を寄せていた、と言うことですね。
余談ですが、家康は関ケ原で外様格の豊臣系の反石田三成の武将に手柄を立てさせたために褒賞を出さざるを得なくなり、これに懲りた家康は大坂冬の陣夏の陣では徳川譜代(後の御三家、親藩含む)主導で戦いましたね。
スレ主さま
ありがとうございます(^.^)
義昭と信長は同床異夢。
義昭を神輿として信長が実務を担い秩序を回復すると言う「立場」は同じ。
しかし「目的」軍事・経済・国家運営、これらは大きく違っていたのです。
ですので、堅い同盟関係にあったとか、信長が全幅の信頼を寄せていたと言う事はないと思いますが、同じ義昭陣営ですし秀吉などの織田兵も居る中で、幕臣達が裏切って、【この段階では】反義昭陣営だった浅井・朝倉・六角に付くとも思っていなかったと思うのです。
ひょっとしたら、単に消耗率の高い殿に織田兵をあまり置きたくなかっただけかもしれませんよ。
浅井・朝倉はその後、正統性を得る為に義昭を取り込みにはしります。義昭と信長の不和をついた、この作戦は見事成功。信長包囲網を構築するにまでになります。
この後のイメージが強い為、池田達が裏切ると言うイメージになるのではないでしょうか?
大坂の陣…確かにそうですよね。
得る土地がなくても…戦う度に恩賞が必要。将軍も因果な商売かもしれませんね(^.^A
吉法師さん、詳細な解説ありがとうございます。
なるほど、同床異夢でしたか。今風に言えば戦略的互恵関係と言うものでしょうか。堅い同盟、全幅の信頼は言い過ぎでした。お恥ずかしい。
外様は信用なりません。徳川家の提灯持ちの津の藤堂藩が鳥羽伏見の戦いで山崎の陣地から中立から官軍に寝返って幕軍を砲撃したことを司馬遼太郎は批判的に描いています。
関ケ原で恩賞を与えた豊臣系大名を幕府は力づくで取り潰していきましたね。福島正則、加藤清正の子の忠広、加藤嘉明の子の明成とか豊臣秀頼に対したと同様のいちゃもんを吹っかけ、まさに将軍は因果な稼業です。
信長の退却ルートに関する情報です
敦賀の 手筒山城と、金ヶ崎城は尾根続きにあります。
池田勝正は手筒山城に3000、木下藤吉郎+明智光秀は金ヶ崎城に手勢700(一説には300)で守兵となったようです。
私は、金ヶ崎城址に行ったことがあるのですが、金ヶ崎城があった山は低く、守るのに適しているとは言えません。これが新田義貞時代から有名な金ヶ崎城? と不思議に思ったほどでした。
一方、そこから10kmほど西にある若狭の佐柿国吉城は、数日前まで信長本陣であり、城は難攻不落といわれた山城で、池田、秀吉、光秀らは殿を務めながらそこに逃げ込もうとします。その際に、殿軍の最後尾(木下藤吉郎軍)が朝倉勢に追いつかれ、激戦が発生したようです。国吉城を経由した退却の事は日曜日の麒麟が来るでも紹介されていましたね。
若狭の国吉城に入ってからは、朝倉軍も深追いしなかったようです。その地が朝倉領ではなく、かつて朝倉氏は国吉城を何度も攻めたが落とせなかった経緯がある為かと思います。
この時期、既に幕府と信長は一体ではありません。例えば金ヶ崎崩れでの主要登場人物の一人、朽木元網は幕臣ですが 信長が朽木谷に来たら殺そうと考えていたのを松永久秀が説得して退却に協力させたという話が伝わっています。
第一次朝倉征伐が、若狭の武藤氏を征伐する名目で行われたのは、朝倉攻めに足利義昭の同意を得られなかったからです。
信長が五カ条の条書などを義昭に飲ませて両者の対立関係が顕著になってきた時期です。義昭としては、織田との決裂が決定的になった時に、朝倉というスペアを残しておきたい思惑があったのでしょう。
さて、スレ主さん。 津藩の藤堂氏が徳川軍を裏切ったこと、そして、淀城に逃げ込もうとしていた幕軍を裏切った稲葉氏を司馬遼太郎さんは強く憤っていましたね。 私は決して佐幕ではありませんが、同じく怒りを覚えました。 しかし、幕府より上の天皇の勅命なのだから、彼らも抗う術がなかったのかもしれません。
村角灯さん、実に詳細な解説ありがとうございます。
信長と義昭に隙間風が吹き始めていたのですね、なるほど。
鳥羽伏見の戦いで天皇の名と言うのは幼少の明治天皇で、山内容堂が「幼帝を擁し権力を私する者」と西郷、大久保らを批判しかけると岩倉具視が西郷隆盛、大久保利通の応援もあり一喝し、井上清教授はボンボン育ちの松平春嶽や山内容堂は叩き上げの西郷、大久保に敵うものでなかった、と書いていますね。
こんにちは(^_^)
村角灯さん、金ケ崎は景色はキレイですが…確かに難攻不落のイメージじゃないかもしれませんね(^_^A
補足と論拠のご説明です。
私も村角灯さん同様、幕府と信長は一体ではないと思っています。
以前書いた同床異夢、スレ主さんに上手く訳して頂いた戦略的互恵関係です。
潜在的には敵でもあるが、利用し合う仲でもある。表面上では敵対出来ず同陣営。
そして義昭は、金ケ崎の後も『将軍親征』つまり信長の戦いに義昭自ら出陣する事。を行っています。また信長は、金ヶ崎でも、諸将が裏切らないよう、人質を取っていたようです(信長公記)。
ですので金ケ崎の段階では、義昭と信長の間に暗闘はあっても、池田勝正や光秀が、独断で信長を裏切り討つ可能性は低いと私は考えるのです。
『この時点の義昭は、信長が横死しても困らなかったのか?兄を殺した三好陣営に身を委ねられるのか?人質を無視できるのか?』長くなるので内容は割愛しますが、そう言う問題だと思うからです。
朽木の件は、軍記物「朝倉記」に記載があり、可能性はあると思います。
但し仮に本当でも『朽木領の場所を考えると』、理由が、幕臣だからではなく、浅井・六角との関係だった可能性もあるのでは?
次に、私がWikiにも書かれている「武藤攻め」を口実に説、を採らない理由は以下の3つ。
①資料には「越前へ」「若州へ」と双方あるが、どちらにせよ朝倉支配下である事。
②武藤(5000石≒兵力200人?)攻めには、大軍すぎる事(3万~10万人)
③「武藤攻め」の根拠と言われる「信長から毛利元就への文書」の内容を文字通りに取るべきではないと思う事。
毛利文書の内容は、Wikiにもほぼ記載がないので簡単に説明します。
「若狭の武藤を成敗した。朝倉からちょっかいがあったが、軽くあしらった。しかしそこで毛利と共闘の時期になった為、京に戻った…」
などの内容。浅井の裏切りにも、自身が逃げ帰った事にも一切、触れておらず、遠征は成功の形で毛利に報告しているのです。
『朝倉を攻めた』は書けない。書いたら『遂行できなかった事』も書かなければならないからです。だから『武藤攻め』と書いた…
この文書は論拠には適切でないと思いませんか?
新喜劇の「今日はこれぐらいにしといたるわ」を思い出します…(^_^A
吉法師さん、詳細な解説ありがとうございます。
最後は池乃めだか師匠で来ましたか(笑)。私からは専門的すぎて、特にコメントするところはないですね。
ただ、朽木元綱と言う武将は関ケ原で小早川秀秋に呼応して寝返り西軍の大谷吉継勢を攻めて潰走させた印象があり、私個人は良い印象がないのです。
専門的なことは他の投稿者の皆さんに譲ることとします。
冒頭から「半沢直樹」の猿之助の伊佐山部長か愛之助の黒崎金融庁検査官の物真似の鶴太郎さんの摂津晴門。高視聴率にあやかりたくてこんな演出してるんですか。ちょっと暑苦しいのでこれはいい加減止めてもらいたいなあ。
如才ない藤吉郎の立ち回り。小ずるい感じを佐々木蔵之介さんが好演(「ひよっこ」の朴訥なシェフとは全然違う)。
駒ってスーパー庶民ですね。足利将軍家の義昭の寵愛を一身に集めるって春日局か天璋院篤姫か。まあ帝の囲碁仲間の東庵、前関白の幼馴染の伊呂波大夫がいるので驚きませんが。まんまと光秀に今井宗久から鉄砲を筒井順慶分を得ることに成功。
姉川の戦いには勝利したものの延暦寺と結ぶ朝倉義景に苦戦の信長。延暦寺と石山本願寺を屈服させねば天下取りはできませんね。
家康は武田信玄を視野に入れてますね。風間俊介さんだと実直な青年で後年の狸親父の面影はないです。
光秀は名将と言うより政界フィクサーの匂いがしていますね。
「麒麟が来る」では描かれない内容が信長公記にはいろいろと書かれていてとても面白く読んでいます。
【1 第一次朝倉征伐の後始末】
第一次朝倉征伐で信長軍が京に逃げ帰った後、信長は丹羽長秀と明智光秀を若狭に派遣して、武藤友益から人質をとり、城を破却しています。
元々、武藤友益を征伐する為と言う口実だった遠征ですので、結果的にこれで遠征は成功という体裁を取ったのでしょうか。この辺りの時期に既に明智光秀は丹羽長秀と併記される重要人物とみなされていたというのは凄い事です。
【2 六角義賢の蜂起と平定】
義昭上洛の時に、信長に蹴散らかされた六角義賢が近江で蜂起し、美濃-京の連絡路を絶つ行動を起こしたので、それを平定
【3 志賀の乱】
信長は、
①延暦寺から奪った所領を返還する
②仏法を守る寺院として、浅井・朝倉に味方しない、少なくとも中立の立場を維持してくれ
③ ②が守られないなら、焼き討ちする
という手紙を何度も延暦寺に送って、延暦寺が浅井・朝倉を匿うのを止めさせようとするのですが、無視されたようです。 これが、光秀が主力になる延暦寺焼き討ちにつながるのですが、紹介されませんでしたね。来週かな?
「麒麟が来る」では、信長を自分は信じたいのに、常に裏切られる孤独な人として扱っていて、感情移入してしまいますね。信長公記を読んでみると、絶え間なく戦いに明け暮れていて、彼の戦いへのモチベーションは何だったのだろう? と考えさせられてしまいます。
【4. これは信長公記ではないのですが】
第1次朝倉征伐のわずか2か月後、の元亀元年6月に、池田勝正が守護をしていた摂津で内紛が起こり、池田勝正は追放され、摂津(池田市、尼崎市、西宮市あたり)が三好側に寝返ります。その結果、信長の瀬戸内へのルートが遮断されます。 それを回復すべく発生したのが元亀元年6月の昨日紹介されていた野田城・福島城の戦いです。 摂津に残った池田氏は幕府・信長を裏切ります。
信長、義昭の政権は非常に微妙なバランスの上に成立していたようです。
村角灯さん、おはようございます。コメントありがとうございます。非常に興味深く読ませて頂きました。
柴田勝家と並ぶ織田家の重臣の丹羽長秀と光秀が同格とは驚きです。この時期は光秀はまだ幕臣ですよね。
延暦寺の天台座主の覚恕法親王(春風亭小朝さん)が予告編にいましたね(このレベルのネタバレはお許しを)。「国盗り物語」には兄の正親町天皇とも出ていなかったので(朝廷関係や松永久秀が出ていない。久秀役は台詞なしのエキストラ)興味津々です。
近畿圏は石山本願寺を制圧しない限りは信長は安泰にならないですね。荒木村重も裏切りますし。
東庵先生は何者なのか?
曲直瀨道三なのか、そんな気がする。
スレ主さん こんにちは
光秀は第一次朝倉征伐の頃に将軍から京都市の下久世に領地を拝領しているので、幕臣、あるいは両属ですね。
ところで、筒井順慶が登場することで大和における信長の政策の矛盾に苦しんだ松永久秀を深く描いていくんでしょうか。 今回、吉田剛太郎さんという主役級の人を配しているので、何故久秀が信長を二度も裏切る事になったのかを詳細に描くのだと思います。 そしてそれが、光秀の謀反とおそらくオーバーラップしていくのではないかと想像しています。 皮肉ですよね、筒井順慶を幕府、信長に紹介したのが光秀って。
麒麟が来る は今までと歴史の切り取り方が違っていて本当に面白いです。覚恕法親王も楽しみですね。
ちなみに、東庵先生、摂津晴門の喋り方をなんとかしてくれ!! というのは私も同感です。
あごさん、コメントありがとうございます。
東庵=曲直瀨道三説、非常に面白いですね。正親町天皇の診察もしてますから囲碁仲間でもこの際いいでしょう。しかし、博打好きと言うのは困ったものです。
村角灯さん、コメントありがとうございます。
なるほど、光秀は幕臣であり信長にも臣従していたとも考える余地がある訳ですね。
松永久秀が吉田鋼太郎さんと言う特にNHKではお気に入りの俳優が演じ、筒井順慶も「カーネーション」のヒロインの夫で鶴瓶師匠のご子息と著名な演技陣ですから「国盗り物語」にない場面が描かれそうですね。洞ヶ峠もやるんでしょうね。
覚恕法親王、正親町天皇とも著名な俳優を配し力を入れてる感じです。
そうですよ、あの東庵の勿体ぶったネチネチした話し方、それとどう見ても「半沢直樹」を意識した鶴太郎さんの摂津晴門。鶴太郎さんは「太平記」ではバカ殿北条高時でしたがあんな歌舞伎か桃太郎侍か暴れん坊将軍のような変な節回しの話し方でなかったから演出の指示でしょうね。高視聴率作品の猿真似は駄目です。まさか光秀に「お前の負けえ~~~~!!」と伊佐山部長のギャグを言わないでしょうね(笑)。
あごさん
東庵先生=曲直瀬道三 説 は確度が高いと思います。曲直瀬道三と明智光秀は深い親交があり、光秀が京都奉行の時期、自分の屋敷は持たず、曲直瀬道三の家にいそうろうしていたそうです。
スレ主さん
松永久秀は、信長と義昭から「大和切り取り次第」の許可をもらうのです。しかし、筒井順慶が信長と義昭に仕えるようになった後、両天秤にかけられ、結局筒井順慶が大和守護に任命されるんですね。松永久秀が謀反を起こす心情も理解できます。
そして、この構図は、四国切り取り次第を長宗我部元親に許しながら、三好氏と組んで長宗我部と三好を両天秤にかけた信長の四国政策の状況とよく似ています。
そして、蔑ろにされた長宗我部元親のバックにいて板挟みになり、面目を潰されたのが光秀。松永久秀の事が頭をよぎったのではないでしょうか。そして本能寺。
さてさて、当たるも八卦当たらぬも八卦。どうなりますことか。
遅い時間に失礼します。役所に出す書類を書いてました。
村角灯さん、実に鋭いじゃないですか。
松永久秀は筒井順慶と競わされたのですね。長曾我部元親も三好の残党と競わされたのですね。
何やら吉川英治「新書太閤記」で秀吉と競わされた光秀の苦悩もちらついてきました。でも、池端俊作さんは敢えて「新書太閤記」「国盗り物語」と言う往年の著名な作家の歴史観に挑戦状をたたきつけている感じがあります。
はてさて、今後の描写が俄然楽しみになってきました。
あごさん 申し訳ないです。記憶違いがありました。
光秀と繋がりが深く居候していた医者は 曲直瀬道三の弟子 施薬院全宗です。光秀が坂本城主になった後も天正5年までその関係は続きます。
施薬院という名で 義昭、駒の会話とも繋がってきますね。
全宗は後に秀吉に仕えて 秀吉の命により施薬院を再興。また比叡山の再興にも尽力します。
今のギャンブラー東庵先生からは想像ができないけれど、もし駒の願いで平和の象徴である施薬院が再興したらそこで働く医師は東庵先生になるのがピッタリではないでしょうか。
東庵先生のモデルは施薬院全宗と推測します。
あごさんより先に返事して申し訳ありません。
施薬院全宗だそうですよ、あごさん。何か一言お願いいたします。他の皆さんもご意見があればどうぞ。このレベルだと私はコメントできないです。
スレ主さん 最近失敗ばかりで混乱させてしまいすみません。
ところで 菊丸 はどこに行ってしまったのでしょう? 家康に仕えているのかな?
菊丸、見ませんね。次回当たり出てきますでしょうか。
曲直瀨道三。
1507~1594、近江源氏、近江国(守山市)出身。
足利義輝、織田信長、明智光秀、細川晴元、三好長慶、毛利元就、正親町天皇など。
斎藤道三と並ぶ二人の道三。
イメージというかアレンジしたオリキャラだと思います。お弟子さんはたくさんおられたようです。
ドラマでは唐突に帝と囲碁、事前に帝の診察がきっかけというエピソードが欲しかったような。
囲碁というのが本能寺における算砂のエピに繋がるのか?
あごさん、本当にありがとうございます。
算砂と言うのは、本能寺の変直前に信長と囲碁を打った仏僧であり棋士ですね。
本能寺の変の前日に算砂と利玄が信長の前で囲碁を打ち、その時に三劫(こう)無勝負という珍しい局面になったそうです。
それで三劫は不吉とか、しかし日本棋院の見解は吉報😱
その時の打ち掛けの棋譜がありますが、その棋譜が本当なら、そのあと三劫無勝負になるとは考えられません。
話しは変わり明石の花火事故でマスコミがしきりに将棋倒しというから将棋連盟から将棋倒しとか
言わないでくれとクレーム。
そこで将棋倒しは禁句に、しかし言葉狩りだと
クレームがはいり再び将棋倒しが復活(めでたし、めでたし
あごさん、おはようございます。コメントありがとうございます。
とても面白い話ですね。こう言う話は大歓迎ですので、これからもぜひご投稿下されば非常に嬉しく思います。
ラストは酷いの一言でしたね。
幼い妹が延暦寺に売り飛ばされ買い戻すべく駒から買った薬を売りに比叡山に登った少年が無残に斬殺される。演じたのは込江大牙君。「エール」で鉄男の幼少期を演じ「35歳の少女」では結人の子供時代を演じる。子役でも難関なのに重要な役を次々に演じるのはポテンシャルが高いと評価されてのことだと思う。「麒麟」ではもう出て来ないね。
比叡山に物売りらしき女性の他に遊女も多数。何より、座主の覚恕法親王が女官を多数膝元に侍らせオスマントルコ帝国のハーレムの如し。しかも実兄の正親町天皇への容姿等からの強い劣等感と京の実益の現世の煩悩にまみれ宗教者とかけ離れた生臭坊主。政界フィクサーの如く朝倉義景や摂津晴門とも癒着。信長の叡山焼き討ちを正当化する描写だが、巻き添えの薬売りの少年や物売りらしき女性はとんだ災難。光秀は「女子供は逃がせ」と言うが手遅れ。以前のドキュメンタリー番組では秀吉の軍勢は逃げ道を確保しながら攻めたが光秀は包囲殲滅して回ったとあった。「国盗り物語」は非道な信長に唖然とする光秀だったが、「麒麟がくる」は叡山に相当の悪行があり光秀も信長にそこまで批判的でない。ただ、巻き添えの貧しい庶民が気の毒だ。
松永久秀は怒り心頭。将軍義昭は筒井順慶も厚遇してるのを知ったからだ。この人は慈愛深いが人が好く政界の暗部に疎い。摂津晴門らに言いように利用されている。
玉三郎さん、ふくよかな顔立ちになって却って天皇らしく見えます。
光秀の心情描写が私には少し分かりにくい。自分の信念は何かが見えてこない。
鶴太郎さん、冒頭から「半沢直樹」の伊佐山部長か黒崎金融庁検査官の物真似はもういいから止めて下さい。そんなことしても視聴率には関係しませんよ。
歴史が動き面白いです。
甲冑姿が多いので、表情が捉えにくく、心理の理解が難しいですね。
金ヶ崎崩れで殿を務め、現実を知って、理想主義者で無くなった。六天魔王信長の第一の理解者になった。摂津晴門や覚恕の旧体制の悪弊を目にして「新しい世の中を作る為に旧悪は破壊すべき」との決意ができた。 などでしょうか。
変に比叡山焼き討ちを止めることを注進するような薄寒い演出でなくてよかったと思いました。
しかし、光秀が特別である理由がわからないですね。比叡山焼き討ちの後、光秀は志賀郡を拝領し、延暦寺の利権を継承し、坂本城の建築を許されるという、破格の褒美をもらうのですがなぜでしょうか?
村角灯さん、おはようございます。コメントありがとうございます。
そう、歴史が動き出しましたね。
光秀が特別待遇である理由は何故なんでしょう。
おかしな先入観のない公平無私の村角灯さんなら今後の回で答にたどり着けると思いますよ。
私は司馬遼太郎史観に漬かっていた反動で「国盗り物語」で信長の叡山焼き討ちの残虐さに眉を顰める光秀は司馬さんの思い込みで、実は光秀が叡山焼き討ちを率先して容赦なくやり遂げたからではないか、と言う気もします。ドキュメンタリー番組は秀吉の軍勢より光秀の軍勢の方が残虐だったと、ある寺の住職が伝承を語っていました。
スレ主さん そうですね。
光秀が叡山焼き討ちを率先して容赦なくやり遂げたからかもしれません。比叡山焼き討ちに反対意見を述べたとされる佐久間信盛は後に追放されていますね。
それにしても、ドラマとしてはデジタル式の善悪で面白いのですが、覚恕を悪く扱いすぎのように思いました。
覚恕が天台座主になったのは、浅井朝倉が叡山に籠る志賀の陣の年、叡山焼き討ちの1年前です。 叡山腐敗の責任を彼に負わせるのは不公平と思う一面もありました。
村角灯さん、コメントありがとうございます。
「国盗り物語」を改めて読んだら、信長に御仏の尊さを説き叡山焼き討ちを諌止する光秀の髷を怒りに任せてつかんで振り投げる無神論者の信長が描かれてますね。光秀が教養を立てに神仏のありがたさを小賢しく説くのが我慢ならない。でも、これは史実でなく司馬遼太郎さんの創作に過ぎないのですね。「西郷どん」でも思いましたが司馬遼太郎=史実と信じている人がいかに多かったか。
覚恕は悪く描かれすぎです(笑)。だいたい、あの摂津晴門の「半沢直樹」悪役調の歌舞伎か桃太郎侍のような抑揚は何ですか。殆どコントですよ。二条晴良も見るからに近衛前久に比べて悪役が分かりやす過ぎます。何か視聴率を意識してる気がしますね。
スポンサーリンク