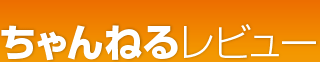3.60
3.60
| 5 | 411件 | ||
| 4 | 216件 | ||
| 3 | 66件 | ||
| 2 | 48件 | ||
| 1 | 210件 | ||
| 合計 | 951件 |
義時は傍観者というより、人の意見を聞き、より妥当だと思われる意見に、彼が同意することによって周りが動いていく、という人物としているように思える。
根は温情派だが、同時に冷静に事態を見分け、情に流されない判断力の持ち主であり、そのことを皆が知っているので、信頼もされ、彼の判断に乗って動いていくということではないか。頼朝さえ彼を最も頼りにしているように描かれていた。
例えば、中国の漢の高祖•劉邦がそういう存在だったのかもしれない。彼を支える明晰な多彩な人たちに恵まれたということも似ている気がする。
特徴を捉え、それぞれのキャラが立って面白い大河になっている。
個人的には『草燃える』のほうが好きだ。
合戦シーンの躍動感、軍議や評定の場面の緊張感や心理戦、女性たちのキャラなど、見ごたえのあるドラマだった。
圧倒的な演技力の石坂さん、岩下さん。純朴な青年だった義時(松平健さん)が、茜(松坂慶子さん)と別れてから徐々に変わっていき、最後には時政よりも老獪な政治家となっていく姿に恐ろしさを感じた。そしてため息がでるような美しさの松坂慶子さんの茜役と白菊役の対比の演技が素晴らしかった。
可憐で繊細な大姫を演じた池上季実子さんも印象的だった。
朝廷から征夷大将軍として正二位の官位を授けられた頼朝の正室として御台所に出世した政子にたいして、地下公卿出身の牧の方(りく)のジェラシーがエスカレートしていくのが面白かった。
安達盛長も武田鉄也さんの緩急のある演技が良かった。義村(藤岡弘さん)も義時と同様に老獪な御家人に変貌していく様にゾクゾクした。
今、振り返ると、脚本、演者、制作陣の意気込みが伝わってくるような『草燃える』だった。
『鎌倉殿の13人』は、歴史的にどうでもいいような話題、あるいは歴史を改ざんしたような話をたくさん盛り込んだコミカルファミリードラマのように思える。たぶん後半も変わらないだろうと思う。だから録画をしてまで観る気はない。
大泉頼朝さんお疲れ様でした。
今後の時政の行動はりくの入れ知恵が多くなりそうだ。
次回は最初で最後の13人が揃うことになるのかな。
草燃えるは、頼朝や政子、時政、義時などを中心としたドラマとしては初めてで新鮮であり、わくわくしながら見ていた。しかし、制作年が今と違いすぎて、今年の鎌倉殿とは比較はできないと思う。
少なくとも今あらためて見ると、いかにも「劇」であり、舞台の上で演技をしているような演出だ。それが時代劇といえばそうなのだが、やはり古い。
だからといって、草燃えるの価値が下がるわけではないが、今見たら、井戸端会議や、御家人たちの内輪話、男女間のあれやこれやでもどかしい場面も多く、面白くないと感じる。
今のドラマは、安っぽいとか、大道具小道具に手抜きが多いとか、作家や演出の元も良し悪しがあり、決して昔より良くなった、とは言えないが、少なくとも昔のドラマのような古さは感じない。かつ、新しく発見された史料や研究成果を取り入れている部分もあり新鮮さがある。昔のドラマは史料も見解も古いものをベースにしているだけなので、今見ると物足りなさが大きい。
「行かず〇〇」なんて聞いた事があって、何かイヤな言葉だなと思っていたんだけど
この時代の女の人は夫が死ぬと「後家」として夫の権限、家を引き継ぐんだったね。
たとえ嫡子が成人していたとしてもお母様の力には逆らえない。
歴史の先生が教えてくれた。
自分も政子様が鎌倉殿になってもらいたいと思う。
さっさと再婚していた人もいたけどね。常盤御前は源義朝の側室だったが、一条長成と「再婚」している。義経が奥州藤原氏の元に向かったのもそのコネがあったからという説もある。
「これは何ですか?」で始まり「これは何ですか?」で終わった。
第一話、宗時お兄ちゃんが実衣に佐殿に持っていくようにと託した果物を政子が横取りして持っていった事が姉妹の運命のいたずら。
いやね、端々、隅隅にまでサービス精神のあふれるストーリーだね。
板東彌十郎さん
最初はこの爺さんと宮沢りえの夫婦に違和感しか無かった。
このところ
NHK、Eテレでは歌舞伎にまつわる番組で
民放各局では、トークでもクイズでも面白かった。
北条時政がこの人じゃなかったらここまで見入っちゃう事が無かったんじゃないかと感じる位大好きになりました。
私も最初はテレビドラマでお見かけした事のない坂東彌十郎さんの時政がちょっと不満でしたが、回を追うごとに、魅力を感じるようになりました。
時政お父さんが出て来ると、なんとなく安心感に包まれる。人生経験豊かな時政の何気ない一言が、周囲を和ませ、義時達を導いている気がする。
坂東彌十郎さんのお人柄が画面に反映されているのでしょうね。
不謹慎かもしれませんが、頼朝を亡くした政子とアッキーが重なってしまい、悲しかった。
頼朝の死後後継者を巡って分裂してしまった北条家。政子には義時しか味方がいない状況。ここで是非政子の味方として亀の前に再登場してもらいたい。亀の前はあの事件以降行方が判らないらしいが、実は三浦氏の保護を受け頼朝がその後も度々彼女の元に通ったらしく、頼朝死後は妙悟尼として大椿寺を建立して菩提を弔ったらしい。
ドラマだから裏のブレーンとして政子を支える存在となれば面白そうだと思うけど。
常盤御前が一条長成と再婚したのは、別に常盤御前の意志ではなかったと思う。
義朝の敗死後、常盤御前を側女にしていた平清盛が飽きたので一条長成が貰い受けたのか?はわからないが、あの時代の女性は自分から「誰それと再婚する」なんて言い出さない、誰かにそうするように仕向けられただけ。
和田義盛と再婚?していた巴御前も同じだと思う。
あと、平安時代や鎌倉期ではまだ「側室」とは言ってなかったらしい。
「平清盛」でも「鎌倉殿の13人」でも正室以外の妻はドラマの中では側女(そばめ)と呼んでいる。
懐古主義ではないけど、なんというか、パンチ力に乏しい大河だと思う。見せ場がないというか。
義時なんているかいないか全然わからない。大河を見ない家族が主人公を政子だと思っていたこともあった。
細やかな心情表現をしてるのかもしれないけど、結局殺し合うんだからある程度シロクロはっきりさせてほしい。敵か味方か全然わからん。なんでミイがしゃしゃり出てきたのかも謎。
みいがしゃしゃり出てきたのにも大きな意味がありますよ。もうすぐあの夫婦も否応なく権力争いに巻き込まれていきますからね。そういえば全成の占い、実朝の乳母になるのは吉凶半ばでしたっけ。
小栗旬の力不足なのか脚本の弱さなのかそれとも意図的なのか、義時がいつまで経っても存在感が薄かったんだけど、頼朝が死んでいよいよ覚醒するのかしら。
でも、一方で、小池さん演じる北条政子は演技のうまさも相まって存在感たっぷりなので、これは作り手の差配ミスのような気がしないでもない。
とにかく、小栗義時、もっとしっかり画面を占領する圧が欲しいわ。
敵か味方かなどと言っていては、この鎌倉初期の御家人たちの内輪もめ、権力闘争は面白く見れないのではと思う。
また、義時は一応ドラマの主役ではあるが、ほとんどの事件の場合、首謀者ではない。時々の主役はむしろ時政と牧の方や、比企、三浦義村、和田、そして政子や頼朝の子たち。それぞれの思惑が時によってあっちについたりこっちについたり、わけがわからないから面白い。特にキーマンは三浦義村だと期待する。山本耕史が、鎌倉をかき回す、何を考えているかわからないくせ者を上手く演じてくれそうだ。
次の准主役は泰時というのをどこかで読んだ。そうなら、この時政、義時の時代の権力闘争の時期と、その次に来る泰時の御成敗式目や評定衆による合議制を布いた政治まで延ばして対比的にえがき、どちらにも重要人物であった義村も准主役であっても面白い。
日本沈没から鎌倉殿の13人まで続けて見てわかったのだが、小栗旬という人、あんまり演技が上手いとは言えないんだな。
大作というものに対しては、はっきり力不足だと思う。
これは、「プロフェッショナル」で彼自身も自分は演技が下手だから、とはっきり言っていたことで、
その時はまだよく知らなかったから、大河主演にまで選ばれてそれはないだろうと思ったのだが、こういうことだったのか、と。
何か俳優の独特の個性というか、突き抜けるようなものが感じられないんだよね。見ていてモヤモヤする。
これは、平和主義で心根が優しく出る杭になりたくない、というドラマ上の義時のキャラ設定とは全く別の話で。それならそれなりの魅力ある人間像が造形できるというのが俳優の才能のはずだが、どうもその辺りがなかなか充足されない。
要するに、「平々凡々」なんだよね。
実はそれを逆手に取ったキャスティングなのだ、義時はあくまでワンオブゼムなんだからそれでいいのだ、と作り手が考えてるとは、さすがに考えにくいしなあ。
小栗旬のテレビドラマのベストアクトは、リッチマン・プアウーマンだと思う。獣医ドリトルもよかった。日本沈没は脚本が悪い。鎌倉殿は、義時の見せ所はこれから。まだ全体を通しての評価はできない。
今までのところは、頼朝や大江広元や梶原景時たちがどのような考えで敢えて肉親や仲間を排除するのかを、側近として目の当たりにしてきたところを、よく演じていると思う。
今後はそういう判断を、自分が行って皆が納得する形での裁定をしていく苦悩と凄みをどう表現するかが問われる思う。
情報力と、筋道の通った論理的判断に長けた者が結果的に鎌倉のトップに立った。そこをどう表現するか、脚本と演技の見ものだ。
筋道の通った論理的判断というのは、前回、義時の言っていた、「私利私欲に走らず鎌倉を支えていく」ことを基本として行動していくことだと思う。
その事は、さっそく、頼朝の死直後から発揮され始めている。
「ここの何人も次の鎌倉殿を誰にするか決めることはできない。決めるのは御台所だけです。」
と紛糾する御家人たちの議論を義時が一喝したところが肝だった。
また、時政たちに、北条あっての鎌倉ではない、鎌倉が栄えてこそ北条も栄えていけると考えている、という見解の違いを明言したところだった。
鎌倉殿が武士たちに所領を安堵し、事あれば鎌倉殿につくすという、御家人たちの相互扶助の鎌倉体制の意義を、頼朝の近くで最も感じていたからこそ、義時は この先それに基づく判断をしていくのではないか。そしてそれは泰時に受け継がれていくのだと推察する。
そういう義時、泰時、及び大江広元たちと、その対極の私利私欲を全面に出してくる人たちと、何を判断基準にしているのか訳のわからない三浦義村など、脚本の自由度も高いので今後も面白くなるかもしれない。
主演が霞んでいるような。。。
頼朝役と義経役がなんか合わない。それから妙に肉付きのいい人がいたり朝シャンでキレイにサッパリしてそうな人や「よっしゃあ」という意気込みだけでトライしてそうな人など背景にまったく馴染まない。役者の人選においても即席カップ麺みたいな手軽さがどうにも納得いかない。見谷氏がそこに油を注ぐから余計にチープに見える。
一回抜けたのでTwitterは海水浴編で盛り上がってたけど、やっぱりドラマ再開が待ち遠しい。前半主役の頼朝が去り、いよいよ義時のターンが始まる。が、源氏の悲劇的な行く末、一枚岩ではなくなる北条、梶原比企畠山和田と欠けていく御家人たち。ハードな展開の中で救いは泰時の成長か。義時政子姉弟の修羅の道がどう描かれるのか楽しみだ。
小栗旬さんは真面目に役者道に精進しているイイ役者だと思う。彼ほど成長ぶりがはっきりとわかる役者はいないだろう。それは新人時代から彼の出演作を見ている人ならわかってもらえると思う。
この義時役はとても難しい役だ。だいたい主人公だが脇役という不思議な変なキャラだからだ。またそれを三谷氏が義時は何者?とミステリィー風にあまり感情表現させないように描いているので、よけい義時のキャラがややこしくなっているというしだい。つまり役者は主人公なのに目立たずそれでいて作品の中心にいるという奇妙な人物を演じないといけない。そんな無理難題を三谷氏は役者にさせているのだ。
まあー、普通の役者ならまずやりたがらないだろう。どう演じたらいいかわからないし、華もないし、見せ場もないし、つかみ所がなさ過ぎるのである。
だから小栗さんはよくやっていると思う。
もし三谷氏の脚本ではなく、吉川英治や司馬遼太郎や手塚治虫なんかが描くような、志と理想と信念を持ち、感情豊かで、激動期に傷だらけになりながら新しい時代を作った男の生き様を見せるというような北条義時なら、もっと小栗義時は面白かったしハマリ役になったと思う。
なぜなら、この大河、小栗旬さんの最大の武器のチャーミングなハニカミ笑顔があまり見れず、それが少しも生かされてないのだ。だが、その小栗義時ならあの笑顔がすごく生かされたと思う。それがほんと見てみたかった。
と、ここまで書いていて、気がついたが、小栗旬さんが来年の徳川家康や再来年の藤原道長やればすごいハマリ役になったのでは?
それもすごく見たかったな!
とにかくここまで来たら見守るのみですな!
髪の毛を切った
小っちゃい仏様?観音様?がいらっしゃった。
こういう本当に見逃しそうなシーンに号泣なのよ。
次回「鎌倉殿と13人」
え!!まだ始まってなかったの?
初回からずーっと13人の、人となりの紹介だった訳ね。
明日からの話を楽しむ為の、、、
小学生並みの幼稚な仲間入れ合戦で決まった評議衆の13人。
レベルが低すぎます。
13人が選ばれる過程を笑いも交えて描きながら、改めて御家人たちの人間関係も復習するという秀逸な脚本でした。家康が吾妻鏡を愛読してたのは有名だけど、特にこの初代将軍死後のゴタゴタは随分と参考にしたんじゃないかと想像する。
?小学生並みの幼稚な仲間入れ?
小学生の方が理想が高く、道理が通っているのでは。子供の力を侮るへからず。
御家人同士の露骨な勢力の張り合い、数合わせ、や疑心暗鬼が面白かった。
カリスマ性のある創業者が死亡した後会社がガタガタと崩れていくのは今でもよくある話。鎌倉幕府(当時幕府という名称は無かった。今作で用いられていないのは三谷幸喜が歴史マニアであることもあるだろう)を北条一族が引き継いでいなければこの時点で崩壊していたこのは確実。どんな形であれ存続したのは奇跡に近い。
頼家の時代に代わって、義時が活躍するのかなと期待したけど、相変わらず、チマチマしたドラマで面白くない。
余談だが、頼朝の病状は後鳥羽上皇が言っていたように、関白藤原道長と同じ。道長は生前、自身の臨終のとき、阿弥陀仏の手と自身の手を五色の紐で結んで、阿弥陀仏によって西国浄土に導かれることを願った。道長の親族はその通りにして道長を葬送した。
頼朝の葬送に関する文献資料はない。すごくラフな大河ドラマなのに、頼朝と藤原道長の葬送をドラマの中で酷似させる必要があったのかな?
存在感の際立つ初代鎌倉殿大泉洋をしっかり描き、その喪失をもって鎌倉を「柱がなくなった組織」としする脚本なので小栗義時が目立たないのは計算通りだし正解でしょう。
どの人物にも人物像にぶれがなく大勢を同時に動かす群像劇、楽しんでいます。
こりゃ頼家では持たないな。
誰もがそう思ったはずだ。
という事は源氏に代わる家が必要となる。
北条と比企が大ゲンカだな。
「佐々木のじいさんは?」義村「死にました」
「千葉のじいさんは?」義村「もう死にます」
義村「じいさんは止めときましょう」めちゃワロタ
鎌倉殿対13人。
時政『もうひとりいっとく』に笑った。
国盗り物語のような壮大なものではなく内部抗争を描いているので
チマチマしているのはしょうがない。でも人の持つ欲望だとか
野心だと家族愛だとかが凝縮されて描かれて引き込まれます。
二代鎌倉殿頼家を補佐するために設けた制度が、最初文官4人と梶原景時の5人から比企能育と北条時政が横やりを入れ、また政子の要請で義時まで加わり、13人まで増えて収まるまでをコメディータッチに描き痛快でした。また現代の政界の派閥争いのようで興味深かった。年上の大人たちに負けまいと対抗して若手を登用するのは若さゆえに焦る律儀で責任感のある頼家がよく描かれました。その裏で時政の正妻りくの野望や頼家の正妻つつじと側女せつが争う女の戦いや野望を持たない不甲斐ない全成をけしかける正妻実衣や義時をしたたかに支える正妻比奈や陰で北条のために尽力をする政子など女性陣も存在を見せて逞しく描いていました。その他、都の公家たちと交流を深めるため蹴鞠を嗜むなど現代のゴルフ接待を彷彿させて800年前を描いても人のやることは変わらないことを思わせて面白かった。
第27回「鎌倉殿と十三人」
巻刈りの時、「九郎殿なら・・・」と物申して反発された景時が頼家に一番信用されているというのが意外だった。「義時を除いて御家人の中で頼朝の生前、腹を割って頼家に話した御家人は景時だけだったという事か」と最初思ったが、後の比奈の発言で頼家は「困った時ほど、まわりに助けを求めない性格」と判明。「あの時、景時には邪険な態度をとったが内心は嬉しかった」のが真相という事か。つきあい辛い人が鎌倉殿になったものだ。
私は義時は「主役」扱いだけれども「狂言回し」のつもりで観ている。いないと困るのだけれども、目立ってはいけない存在みたいな。突飛な例えだがアニメ「キテレツ大百科」のキテレツのように、主役なんだけれども本人はさほど活躍せずに、ストーリーの手綱の引き締め役みたいな。原作より脇の登場人物が目立つところも似ていて、三谷さんは今作をあんな感じで義時を軸扱いにして、脇役たちの見せ場を活き活きと描いた作品にしたいのではないかと最近は観ていて思えてくる。彼らを補佐したり助言したりして、物語の進行を良くする為に彼をあのポジションにしているのではないかと。たまには義時が主役の話も観たい願望はもちろん有るが。
文(ふみ)は無しで鎌倉から京へ頼朝死すへの便りは場面省略、後鳥羽上皇(尾上松也)の台詞でそれが示唆されるのみ。淋しい!。楽しみにしている物が出て来ないと自分は何を伝えたくてレビューを書くのだろう、という気持ちになります。
死んだ、もうすぐ死ぬ、爺さんはやめときましょう
これは
山本耕史にしか言えない。
言わせる三谷幸喜恐るべし
以前の大河ドラマの「 草燃える 」のときに北条政子を演じていた岩下志麻さんの演技は、如何にも北条政子という雰囲気がありましたが、小池栄子さんが演じている北条政子も、なかなかどうしていい雰囲気を醸し出していて好感が持てますよね。ですから、これからのお話の展開には、凄く期待ができると思います。そして、その小池栄子さんには、小池栄子さんなりの個性的な北条政子像を創って欲しいですね!!
爺さんとか何とか言っても登場時から何十年も経過しているのに同じ人物がずっと演じているから今の年齢が何歳なのか全く分からない。年表などを手元にして見ている人は少ないだろう。
ディモンティ高岸さん栃木GB入団おめでとうございます。
ネタバレになってしまうけど、もうあの仁田殿は北条と比企の争いで最期を遂げもう撮了したのでしょう。オリキャラならあのまま最終回まで出てほしかったです。
大河はこの時期をどう見せるかで決まるようなものだけど、これはきついなあ。チマチマ感が半端ないホント。きつい。見出したらおもしろいんだけど見るのによっこらせと気合いがいるようになってきた。北条政子以外の女性たちがチャチャ入れるのが邪魔。
これ以上視聴率が落ちると次の家康にマジで抜かれるかも。
5人のはずがどんどん増えて13人になって
まさに船頭多くしてなんとやらにならなければいいが(笑)
頼家の今の立場は父信玄が偉大だった武田勝頼となんかかぶりますね
最後「北条が2人入っておった」と数合わせに執着する時政パパにガックリ。これでは、比企と変わらないではないか。嫌な夫婦が、合わせ鏡のように2組に増えた。
全成と実衣もそれに合わせるかのようにいびつな夫婦関係になり、北条の皆が良い人に見えたのは頼朝という強い柱が有ったからこそだというのが露見してしまった皮肉。いや頼朝に関わってしまったから?、どちらにせよ皮肉。これなら、頼家の乳母夫(めのと)になる前に比企を滅ぼしておけば・・・と思ってしまう。頼朝が生きているうちにそうしていたら、鎌倉時代の歴史はかなり変わっていただろう。
変わっていないのは自分の家一族より鎌倉の事を考える義時親子と政子のみ。彼ら以外の「猛き者も遂には滅びぬ」となってもおかしくない方向へ捻り始めた展開の妙。第1回から基本いい人だった時政や実衣が討ち取られる立場に巻き込まれ、反転していく脚本が巧みだ。
三谷幸喜が前説にたっぷり前半を費やしておいて本当に描きたかったのはまさにここからの後半の展開。
騙し騙され、裏切り裏切られ、殺し殺され合うドロドロ展開は鎌倉版「仁義なき戦い」そのものだ。ここまで長く描かれた各人物に愛着が湧いてきているだけに「あの人が?」「え、この人まで?」となるのは間違いない。本題である後半だけを描いていたら全く面白くならなかっただろう。ここに至るまでの前半に食材の調理時間を長く費やしていたからこそ最高の料理の数々となって視聴者に饗されるのだ。
おそらく最終回に清廉潔白な人物として生き残っているのは坂口健太郎ただ一人だろう(笑)あとは山本耕史ぐらいだろうが清廉潔白ではない(笑)
とにかく今回の三谷大河は大河ドラマの長尺を最大限利用してフルコースのメインである後半を盛り上げるという最高に贅沢な作劇方法だ。コメディが得意な吉田照幸の演出も合っている。
まさに巴の言った通り「人は変わるのです」。あの時は大姫の人生が開けそうな前向きの、希望の言葉のように聞こえたのに。本当に皮肉。
義時と腹を割って話せる三浦義村が良い味出してる。
真田丸の三成も良かったが、三谷さんは山本耕史の使い方が上手い。
13人に入ってるのは父義澄の方だが、義村のこれからの活躍にも期待。
義村は何で女性と2ショットになるシーンが多いんでしょうか?。「女たらし」という設定だとしても、そういう女をくどくシチュエーションではなくても女性キャラが1人でいるところになぜかいる、現れるシーンが多いですよね。田舎で野良仕事に励むりくさんと話すシーン、八重さん最後のシーンの川で鶴丸をバトンタッチで受け取り陸に上げて助けるシーン、外で熱で倒れる大姫を抱きとめるシーン・・・くどくというより、「鎌倉の女の動向はみんな俺は知ってるぜ」という感じで、女性キャラの前では八面六臂の活躍。
わざと脚本で「そういう女がらみの場面なら彼」とばかりに書いてるんでしょうけど、前に八重に預けた「俺の子供」の母親の所在含め、本当にこの人の女性関連の話をオープンに物語化して欲しいなあと思うくらい、興味そそられる事象なのであります。
スポンサーリンク